宝亀10年2月8日(779年2月28日) 淡海三船、鑑真の伝記『唐大和上東征伝』を撰する。
平安後期の写本『唐大和上東征伝 高山寺本』(五島美術館)が重要文化財。
『唐大和上東征伝』は、宝亀十年(七七九)に淡海真人三船(元開)が著した鑑真の伝記で、鑑真の従僧思託の撰した『大唐伝戒師僧名記大和鑑真伝』(三巻)などをもとに一巻にまとめたもので、思託の撰した伝が失われたため、この『東征伝』が鑑真の伝記の基本資料となっている。
本帖は、その平安時代後期の古写本で、体裁は粘葉装、茶地の原表紙を存し(裏表紙は後補)、中央に「唐大和上東征傳一帖鑒真傳也」と外題があり、左下に「使唐沙門章觀之」と墨書があるが「章觀之」の三文字は墨で抹消されている。本文の料紙は楮紙で、半葉七行に押界を施して用い、通帖一筆に書写し、文字の誤脱等を同筆にて補っている。本文中、鑑真の将来品目を掲げた箇所などに、ところどころ余白があるが、これは親本の欠脱等をそのまま空白にして書写したものと考えられ、誤脱の訂正とあわせて書写の態度が厳正であったことを窺わせている。尾題と「寶龜十年歳次己未二月八日己卯撰」の撰述奥書についで、元開、思託、石上宅嗣らの鑑真追悼の詩七首を収め、帖末には「交畢」の校合奥書と老後に金峯山寺に施入すべき旨の奥書が本文と同筆で書かれている。書写奥書はないが、表紙にみえる章観については、高山寺典籍文書類(重要文化財)のなかに同人の書写した本があり、本帖はそれらと同筆であることから、十二世紀中葉頃の章観の書写になることが判明する(ただし章観の伝記等は未詳)。
本帖は首尾に「高山寺」の朱方印が捺され、また表紙に「五十五箱」と朱書があるのが鎌倉時代の高山寺の聖教目録の記載と合致して、もと高山寺に伝来したことが知られる。『唐大和上東征伝』の最古写本としては、十二世紀前半頃の書写になる観智院本が知られているが、本帖はこれにつぐもので、観智院本等の諸本と比較して字句等に異同があり、『東征伝』の本文研究上に重要な写本である。
文化庁国指定文化財等データベースより
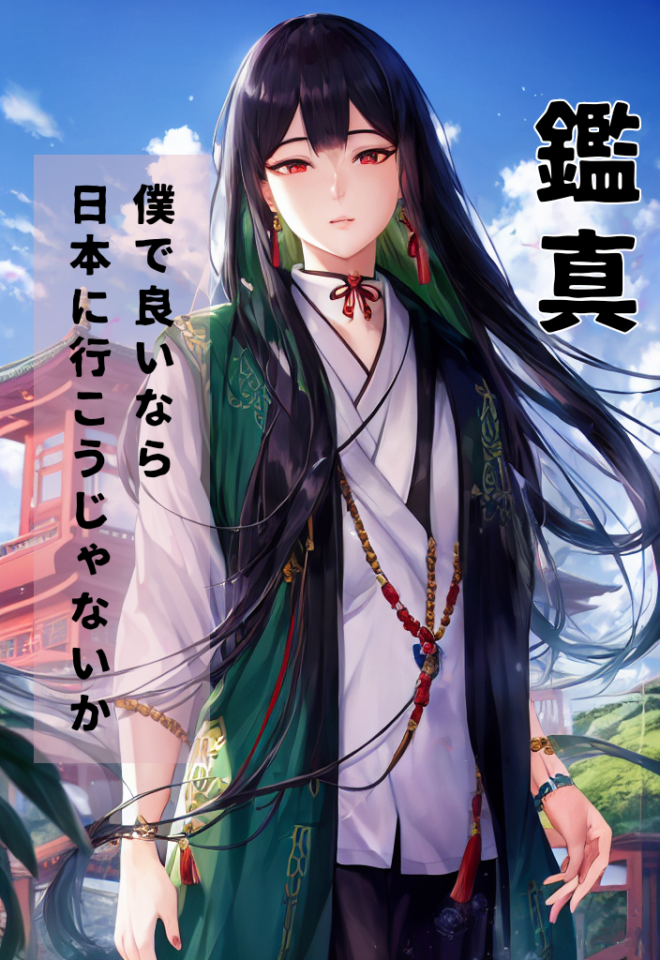






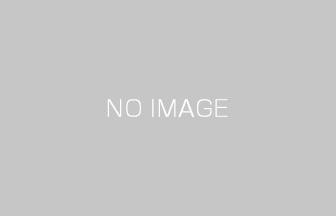

この記事へのコメントはありません。