明治2年3月12日(1869年4月23日) 明治天皇が天皇として初めて伊勢神宮を参拝。
伊勢神宮には、未婚の皇女が斎王として伊勢に常駐していましたが、天皇が参拝したことは歴史上ありませんでした。その理由としては、伊勢神宮の地に足を踏み入れることがタブーだったと考えられます。『日本書紀』によると、第10代崇神天皇の時代、天皇が住む宮中にアマテラスと大和大国神の2神を一緒にまつっていましたが、疫病や災害が起こり、神の怒りだとして皇女の豊鍬入姫(とよすきいりひめ)に託して、大和の笠縫邑に厳重な神域磯城神籬(しきのひもろぎ)を立ててまつりました。さらに次の11代垂仁天皇の時代にも、改めて皇女倭姫に託し、鎮祭すべきところを求めて近江や美濃を巡って、最後に伊勢に到達し、五十鈴川上に斎宮(いわいのみや)を立て、まつったのが、伊勢神宮の内宮の起源となっています。ちなみに倭姫は、おいっこのヤマトタケルに、三種の神器のひとつ天叢雲剣(草薙の剣)を与える女性です。つまるところ、伊勢の神とは天皇に「たたる」神だという認識だったわけです。



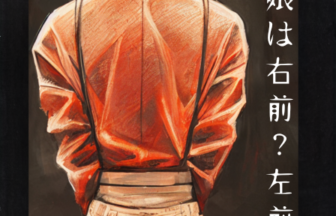





この記事へのコメントはありません。