【日曜日の夜 21:00 郊外のスーパー銭湯「太閤の湯」・マンガコーナー】
(お風呂上がりのポカポカした中、館内着をまとうエミとサキが、巨大クッションにその身体を埋もらせている。サキはフルーツ牛乳を片手に、エミはオロナミンCをポカリスエットでわった「オロボ」を飲みながら本を読んでいる)
サキ:ぷはーっ! お風呂上がりのフルーツ牛乳、なんでこんなに美味しいんだろ〜。生き返るぅ〜。……って、あれ? エミちゃん、マンガ読まないの? 今日は『鬼滅』全巻読破するんじゃなかったっけ?
エミ:ふふ、予定変更よ。さっきサキちゃんと露天風呂に入ってたら、ふと歴史の“湯けむり”が見えちゃってね。カバンからこの本を引っ張り出してきたの。下川耿史さんの『混浴と日本史』。
サキ:えっ、混浴!? またそんな刺激的な……。でも、エミちゃんが読むってことは、単なるHな本じゃないんでしょ?
エミ:もちろん。これは筑摩書房から出ている、日本の入浴文化の深層に迫る硬派な歴史書よ。
ねえサキちゃん、今年の大河ドラマ『べらぼう』と、来年の大河ドラマ『豊臣兄弟!』。この二つの作品をつなぐ隠れたキーワードが何か分かる?
サキ:えー? 『べらぼう』は江戸時代の出版王・蔦屋重三郎の話でしょ? 来年の『豊臣兄弟!』は戦国時代の秀吉と弟の秀長だよね。時代も違うし……共通点なんてあるの?
エミ:ふふふ。答えはズバリ、『お風呂』よ。
もっと正確に言うなら、「豊臣秀吉が熱狂させ、松平定信が凍りつかせた“混浴”という文化」ね。
この本を読むと、その因縁の歴史が手に取るように分かるの。まずは、そもそも日本人がどんな風にお風呂に入っていたか、この本で少しだけ振り返ってみましょうか。
サキ:うん、手短にお願いね。のぼせそうだから(笑)
古代〜奈良:おおらかな「歌垣」から、仏教の「功徳湯」へ
エミ:日本人の入浴のルーツはとても自然でオープンなものだったの。古代の『歌垣(うたがき)』のように、水辺での水浴びは男女の出会いの場でもあったわ。
でも、奈良時代に国家ができると、少し様子が変わってくる。仏教が伝来して、お風呂が「宗教的な施し」になったの。
サキ:宗教的な施し?
エミ:そう。東大寺などの大寺院で行われた『功徳湯(くどくゆ)』よ。これは庶民を無料で入浴させて、清潔と健康、そして仏教のありがたさを教えるチャリティー活動だったの。
そして驚くことに、このお寺のお風呂も、基本的には混浴だったと考えられているわ。
サキ:えっ! お寺なのに混浴!? お坊さんに怒られないの?
エミ:当時は巨大な鉄の湯釜が一つしかなかったから、男女別にする余裕なんてなかったのよ。それに庶民にとって混浴は温泉地での当たり前の習慣だったから、誰も「わいせつだ」なんて思わなかった。
光明皇后がハンセン病患者の背中を流した「千人施浴」の伝説も、この流れにあるのよ。仏様の前での裸は、あくまで清らかなものだったのね。
秀吉と混浴の蜜月:混浴文化の黄金期
サキ:へぇ〜、昔の人はおおらかだったんだね。で、そこからどうやって秀吉につながるの?
エミ:ここからが本番よ。来年の大河ドラマの准主役、豊臣秀吉。彼こそが、日本のお風呂文化を『清らかな施し』から『欲望渦巻くエンターテインメント』へと変貌させた張本人なの。
サキ:ええっ、秀吉が!? 何したの?
エミ:秀吉が天下を統一したのは1590年(天正18年)。戦乱が終わって世の中が平和になると、人々は娯楽を求め始めるわ。
秀吉はその前年の1589年(天正17年)に、戦乱で荒れ果てた京都の街を再建するために、家来の原三郎左衛門が願い出た遊郭の開設のアイデアに飛びついたわけ。秀吉は工事中には自ら馬を駆って進行状況を視察したくらい熱を入れていたの。それが、江戸の吉原に並ぶ京都の島原遊郭ね。
サキ:色ごとが好きな秀吉らしいわね。
エミ:続いて1590年、秀吉の居城大坂城のある大坂で『湯女風呂』の第一号がオープンしたの。これも当然、秀吉の許可がないとできなかったでしょうね。
一五九〇年、大阪に風呂屋が生まれ、同時に湯女も現れたというのである。垢をすり髪を洗うので髪洗い女とも呼ばれた。髪を洗うのでいつも櫛を頭にさしていたというわけである。
サキ:湯女風呂って、普通のお風呂屋さんとは違うの?
エミ:全然違うわ。湯女風呂は、お風呂屋さんというより『簡易遊郭』に近かったの。
お風呂にお客を入れるだけでなく、背中を流し、髪を洗い、さらにはお茶やお菓子を出して、三味線を弾いて歌い……そして別室で『密接なサービス』も提供していた。
つまりこれ、秀吉の遊郭政策とセットっていうわけよ。
サキ:うわぁ……。天下人が率先して『夜の街』を作ったんだ。
エミ:そうなの。この『公認遊郭』の誕生とほぼ同時に、もっと手軽に遊べる場所として『湯女風呂』が生まれた。つまり秀吉の時代は、お風呂が単なる衛生の場から、『女と男が入り乱れる快楽の空間』へと劇的に進化した転換点だったのよ。
闇夜のワンダーランド「ざくろ口」と松平定信の怒り
サキ:へぇ〜、天下人によってお風呂がお洒落でエッチな場所になったんだ。それが江戸時代も続いたの?
エミ:ええ。江戸時代になると、さらにディープになるわ。江戸の銭湯には「ざくろ口」という独特の入り口があったの。
これは浴室の熱気を逃さないために、入り口を低くして、中は湯気でモウモウにしてたの。しかも窓が少なくて薄暗い。
そんな暗闇の中で、男女が入り乱れて入浴してたのよ。当然、そこで何が起きるかというと……
サキ:……あ(察し)。なんかドキドキしてきた。
エミ:ふふ。でも、そんな「パラダイス」を許さない男が現れる。それが今年の大河ドラマ『べらぼう』の後半で猛威を振るう、松平定信よ。寛政の改革を断行した超・堅物の彼にとって、この男女入り乱れる湯女風呂や混浴なんて、道徳的堕落の極みでしかなかったの。
サキ:あー、定信さん、ドラマでもなんか厳しそうな顔してたもんね。「不潔極まりない!」とか言いそう。
エミ:まさにそれ。定信は1791年(寛政3年)、ついに『男女混浴禁止令(男女入り込み湯禁制)』を発令したわ。「風俗に悪影響があるから、銭湯は男女別々にしろ!」ってね。
それまでも禁止令はあったけど、定信の改革は本気度が違った。彼は出版統制を行って、蔦屋重三郎のような版元や、山東京伝のような作家も処罰したでしょ? それと同じ文脈で、お風呂という庶民の楽しみにもメスを入れたのよ。
サキ:うへぇ、表立った出版も規制され、暗い場所の秘め事も全部規制しちゃうんだ。息苦しかっただろうなぁ。
エミ:でもね、面白いのはここから。お上(幕府)がいくら「混浴禁止!」って叫んでも、江戸っ子たちはなかなか従わなかったの。
銭湯の経営者たちは「男女別々にしたら、釜も浴槽も二つ必要になってコストがかかる!」って猛反発。
結局、浴槽の真ん中に板一枚の仕切りを入れただけの「底はつながってる」状態にしたり、脱衣所は一緒だったり……。
当時の川柳に《山の手の湯は女人とへだてなし》なんて詠まれているように、なかなか規制は行き届かなかったみたいね。
サキ:あはは! 板一枚って、ほぼ混浴じゃん! 江戸っ子強い!
エミ:そう。秀吉が種を蒔き、江戸の泰平の中で花開いた「混浴」「湯女」という猥雑だけど爛熟した文化。それを儒教的な道徳で縛り付けようとした松平定信。この「快楽 vs 規律」の戦いこそが、日本の入浴史のハイライトなの。
結局、混浴が完全に姿を消すのは、明治時代になって西洋人の目を気にするようになってから。それまでは、日本人は「裸の付き合い」を何よりも愛していたのよ。
極東にあらわれた極楽空間は健在!
サキ:そっかぁ……。今年の大河と来年の大河が、お風呂でつながってるなんて思わなかった。
秀吉の時代はイケイケで、定信の時代はシュンとしちゃって……。歴史って、行ったり来たりしてるんだね。
エミ:ええ。でも、どんなに時代が変わっても、お湯に浸かって心身を解き放ちたいという日本人の欲求は変わらないわ。
……ほら、サキちゃん。そろそろ私たちも現代の功徳湯を楽しみましょ?
サキ:えっ? 現代の功徳湯?
エミ:(マッサージ機のコーナーを指差して)あそこよ。最新鋭の揉み玉が、極上の奉仕をしてくれるわ。
サキ:あはは! 機械かーい!でも、それもいいけどさ……
(ゴロンと転がっていたサキは正座すると、エミの頭を太ももに乗せて、髪をなでなでしはじめる)
サキ:今は混浴はほとんどなくても、こうやって館内着を着たら男女関係なくごろごろとリラックスできるのは、日本文化のおかげよね。
エミ:ちょ、ちょっとサキちゃん、ここ公共の場よ? 人が見てるじゃない(苦笑)
サキ:いいじゃ〜ん。ここは現代の「ざくろ口」の中よ。ねえエミちゃん、髪の毛まだ濡れてるよ? 後で乾かしてあげよっか?
エミ:……もう。子供扱いしないでよ。
サキ:えへへ。だってエミちゃんの髪、サラサラで触ると気持ちいいんだもん。
あ、そうだ。マッサージ機もいいけど、私がエミちゃんの肩揉んであげる! これぞ正真正銘、現代の『湯女』サービス!定信公に怒られないように変なことは無しよ♡
エミ:(顔を真っ赤にして)……あ、当たり前じゃん…そんなことしたら出禁になっちゃう。今夜はサキちゃんの『おもてなし』に甘えさせてもらおうかしら。
サキ: は~い♡。殿様、お疲れみたいですね、肩こってますよ~。
【参考文献】下川耿史『混浴と日本史』(筑摩書房)



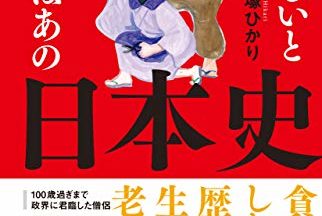


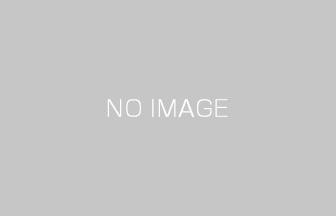

この記事へのコメントはありません。