推古30年2月22日(622年4月8日) 推古天皇の摂政皇太子の聖徳太子が斑鳩宮で亡くなりました。49歳。法隆寺釈迦如来像(国宝)光背銘・中宮寺天寿国曼荼羅繍帳(国宝)から。一方、日本書紀では推古29年2月5日没としています。
天寿国曼荼羅繍帳は現存日本最古の刺繍。亀の中に一文字ずつ書かれて、全体で一つの銘になるが、これだけでは判読不可能で、聖徳太子の伝記史料集『上宮聖徳法王帝説』と照らし合わせることで、欠損部分を補い、この刺繍が作られた理由についての銘文の復原が可能となっています。
推古天皇30年(622年)2月22日に聖徳太子が没したあとに、その妃である多至波奈大女郎(推古天皇の孫)が、推古天皇に聖徳太子が往生した先と考えられる天寿国の状態を刺繍で描いて、夫を偲びたいと願い出たので、渡来系の東漢末賢、高麗加西溢、漢奴加己利が下絵を描き、同じく渡来系の椋部秦久麻が指導して、采女たちが2帳の繍帳(ししゅう)を作ったとの刺繍の制作の経緯が書かれています。
2月5日の記事で紹介した、平安時代に仏師が聖徳太子の7歳像を造った日付が2月5日であるのは、日本書紀に書かれた没年に従ったためと思われます。というのも、天寿国曼荼羅繍帳は長らく行方不明で、再発見されたのが、鎌倉時代の文永11年(1274年)だからです。

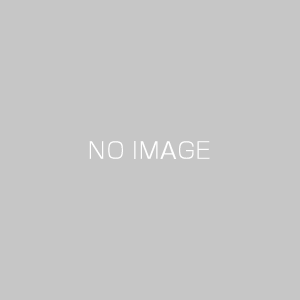







この記事へのコメントはありません。