ユダヤ人難民へビザを出して命を救った在リトアニアの外交官杉原千畝の軌跡は、本人が晩年までほとんど語らなかったこともあり、妻の杉原幸子氏の『六千人の命のビザ』が第1の根本史料となっている。
ただ、本人やその家族の回顧については、記憶違いなどからそのままその言葉を信じることは歴史学では認められていない。言葉を換えれば、その言葉を疑ってかかり、ほかの史料と照らし合わせて、真実を浮かび上がらせることが必要だ。
むろん、杉原千畝がとった行動が英雄的ではあるが、本のタイトルの6000人がそもそも根拠がない(ビザの発給数は2000台)など、感覚的な記憶については、検証が必要という部分を明らかにしておくことは、歴史が未来の人たちへの役に立てるためにも重要だと考える。
例えば、将来に外交官が杉原を見習って人道的な処置をしたときに、幸子氏が思っているように「ビザの発行が違反行為だった」と認識すると、躊躇するかもしれない。杉原が外務省に反して行ったとすることは杉原をより英雄的にみせるが、実際は杉原はこの行為に対して罰を与えられたことはなく、ギリギリの適法の範囲で出していたというのが事実である。
将来の外交官は、杉原が適法、裁量の範囲内でギリギリの人道的な行為を実施していたという史実を踏まえていれば、彼(彼女)もまた自分ができる限界まで挑戦することができるかもしれない。
こうした視点(うがった見方)から『六千人の命のビザ』を読んでみると、杉原千畝がスパイ活動を伴うインテリジェンス・オフィサーであったことがよくわかる。千畝が命のビザについても、後世までみずから語らなかったのも、インテリジェンス・オフィサーとしての一生の役目だからだろう。
6000人のビザの根拠は、幸子氏のこの本にしかないとされている。その部分は、77ページの「プラハで夫はカウナスの領事館の引き揚げについての書類を整理していました。本省から各国の外交官に、発給したビザの枚数を報告するようにという指示が出されていました。一九四一年二月二十八日付けで送った報告書には、七月九日から八月二十六日まで発給したビザの数が合計二一三九枚と書かれていました。しかし、八月に入ってからはビザの発給に番号をつけることも止めてしまっていましたので、実際に発給した枚数はこれよりも多かったのです。子供たちを連れていたこともあり、実際に日本を通って各国に逃れたユダヤ人の数は、六千人以上にものぼったと言われています」
その後の調査で、杉原はきちんとビザの数をカウントして把握していたことがわかる。実務上、そうしないと偽のビザなどと判断されて日本に入国できなくなるからだ。たしかに子供の名がリストにないものの家族で日本へ行ったケースもあるが、子供の名前もきちんとリストにのっているケースもあり、またビザは発行してもらったものの結局リトアニアを出国しないケースもあり、杉原のビザで逃れた人数は、ビザ発行の実数である2139をの数倍などということはなく、2000人台と考えられる。
本書は、意外にも杉原の諜報活動をしていたことも明示している。ロシア語が堪能な杉原はリトアニアのあと、プラハ(チェコ)の領事、ケーニヒスブルグ(リトアニア<すでにロシア>に隣接する東プロイセン)の総領事代理、ルーマニアのブカレストの公使館と転任して、語学を使った諜報活動をしていたことがわかる。
一方で驚いたのは、幸子氏の映画のような脱出劇だ。
1944年5月、アメリカの空襲が激しくなり別荘地に疎開していたのだが、ソ連のブカレスト侵攻が迫り、幸子氏は単身、ブカレストの家に置いていたフィンランドの作曲家シベリウスのレコードと写真をとりに戻ろうとした。ブカレストの手前で、「今、ブカレストの街では市街戦が行われている」と聞かされ、ドイツ兵とともに近くの森に隠れた。デューラーという若い将校が護衛役となり、パルチザンに包囲された戦線を脱出する。砲弾が狂ったように飛び激しい音が頭の上を過ぎます。若い将校は全身で私の身体を覆い、息を殺して私は目を閉じていました。茫とした私の意識の中を、弾丸の音が掠め、気がつくと、私の身体は軽くなって草の上に放り出されていました。
砲声は全く止んでいました。傍らに目をやると、草に半ば埋もれるように若い将校が横たわっています。怖る怖る手を触れて、彼の名前を呼んでみました。
「デューラー!」
答えが返ってきません。
夜明けの淡い光の中に、若い将校は眠ったようにかすかな微笑みを口もとにに浮かべて、息絶えていました。
(略)
何か足元がおかしいと思ってみると、いつのまにかハイヒールの踵が折れていました。戦火の中を夢中で駆けていたので気付かなかったのです。
(116ー117ページ)
なんと、ハイヒールで戦場を歩いていたというのだ。
劇的な生還だった。
その後、ソ連に家族で抑留され、ドイツ軍の誇り高い将兵と日本軍の抑留者の「下品さ」を比較している。ただ、これは戦闘中の兵と、武装解除されたあとの兵との違いの可能性もあり、感情的な比較かもしれない。
男ばかりの収容所で女性は珍しかったのでしょう。私はルーマニアの森の中でドイツ軍と一緒にいた時のことを思い比べてしまいました。ドイツ兵の中に、女性の私がいても、兵隊たちは知らん顔をしていました。もちろん、シャワーを浴びている時に覗きにくるなどという人はいなかったのです。小さい頃からの躾の違いなのか、日本人とヨーロッパの男性との違いを感じさせられた経験でした(142ページ)
帰国後の杉原は、外務省をクビになる。
「ああ、外務次官の岡崎さんの部屋に呼ばれて、<君のポストはもうないのです、退職して戴きたい>と言われた」
夫はポツリと言うと、黙り込んでしまいました。かなり後になって、岡崎次官に「例の件によって責任を問われている。省としてもかばい切れないのです」と言われたことを聞きました。
(150ページ)
この「かなり後になって」の言葉、杉原がビザ問題でクビになったとみなされているのだ。基本的に、千畝本人は弁明していないようだ。
すぐあとにこうある。
私の胸には言いたいことが渦巻いていました。夫の胸中も同じだったに違いありません。しかし夫は自分のしたことについては弁解はしない。余計なことは言わない人でした。ですから、ひと言の弁解もせずに引き下がってきたのです。当時、GHQの命令で、各省庁では大幅な人員整理が行われていました。外務省にとってみれば、夫は当然その中に含まれるべき者として扱われたのです。
(150ページ)
つまり、このクビになった理由付けは、本人ではなく妻の感情からの解釈であることがわかる。
むしろ、杉原本人はクビの原因を、学歴にあったとみている節がある。つまりノンキャリアだから、東京帝大卒のキャリアの雇用を守るために切られたのだ、と。実際、その面も強そうだ。
その後、杉原は語学を生かして、進駐軍の仕事や商社で働く。腕(語学)があるノンキャリア外交官だからこそ、ある意味で簡単に就職先が見つかるだろうから「くび」という判断もあったのかもしれない。
夫は長男の弘樹に「外務省に入れ」と言っていたようです。自分の果たせなかった夢を託したかったのに違いありません。
「東大を出ていなければ、役人の世界では昇進が遅れる」
弘樹にそう言った言葉は、夫が外務省で感じていた長年の思いだったのでしょう。(159ページ)
妻は夫の思いをこう忖度しているが、実際、杉原がインテリジェンス・オフィサー(情報外交官)としての仕事をどう評価していたかはわからないが、妻のいうように「恨み」を抱えていたよりも、単純に海外の仕事のおもしろさに素直に「魅了」されていた可能性が高いのではないだろうか。
実際、杉原は一時、科学技術庁に入り「官僚」になったにもかかわらず、昭和35年から川上貿易のモスクワ事務所長として、15年にわたりソ連で単身赴任を続ける。昭和50年、70歳までソ連に赴任していたのだ。当時はソ連である。
つまり、貿易が目的といえでも、ソ連からも、日本からも、あらゆる面で「情報」が求められた。民間にあっても、インテリジェンス・オフィサーとしての任務は多かっただろう。千畝はロシア語のスペシャリストで、戦前はソ連への外交官としての就任をソ連から断られている(ビザを出さない)。それだけやり手のインテリジェンス・オフィサーだったのだ。
ソ連から赴任が認められたということは、なんらかの暗黙の「契約」があったのだろう。
それは「人道的な外交官」としての杉原の一面とはかなり違う物語かもしれない。しかし、杉原本人が最も輝き、本人が満足していたのは、むしろこの戦後の仕事だったかもしれない。


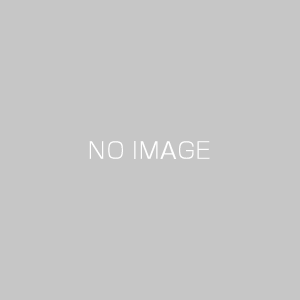






この記事へのコメントはありません。