エミがサキを家に招いて『べらぼう』の最新話を一緒に見終わりました。
サキ: はぁ〜、今週のべらぼうも面白かった! 蔦重、やってくれるね! まさに江戸時代の天才プロデューサーだよ。
エミ: うん、本当に。歌麿の浮世絵とかが、江戸だけじゃなく全国に広まっていく様子、ワクワクする。あれぞまさしくメディアの力だよね。
サキ: 幕府(政治)がガチガチに藩っていうタテ割り社会を作ってるのに、文化(アート)の力は、その藩のボーダーを軽々と越えていってる感じがたまらない。
エミ: …サキちゃん、良いところに気づいたね。でもね、私はあのドラマを見ていて、逆のことを考えてたんだ。
サキ: え、逆?
エミ: 文化(アート)がボーダーを越えたんじゃなくて、もうとっくにボーダーが崩壊してたから、蔦屋重三郎はあれだけ派手に活躍できたんじゃないかって。
サキ: え? どういうこと? 幕末・明治維新よりずっと前だよ?
エミ: 政治(幕府)が作ったボーダーはね。でも、経済のボーダーは、あの時代(江戸中期)にはもう消えてたんだよ。
サキ: 経済のボーダー?
エミ: 例えば塩は江戸中期に全国で作られなくなっていくのよ。
サキ: 塩? 海岸があるところならみんな作れそうだから、地産地消してるんじゃなくて?
エミ: それが、まったくしてない。『森林飽和』(太田猛彦著)って本によると、流通が発達しすぎたせいで、効率よく作れる瀬戸内海沿岸の十州塩田が、1760年ごろには全国の生産量の9割を占めてたっていうの。
サキ: 9割!? じゃあ、他の地域の塩田は…
エミ: 価格競争で全滅。もう地産地消はとっくに消えてたの。都立図書館で『加賀藩の流通経済と城下町金沢』(中野節子著)という専門書で見つけたんだけど、あの百万石の加賀藩ですら、自給自足できなくて、瀬戸内から塩を買ってたってぐらいだから。
サキ: うわ、石川県、めっちゃ海に囲まれているのに、知らなかった…。政治的には藩に分かれてるのに、経済的には瀬戸内産の塩がないと生きていけない、ボーダレスな全国市場がとっくに完成してたんだ。
エミ: そういうこと!だから、蔦屋重三郎がべらぼうで成功できた本当の理由の一つは、彼の才能だけじゃなく、塩や米の商人たちがすでに作り上げていた全国の流通網(ボーダレスな市場)に、彼が浮世絵という新しい商品を乗せることに成功したから。
サキ: なるほど!蔦屋重三郎がゼロから道を作ったんじゃなくて、もう高速道路(流通網)はあったんだ!彼がやったのは、そこにアートっていう最高にクールなスポーツカーを走らせることだったんだね!
エミ: まさに!そんな感じよ!地産地消が無くなっていく代わりに、ほかに全国に一気に広まったものもあるの、わかる?
サキ: 全然、わからないんだけど?
エミ: 答えは金魚よ。金魚を飼育する文化が庶民にまで一気に広がったのが浮世絵と同じく江戸中期なのよ。
サキ: 浮世絵は当時、錦絵だっけ? 金魚も錦鯉っぽいもんね(笑)
エミ: ははは、確かに錦だ! ともかく、塩をはじめとする経済のボーダレス化が、浮世絵など文化のボーダレス化を生んだって構図なんだよ。そう考えると、私たちが幕末・明治維新って呼んでるものは、ただ政治がその事実に追いついただけ…って思えてこない?
サキ: うわー…その視点で来週のべらぼう見たら、また全然違って見えそう。エミちゃん、深い! また来週もべらぼう見にきてもいい?
エミ: もちろん! 塩ちゃんこ作って待ってる!







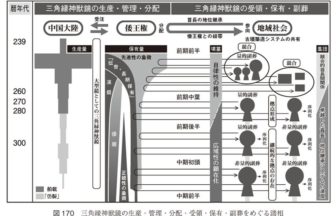

この記事へのコメントはありません。