【月曜の夜 エミの書斎(通称:歴史探偵部屋)】
(壁一面の本棚に囲まれた部屋で、エミが優雅に紅茶を飲んでいると、ドアが勢いよく開く)
サキ:大変だよ、エミちゃん! いや、ホームズちゃん!
エミ:(ティーカップを置き、ゆっくりと振り返って)なんだね、そんなに慌てて。サキちゃん、いや、ワトソンくん。
サキ:そんな悠長なこと言ってる場合じゃないよぉ! 今、SNSの歴史クラスタ界隈が大炎上してるの! 大河ドラマ『べらぼう』のせいだよ!
エミ:ほう? 横浜流星くんが蔦屋重三郎を演じる、あのドラマだね。何がそんなに燃えているんだい?
サキ:何言ってるの、きのう一緒に見たじゃん!「写楽の正体」よ! ドラマでは「写楽は存在しない、みんなで作った虚像だ」って設定になっていたじゃん。そしたら「史実と違う!」とか「金出してたの松平定信かよ!」とか、もう喧々諤々なんだから!
エミ:ああ、なるほどね。……ふふっ
サキ:えっ、何落ち着いて笑ってるの?SNSの論争(バトル)に参加してNHKを叩かなくていいの?
エミ:いや、いいじゃない。私なんかむしろ感動したよ。『いいぞもっとやれ!』って思ったくらい。
サキ:ええっ!? 確かにきのうエミちゃん「もっとやれ」ってつぶやいてたかも。でもエミちゃんってガチガチの歴史クラスタじゃん。「史実を守れー!」って怒る側だと思ってたのに!
エミ:ふふふ、サキちゃん、プロファイリングしようか。Wikipedia止まりの歴クラはこう思ってる。『写楽の正体は長年の謎だったけど、最近の研究で“阿波の能役者・斎藤十郎兵衛”だって判明した。だからドラマもそう描くべきだ!』って。
サキ:え、違うの? ネットニュースでもそんな感じだったけど。
エミ:(ティーカップをクイッと上げて)ふふふ。甘い、甘いわワトソンくん。まず、この『国史大辞典』を見てみなさい。
(エミが背中の本棚から分厚い辞典を開き、指差す)
サキ:あっ、そっか!真の歴史クラスタはまず国史大辞典をチェックするんだっけ。
幕末の考証家斎藤月岑は「俗称斎藤十郎兵衛、居江戸八丁堀に住す、阿波侯の能役者也」と考察しており(『(増補)浮世絵類考』)、注目されるが、いまだ確認されていない。【国史大辞典:東洲斎写楽(執筆:小林忠)】
サキ:えっと……『いまだ確認されていない』って書いてあるよ? ほら、やっぱり謎だったんじゃん!
エミ:そこじゃないのよ。重要なのは、この『国史大辞典』が刊行されたのは何十年も前だけど、その時点で既に『斎藤十郎兵衛説』は一番有力な説として載ってるってことなの。つまり、『写楽=斎藤十郎兵衛』説自体は、別に新しい発見でもなんでもないの。
サキ:あ、そうなんだ。昔からある説なんだね。
エミ:そうなの、歴史研究を舐めちゃいけない。じゃあ、なんで最近になって『斎藤説確定!』って騒がれたと思う?
サキ:うーん……何か決定的な証拠が出たとか?
エミ:だいたいご名答。こっちの『新版 歌舞伎事典』を見てごらん。同じコバチュウさんが書いた項目だけど、ここにはこう書いてあるわ。
ところが近年〈写楽斎〉と号する浮世絵師が八丁堀の地蔵橋辺に居住していたことが知られるようになり(《諸家人名江戸方角分》)、旧説への関心が高まりつつある。【新版 歌舞伎事典:東洲斎写楽(執筆:小林忠)】
サキ:……んん? 『写楽斎』っていう絵師が、八丁堀に住んでたことが分かった? それだけ?
エミ:そう。整理するとこうなるわ。
1. 写楽がいた時期より50年くらいあとの幕末の歴史研究者(考証家)による『浮世絵類考』に「写楽は八丁堀に住む阿波藩の能役者斎藤十郎兵衛だよ」って書いてあった。
2. でも、誰もその証拠を見つけられなかったから、「いやいや、別人説もあるでしょ(北斎説とか)」って言われてた。
3. 戦後になって、発見された、写楽が生きていた頃に編まれた人名辞典『諸家人名江戸方角分』にも、「八丁堀地蔵橋に『写楽斎』って人が住んでたよ」って記述が見つかった。
4. 近年、阿波藩の能役者斎藤十郎兵衛についてはその存在が確実視される研究が積みあがっている。
サキ:わおっ! じゃあ、やっぱり『写楽=斎藤十郎兵衛』で決まりじゃん!
エミ:……本当にそう言い切れる?
サキ:へ?
エミ:考えてみて。『八丁堀に写楽斎って人が住んでた』という事実と、『阿波の能役者・斎藤十郎兵衛が写楽である』という事実。これ、イコールで結べる?
サキ:えっ……と、写楽さんがそこに住んでて……斎藤十郎兵衛もそこに住んでたら……同一人物……かもっては思っちゃうけど?
エミ:そう、この2人は確かに条件が似ている人物ではあるのは間違いないわ、でもそれってそれこそ幕末の考証家はそれに気づいたからこそ、写楽=斎藤十郎兵衛説をあげていたんじゃないのかしら。だから、本来は、いくら斎藤十郎兵衛の実在性や八丁堀に住んでいたかを証明しても、『能役者の斎藤十郎兵衛が写楽でした』とはならないのよ。
サキ:あ……!そう言われれば、そうね。
「正体探し」はもう古い? むしろ
エミ: (紅茶を一口飲み、少し遠い目をして) ……でもね、サキちゃん。私、正直に言うと『写楽は誰か?』っていう犯人探し自体、もう歴史探偵としては不毛な段階に入ってると思うのよ
サキ: えっ? 不毛? だって正体わかったらスッキリするじゃん!
エミ: それが罠よ。いい? 学術の世界ではね、写楽研究はもう次のステージ……いわば『情報に基づく不可知論』という境地に達しているの
サキ: ふ、ふかちろん……? 何それ、必殺技?
エミ: ふふ。簡単に言えば、『今の資料だけじゃ、神様でもない限り絶対に正解は出せないと分かった。だから、無理に犯人を決めつけるのはやめて、この“現象”そのものを楽しもう』っていう、大人の諦めと悟りの境地よ
サキ: へぇ……なんかカッコいいけど、ちょっと負け惜しみっぽくない?
エミ: 失礼な(笑)。でも聞いて。さっきの『斎藤十郎兵衛説』も、実は決定的な弱点があるの。 一つは、その根拠となる資料が、写楽の時代から数十年も後に書かれた『また聞き』レベルのものだってこと。信頼性が低いのよ
サキ: あー、噂話みたいなものか
エミ: もう一つは、『作風の不一致』。能役者だったはずの十郎兵衛が、なぜ能の絵じゃなくて、歌舞伎役者の、しかもあんなにアクの強い絵を描いたのか。その動機が説明できないの
サキ: 確かに。能と歌舞伎じゃ全然違うもんね
エミ: 他にも『北斎説』とか『歌麿説』とか、巨匠たちが変名を使った説もあったけど、どれも決定打に欠ける。あの強烈な個性は、誰の画風とも似てないし、たった10ヶ月で消えた理由も説明がつかない
サキ: じゃあ、結局どうすればいいの? 迷宮入り?
エミ: そこで有力視されているのが、個人を特定するんじゃなくて、当時の社会状況から読み解く『無名集団・版元による匿名説』よ!
サキ: 匿名……集団? まさに大河ドラマ『べらぼう』の内容と完全に一致するじゃん!ていうか、あれって学説だったの?
エミ: 実はそうなのよ。まったくの創作じゃないってところが今年の「べらぼう」のやばい(褒めてる)ところなのよ。当時の「寛政の改革」で出版規制が厳しかった時代。版元の蔦屋重三郎(蔦重)は、自分の名前で出せないような斬新すぎる絵を世に出すために、『写楽』というペンネームを使って、ある種の“隠れ蓑”にしたんじゃないかという説よ
サキ: えっ、じゃあ写楽って人は本当にいなかったかもしれないの?
エミ: 特定の個人ではなく、蔦屋が組織した『匿名集団(プロジェクトチーム)』だった可能性があるの。その根拠とされているのが、写楽の作品に残る『微妙な揺らぎ』よ
サキ: 揺らぎ?
エミ: 写楽の活動期間はたったの10ヶ月 。でもその短い間に、初期、中期、後期で、絵の完成度や表現方法に、一人の人間が描いたとは思えないような審美的な不一致(ズレ)があるのよ
サキ: あー! 最初はすごく上手だったのに、急に下手になったりしたって聞いたことあるかも!
エミ: そう。この不一致は、特定の時期にだけ蔦屋の指示の下で『複数の異なる才能』が一時的に活動したからじゃないか、って説明できるの。あるいは、政治的な配慮から徹底的に個性を消して匿名化を図った結果、作風が揺らいだのかもしれない
サキ: なるほどぉ! 一人の天才がスランプになったんじゃなくて、そもそも描いてる人が違ったかもしれないんだ!
エミ: この説の面白いところは、写楽という存在を『個人の伝記(誰が描いたか)』としてではなく、『寛政時代の出版業界の制約(社会学的な現象)』として捉え直している点にあるの。 蔦屋重三郎というプロデューサーが、厳しい規制をかいくぐってでも世に問いたかった『写楽という現象』。そう考えると、一人の正体を探すよりずっとドラマチックじゃない?
サキ: うんうん! 『チーム写楽』が権力と戦ってたってことだね! なんか燃える! あっ、今SNSが燃えてるのって、こっちのほうで燃えてるのかな?
エミ: そうかもしれないね。写楽はいなかったを批判する歴クラに対して、写楽はいなかった説も歴史説でしょって別の歴クラが対抗して燃え盛っているのかもしれないわね。
サキ: そっかぁ! 実は歴クラVS歴クラのバトルになってるのかもね!
エミ: 写楽はある特定の一人でないという考えは、文学(フィクション)の世界では、いろいろ花開いているわ。2024年11月、つまりちょうど1年前に文芸春秋から刊行された谷津矢車『憧れ写楽』っていう小説なんかでは、もっと面白い新説が出てるのよ。『写楽は二人いた』説。
サキ: 二人!?
エミ: 能役者の斎藤十郎兵衛が『いくつかの絵は自分が描いたけど、あの有名な大首絵(大谷鬼次とか)は俺じゃない』って告白する展開なの。蔦重が複数の才能を混ぜ合わせて『写楽』という怪物を作り上げた……そんなミステリーよ
サキ: うわぁ、ぞくぞくする! それドラマでやってほしい!
エミ: 去年の11月の本だから、当然NHKはこの内容を知っている。だから、べらぼうでは、斎藤十郎兵衛説にも、作者2人説にも、最初からスルーする方針だったのかもしれない。だからね、サキちゃん。『分からないからこそ、無限の物語が生まれる』。この空白こそが、写楽が私たちに残してくれた最大の遺産なのよ
サキ: へぇ〜……。エミちゃんって、たまにすごく良いこと言うよね。たまにだけど。
エミ: (ガーン!なにげに動揺するエミ)ま、まぁ、まぁ、あわわ、あわわ。
サキ: (サキは微笑んで優しくエミの手をふわりと両手で握る)「エミちゃんの推理はいつも冴えてるよ♡ きょうも素敵なお話ありがとう! じゃあ私は『写楽は未来から来た宇宙人説』を推すから、星空の天体観測してくる!
エミ: うー……寒いの苦手だけど、さきちゃんに星座教えてもらいに一緒にいく~
(エミは探偵の帽子を脱ぎ捨てると暖かい毛の帽子にかえてさきの後ろから手を組んで家を出る)






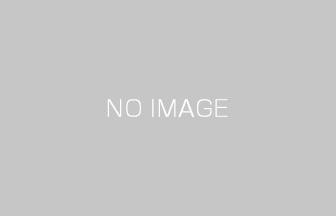
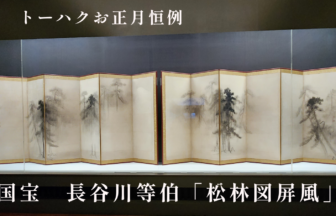
この記事へのコメントはありません。