
エミが淹れたての紅茶をサキに手渡す。サキは両手でカップを包み込み、一口飲んで息をつく
サキ:ふぅ、美味しい…。あったまる。……で、エミちゃん。『国史大辞典』の美術史の話って?
エミ:ああ、そうそう。さっき(前編で)「考古学」みたいな新しい分野は、刊行が古い(1979年)“あ行”だと情報が古いことがあるって話、したでしょ。
サキ:うん。あ行の「阿倍比羅夫」の項目に、考古学的には覆された”古い”情報が載っているって話だったよね」
エミ:その通り。美術史、特に近代以降についてはどうかなって、同じ“あ行”の『青木繁(あおきしげる)』を調べてみたら、面白いことが分かったの。
サキ:青木繁? アーティゾン美術館の《海の幸》で有名なあの若くして亡くなった天才画家?
エミ:そう。彼の《海の幸》も《わだつみのいろこの宮》も、どっちも重要文化財(重文)指定されてる、超・代表作よね。でもね、『国史大辞典』の「青木繁」の項目には……。
サキ:まさか……
エミ:一言も『重要文化財』って書いてないの」
サキ:ええー!? なんで? あ、そっか!“あ行”だから刊行が古くて、まだ重文に指定されてなかったとか?
エミ:いい推理だし、私もそうかなって最初は思ったんだけど、ブブー。指定されたのは1967年。『国史大辞典』の刊行(1979年)より12年も前。だから、執筆者の先生は”知ってて書かなかった”ことになるの」
コンテンツ
始まりは2023年の「重要文化財の秘密」展
サキ:え、なんでだろう。国宝とか重要文化財に指定されているかって重要な情報だよね。
エミ:そう、国宝についてはおそらくほとんどの場合、国宝って明記されているわ。重要文化財って万単位だからいちいちつけたらきりがないから載せない、って編集方針も別に自然だと思うわ、紙の辞書だから文字数制限もあるし。ただ、近代(明治)以降の美術作品って現代でも建築物を除いて国宝って指定されていないの、だから近代美術については重要文化財がトップ、なのだから、書いても良いとも思うよね。
サキ:お上(国)が決めた美術の価値なんて関係ないっとか(笑)
エミ:うん、それは当たっている気がするな。私も「国の格付けより、美術史上の“意味”が大事!」みたいな美術史家のプライドかなって思ったし、おおむねそれが理由のようなのだけど。……でもね、サキちゃん。この話にはもっと深い“闇”がある。というか、私がこの『重要文化財の秘密』に気づいたキッカケは最近のある展覧会だったの
サキ:キッカケ?
エミ:令和5年(2023年)に、東京国立近代美術館で、その名も『重要文化財の秘密』展っていうのがあったのよ。
サキ:そのまんまじゃん(笑)
エミ:そうヒミツ(笑)。その展覧会の図録と目録がこれでね(と、本棚から図録を抜き出してサキに見せる)。この展覧会が何よりスゴかったのは、「明治以降の絵画・彫刻・工芸で重要文化財に指定された全68件」という“全リスト”を、私たちに示してくれたことなの。
サキ:へー! 68件しかないんだ。確かに国宝級に厳選されているみたいだね。
重要文化財(美術工芸品)は1万872件もあるんだね
エミ:そうなの。私はこのリストを“答え”として、『国史大辞典』の項目を片っ端からチェックしたわけ。リストに載ってる画家、例えば『青木繁』『板谷波山』『岸田劉生』『狩野芳崖』『菱田春草』『横山大観』『宮川香山』… 全員よ」
サキ:うわ、マニアックすぎる…
エミ:そしたら、とんでもない“ルール”が見えてきたの。さっきの『青木繁』(×)問題。これと対になるのが、“は行”(1990年刊)の『菱田春草(ひしだ しゅんそう)』や”や行”(1993年刊)の『横山大観』。こっちには、バッチリ『重要文化財』って書いてあるのよ。つまり(〇)ね」
サキ:はぁ!? なんで!? あ、それこそさっき(前編)の『あ行とわ行で15年の差がある』って話でしょ! 1979年の“あ行”と1990年代の“は行””や行”じゃ、編集ルールが変わったんだよ!
エミ:私もそう思ったの。でもね、サキちゃん。(と、〇×△リストを見せる)この一覧を見て。もっと深い“闇”というか、“強烈な性格”が隠れてる。
サキ:な、なにこれ、見ても大丈夫なリストなの?(笑)
重要文化財に指定されている近代作家は次の通り、〇と×は国史大辞典でその作品が重要文化財と明記されているかどうか、1993年以降に重文指定されたものは刊行時未指定で△としていまっす。()は項目ごとの筆者です)
【あ行】
「浅井忠(×)(富山 秀男)」
「青木繁(×)(原田 実)」
「朝倉文夫(△)(富山 秀男)」
「板谷波山(△)(富山 秀男)」
「今村紫紅(×)(富山 秀男)」
「上村松園(△)(富山 秀男)」
「海野勝珉(△)(富山 秀男)
「荻原守衛(×)(富山 秀男)」
【か行】
「狩野芳崖(〇)(宮川 寅雄)」
「川合玉堂(×)(宮川 寅雄)」
「鏑木清方(△)(宮川 寅雄)」
「岸田劉生(×)(宮川 寅雄)」
「黒田清輝(〇)(隈元 謙次郎)」
「小出楢重(×)(宮川 寅雄)」
「小林古径(△)(宮川 寅雄)」
【さ行】
「下村観山(×)(三輪 英夫)」
「新海竹太郎(△)(富山 秀男)」
「鈴木長吉(△)」立項されず
「清風与平(△)」立項されず
「関根正二(△)(原田 実)」
【た行】
「高村光雲(△)(三木 多聞)」
「竹内栖鳳(〇)(中村 溪男)」
「富岡鉄斎(×)(細野 正信)」
「土田麦僊(△)(中村 溪男)」
「高橋由一(×)(佐々木 静一)」
【な行】
「中村彝(×)(原田 実)」
【は行】
「橋本雅邦(×)(細野 正信)」
「速水御舟(〇)(中村 溪男)」
「原田直次郎(△)(原田 実)」
「菱田春草(〇)(中村 溪男)」
「平福百穂(△)(中村 溪男)」
「福田平八郎(△)(中村 溪男)」
「藤島武二(×)(原田 実)」
【ま行】
「前田青邨(△)(中村 溪男)」
「松岡映丘(△)(中村 溪男)」
「宮川香山(△)」立項されず
「濤川惣助(△)(南 邦男)」
「村上華岳(△)(細野 正信)」
【や行】
「安田靫彦(△)(中村 溪男)」
「山本芳翠(△)(三輪 英夫)」
「横山大観(〇)(中村 溪男)」
「萬鉄五郎(△)(富山 秀男)」
【ら行】
「ヴィンツェンツォ・ラグーザ(×)(三木 多聞)」
【わ行】
「和田三造(△)(小倉 忠夫)」
国史大辞典に「重文」と書かれる芸術家と書かれない芸術家
エミ: 2023年の『重要文化財の秘密』展のリストのおかげで、“答え”が全部わかったの。刊行された後に重要文化財に指定された作家については『△』として、分析から外すわね。
サキ: あ、そっか。『国史大辞典』が書かれた時点ではまだ重文じゃなかったんだから、書けないのは当たり前だもんね。
エミ: その通り。で、その『△』を除外すると、刊行時点で“すでに重文だった”作家は20人。そのうち、『国史大辞典』に『重文』と明記された(〇)のが6人、明記されなかった(×)のが14人になるの。
サキ: 14対6! 7割以上は、重文だって“知ってた”のに書かれなかったんだ!?
エミ: そうなの。しかもね、このリスト(〇×△リスト)を見ると、さっきの『先生の好み』説も、もっと深掘りできる。例えば、重文の近代作家の項目を一番多く書いてる美術史家の中村溪男先生。
サキ: うんうん
エミ: 中村先生が書いた重文作家のうち、『竹内栖鳳』『菱田春草』『速水御舟』『横山大観』は(〇)なの。でも、彼が書いた他の重文作家――『土田麦僊』『平福百穂』『前田青邨』『安田靫彦』――は、全員『△』!
サキ: え、それってつまり……
エミ: 中村先生は、自分の担当項目で“刊行時に重文だった”作家(栖鳳、春草、御舟、大観)には、全員重文であることを書いている。彼は(×)を使ってないの。ある意味ですごくフェアでしょ」
サキ: ほんとだ! じゃあ、誰が(〇)(×)を使いわけているの?」
エミ: 「例えば、美術史家の宮川寅雄先生。彼は『狩野芳崖』には重文と書いた(〇)。でも、同じく彼の担当で、刊行時に重文だった『川合玉堂』『岸田劉生』それに『小出楢重』には、重文と書いていない、つまり(×)の対応をとった」
サキ: うわっ! 中村先生と全然違う! 宮川先生は、意図的に『書く・書かない』を選んでるんだ!
エミ: そういうこと! この『選別』こそが“思想”なのよ。じゃあ、その選別の違いを深堀りしようか。
「重文」と書いてもらえなかった14人
浅井忠
青木繁
今村紫紅
荻原守衛
川合玉堂
岸田劉生
小出楢重
下村観山
富岡鉄斎
高橋由一
中村彝
橋本雅邦
藤島武二
ヴィンツェンツォ・ラグーザ
エミ:ふふふ。逆に、『重文』とわざわざ書いてもらえた(〇)画家を全員並べてみようか。この6人よ。
国史大辞典”公認”重文作家6人に共通するのは?
1. 狩野芳崖(かのう ほうがい)
2. 黒田清輝(くろだ せいき)
3. 竹内栖鳳(たけうち せいほう)
4. 菱田春草(ひしだ しゅんそう)
5. 速水御舟(はやみ ぎょしゅう)
6. 横山大観(よこやま たいかん)
サキ: うーん……黒田清輝と横山大観は一般にもよく知られたビッグネームだと思うけど。
エミ: そうね、かなり有名人たちであることは間違いないわね。でも、書いてもらえなかった(×)の《鮭》の高橋由一や《麗子微笑》の岸田劉生だって、作品の有名度からしたらむしろ上かもしれないでしょ。線引きした違いはどうやらそこじゃないみたい。この6人は、明治時代に『近代美術』というレールとシステムそのものを作り上げた“創始者(ファウンダー)”たちなのよ」
サキ: 「創始者?」
エミ: 「そう。狩野芳崖は名前のとおり狩野派だったけど、フェノロサと岡倉天心がプロデュースする新しい「日本画」を描いていった近代日本画の礎を作った人。菱田春草と横山大観は、その岡倉天心の指導のもと日本美術院(東京の日本画アカデミズム)を創設した人たち。 速水御舟は、その日本美術院に(彼らより後の世代として)参加し、画風そのものを革新した天才ね。
黒田清輝は、フランスの画風を持ち込んで日本の洋画アカデミズムを確立した人物。竹内栖鳳は、東京の人にはなじみが薄いかもしれないけど、京都画壇を革新した人物。ここらへんは、東京と京都のバランスもあるのかな。
つまり、『国史大辞典』の先生方は、『重文かどうか』『絵が有名か』で判断したんじゃなくて……
サキ: あ、わかったかも! 『この人は“創始者”だから超エライ!』っていう美術史学の世界での“評価”がまずあって、その“証拠”として『重要文化財』って称号をちゃんと添えておきましょう、みたいな?
エミ: それそれ!完全に同意!! これはもう『ブレ』ですらない。強烈な“アカデミズム史観”と、さっき言った“東京・京都のバランス感覚”の表れであり、美術史学内での『序列意識』がいみじくも発露したものなのよ!
サキ: うわー、なんかパンドラの箱開いちゃった感じ。
エミ: でも、ここで国史大辞典の強みも忘れてはいけないの。黒田清輝、横山大観、竹内栖鳳のような業界の重鎮・大御所だから、ということではないってこと。
サキ: どういうこと?
エミ: 速水御舟は42歳、菱田春草は38歳と若くして亡くなっているの。あくまで、国史大辞典は「大物だから」ではなく「レールを創造したファウンダーだから」という視点を重視しているの。横山大観や黒田清輝、竹内栖鳳は、その“レール”を敷いた上で、さらに長生きして組織のトップ=「大物」にもなったけど、それは結果論。
一方、菱田春草と速水御舟は、“組織のトップ”として君臨することはなかったけど、「朦朧体(もうろうたい)」(春草)や、その後の「細密描写と象徴表現の融合」(御舟)という、後世に続く『新しいレール』そのものを創造した「歴史」は揺るがないわけ。『国史大辞典』の執筆陣の先生たちは、その“組織的な功績”と、“画風上の革新的な功績”を同等に「ファウンダー」の仕事として評価し、(〇)(×)を分けていたんだと思う。
サキ: そっか!さすが最強の歴史辞書だね!
第2の闇 立項すらされなかった巨匠たち
エミ: ……でね、サキちゃん。このリスト、実はもっと恐ろしい『第二の闇』も示してるの。
サキ: え、まだあるの!?
エミ: 『重要文化財の秘密』展のリストには、①「板谷波山」②「海野勝珉」③「初代宮川香山」④「鈴木長吉」⑤「三代清風与平」⑥「濤川惣助」といった『工芸家』も6人載ってる。つまり現時点ではかなりの数の工芸作品が重要文化財に指定されているってこと。じゃあ、彼らは『国史大辞典』でどう扱われてるか……
サキ: どうせほとんど(×)なんでしょ?
エミ: ところが、(×)どころか、『立項されず』――つまり、項目そのものが存在しないのが6人中3人なのよ!(初代宮川香山、鈴木長吉
三代清風与平)
サキ: ええええええっ!? 重文作家なのに!?
エミ: そうなの。でもね、同じ『工芸』でも、陶芸の板谷波山、七宝の濤川惣助、彫金の海野勝珉の3人は、ちゃんと項目が作られてる。この差、なんだと思う?
サキ: もうわかんないよ……
エミ: これも『アカデミズム史観』なのよ。『国史大辞典』の思想はこうなの。
板谷波山、濤川惣助、海野勝珉 = 個人の“作品”を作った『芸術家(アーティスト)』
初代宮川香山、鈴木長吉、三代清風与平 = 優れた“製品”を作った『名工(クラフトマン)』
『芸術家』は“歴史”として項目を作るけど、『名工』は“産業史”だから項目を作らない。そういう強烈な『ジャンル史観』(アート>クラフト)が働いてるのよ。
サキ: うわぁ……。重文っていう“格付け”以前に、辞書に載るか載らないかの“選別”がすでに行われてたんだ……
エミ: これは近代化の負の産物と言われているわ。江戸時代まで日本では美術と工芸っていうジャンル分けはなかったんだけど、欧米では「fine art」>「craft」という序列があったのだけど、そんな序列を知らない日本人が「FineArt」を美術と訳して、工芸を「Crafts」って訳しちゃったのが原因なんだ。
サキ: 岡倉天心とかはそんな序列を意識していなかったかもしれないけど、のちの「美術史業界」が勝手に美術>工芸ってランク付けをしていったってことかしら。
エミ: そういうこと。この『国史大辞典』は、単なる事実のデータベースじゃない。1980年代〜90年代の日本の歴史学・美術史学が持っていた『思想』そのものの結晶なのよ。もっとも、21世紀になると美術史学もそんな評価は変えていくの。2001年に初めて工芸部門で鈴木長吉の「鷲」が重要文化財に指定されたの。その後、この6人が21世紀になってどどっと重文作家になったというわけ。
サキ: うわー……正当に評価されたのって割と最近のことなんだね。
エミ: 『国史大辞典』って、ただの辞書じゃなくて、もう“評価の書物”、存在そのものが歴史なんだよ…
サキ: ……なんか、深すぎて怖い。歴史業界の光と闇の書だ……。
エミ: 闇っていうか、強烈な“思想”ね(笑)。だから、辞書はただ『事実』が書いてある本じゃない。何を選んで、何を書かず、どう評価するか。そこに“性格”が出るのよ。2023年の『重要文化財の秘密』展は、図らずも、この『国史大辞典』という“思想のモニュメント”の性格をあぶり出す、最高のリトマス試験紙になってくれたの。
サキ:(紅茶を飲み干して)……なんか、お茶飲んでるだけなのに、すごい疲れた。でも、めちゃくちゃ面白かった。エミちゃん、次は何を解読するの?
エミ:ふふ。それはまた、次のお茶の時間にね。またサキちゃんが我が家に遊びに来てくれるまでに仕込んでおくわ。


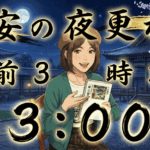





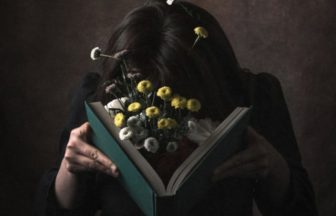
この記事へのコメントはありません。