
エミの部屋。リビングの壁一面が、天井までの本棚で埋め尽くされている。本棚には和書、洋書、画集、そして大量の辞典類が整然と並んでいます。
サキ:うわぁ…。エミちゃんの部屋、すごすぎ。なんか、TSUTAYAの図書館みたいだね!
エミ:ちょっとサキちゃん、やめてよー! TSUTAYAはやめてーっ。せめて「東洋文庫ミュージアム」の本棚って言ってよー!(わざとらしい悲鳴)

サキ:あはは、ごめんごめん。でもさ、この辞典コーナー、場所取りすぎじゃない? 特にこの真ん中の『国史大辞典』って、一体何巻あるの?
コンテンツ
日本史業界最強のツール「国史大辞典」
エミ:ふふふ。よくぞ気づいたね、ワトソン君、いやサキちゃん。 吉川弘文館の『国史大辞典』は、日本歴史の全領域を網羅する総項目数6万6,600を収めた日本史百科で全15巻(17冊)、文字総数はなんと3200万字よ。まぁ、歴史マニアにとって、スマホみたいなものね。
サキ:スマホ? 全然似てないじゃん。こんな重いし、Wi-Fiも飛ばないし。
エミ:“ないと生きていけない”ってこと! 私たち歴史ライターがブログや小説書くときは、まず『国史大辞典』で“通説”を確認するの。これが全ての基準点(リファレンス)になるからよ。
サキ:ふーん。でもさ、それってウィキペディア(Wikipedia)で良くない? 正直、ウィキの方が情報早いし、タダだし。
エミ:(カチッとスイッチが入る)サキちゃん、それが一番大事なとこっ!ウィキは「いろんな情報源をまとめたもの」でしょ? 言うなれば三次資料。誰が書いてるかも、ぶっちゃけ分からない。たまにWiki編集者さんの“クセ”も強いときがあるし。
サキ:あー、なんか分かるかも。編集合戦も多いし、情報量は豊富でも信頼性があるかっていったら、ウィキを思考のスタートにはできないよね。
エミ:そうなの。でも、この『国史大辞典』は、ワンランク上の二次資料なの。一流の歴史学者が、古文書とかを死ぬほど読み込んで、「これが今の学界のスタンダードな見解です」って、自分の“名前を出して”書いてるの。信頼度がダンチなのよ。
揺らがなかった豊臣秀吉の歴史上の初出年
サキ:へー。じゃあ、来年の大河ドラマ絡みで、豊臣秀吉を調べたら、ウィキと全然違うこと書いてあるの?
エミ:そこが面白いんだって! 例えば「豊臣秀吉が最初に歴史の資料に出てくるのはいつ?」っていう問題。ウィキも『国史大辞典』も『永禄八年(1565年)だよ』って書いてる。ここまでは同じ。
サキ:なんだ、同じじゃん。
エミ:違うの! ウィキは「そうらしいよ」「諸説あります」って書いてるだけ。でも『国史大辞典』がそう書いた後、最近(2015年~2024年)に最新の調査研究に基づく『豊臣秀吉文書集』(名古屋市博物館編、全9巻)っていうのが出たんだけど、やっぱり永禄八年が最初だったの。4半世紀経っても通説が揺らがなかった。この“本物感”、ヤバくない?
サキ:ヤ、ヤバい…かも?(エミちゃんも)

最強の歴史辞書の弱点は「あいうえお順」?
エミ:でもね、この最強の『国史大辞典』にも、もちろん“弱点”があってね。
サキ:へぇ、そうなの?
エミ:これ、『あいうえお順』で刊行されたから、“あ行”の第1巻が出たの、なんと1979年なのよ。で、「や行~わ行」の第14巻が出たのは1993年(最終巻の索引の
サキ:うわ、古っ! 私生まれてないし!「あ」と「わ」で15年も差があるの?
エミ:でしょ? 例えば『阿部比羅夫(あべのひらふ)』って項目を見ると、比羅夫が今の北海道あたりで戦った「粛慎(みしはせ)」っていう謎の民族について、『国史大辞典』は「アイヌのことかな?」(この粛慎については、蝦夷と異なるもので、おそらくはアイヌではないかと思われる。)って書いてるの。
サキ:ふむふむ。
エミ:でも、その“後”に中国の歴史学や考古学が進んで、「粛慎(しゅくしん)」は「オホーツク文化人」っていう、アイヌとも日本人とも違う人たちだって分かってきた。ウィキは、その最新情報(オホーツク文化)をちゃんと載せてる。こういう考古学とか科学が絡むと、『国史大辞典』は古いことがあるのよ。特に早い刊の項目はそれが目立つわ。
ちなみに国史大辞典でも1992年刊行の第13巻の「粛慎(みしはせ)」の項目で「中国大陸から樺太・北海道方面に渡来したツングース系民族とみる説、朝廷に服属しない蝦夷に対して用いられた中国風の雅名とする説、その他諸説ある」としています。
サキ:なるほどー! 得意分野が違うんだ。
国史大辞典で鉄壁の防御陣を敷いてから冒険(新説)に乗り出そう!
エミ:歴史学では王道中の王道だから、私はまず“幹”である『国史大辞典』で通説をガッチリ固めて、そこからウィキや最新論文で“枝葉”(新説)をチェックするの。文献史学という歴史業界の保守本流のテーマでは、この幹から外れることは、歴史小説とかフィクションならいいけど、ノンフィクションなら、冒険が過ぎて危険ですらあるわ。でも、文献史学からちょっと外れた「考古学」や「美術史」みたいなときは、最強のチートモードではなくなるのが「国史大辞典」なの。
サキ:うわ、マニアックすぎる…いや深い…。ていうかエミちゃん、この話、お茶飲みながらで良くない? 私、立ってたら足しびれたんだけど。
エミ:あ、ごめん! 熱く語りすぎた。今、最高の紅茶いれる!次は、「美術史」で『国史大辞典』を分析すると、さらに国史大辞典の弱点、というか特徴をあぶりだせるよ!
サキ:う、うん。エミちゃんが熱く語るのを眺めるのが楽しいから熱いお茶を飲みながら聞かせてね。
続き→



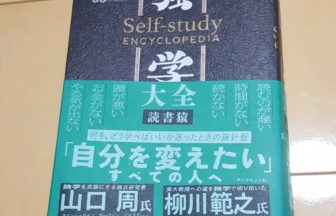

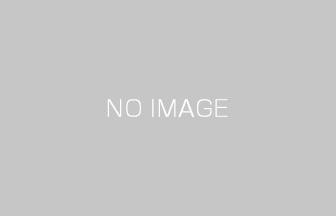
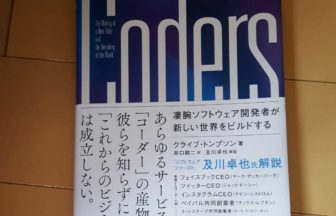
『国史大辞典』とWikipediaという二大情報源の「性格」の違いが、非常に分かりやすかったです