エドガー・アラン・ポーのパンデミック短編小説「赤き死の仮面」を日本語訳しました。原典はすでにパブリックドメインです。翻訳したもとの英語はこちら(Wikisource)
「赤死病」は長い間、かの国を荒廃させていた。これほど致命的で恐ろしい疫病はなかった。血は、その化身であり、血の赤さと恐怖はその印章であった。感染すると、鋭い痛みと突然のめまいが起こり、毛穴から大量に出血し、体中が溶けるように、死んでいった。
特に感染者の顔にあらわれる緋色の汚れは、疫病を示す禁忌であり、顔面にその兆候を見せた人は、とたんに治療や同情の対象から外された。この病気は発症から、進行、終息までがわずか三十分間に押し寄せる圧倒的な死の病であったからだ。
この国にプロスペロー公という恐れ知らずで、勇敢で、そして幸せに満ちた王子がいた。領地の半分の民が死んだ時、彼は宮廷の騎士や公女の中から千人の仲の良いものを集め、彼らと一緒に城壁の奥にある宮殿の奥の院へと逃げ込んだ。この奥の院は、王子自身の奇抜でありながらも高貴な趣味が生んだ、広大で壮大な建造物だった。厚くて高い壁に囲まれており、壁には鉄の門があった。
廷臣たちは中に入ると、炉と金づちを持ってきて内側から門を溶接した。彼らは孤立することで、外の絶望やパニックによる狂乱から逃れることを決めたのだ。奥の院には十分な備えがあったので、ひきこもることで伝染病に抵抗することができた。外の世界は自分自身で世話をすればよい。そんなことにまで悲しんだり考えたりするのは、愚かなことだと。
王子は実際、楽しみの手段をたくさん用意していた。道化師がいた、歌手がいた、踊り子がいた、音楽隊がいた、美女がいた、ワインがあった。これらすべてと安全が壁の内にあった。ないものは「赤き死」だけであった。
彼らが隔離された平和な隠遁生活を始めて五、六ヶ月がたった頃、いまだ壁外では疫病が猛威を振るっていた頃、プロスペロー王子は、豪華な仮面舞踏会を開き、千人の友人たちをもてなした。
仮面舞踏会は非常に華やかなものだったが、その前に舞踏会が開かれた会場について述べよう。七つの部屋が一つ続きになった王たちの空間だ。多くの宮殿では、このような一続きの間は、全体では長細い形状をしており、部屋の仕切りには折り畳み式のついたてが左右の壁の裏側に収納されるため、全体の眺めを妨げることはほとんどない。
ところが、この奥の院は王子が奇抜なものを好むことから想像できるように、一般的な宮殿とは大きく異なる形をしていた。
部屋と部屋は不規則に配置されていたので、ほとんど奥まで見通すことができなかったのだ。二、三十ヤード(約二、三十メートル)ごとに急に曲がり、そのたびに斬新な視覚的な効果が発揮された。部屋の左右の壁の中央には、背が高くて狭いゴシック様式の窓があり、その窓からは、この七つなぎの大部屋に隣接した、壁に囲まれた回廊を見ることができた。
これらの窓はステンドグラスでできており、各部屋の装飾に合わせた色を使っていた。
例えば、東端の部屋の装飾は青で飾られていて、そこの窓ガラスは鮮やかな青だった。第二の部屋の装飾品やタペストリーは紫色を基調としてあり、窓は紫色だった。第三の部屋は全体的に緑色で、窓も同様だった。第四の部屋はオレンジ色、第五の部屋は白、第六の部屋はスミレ色の家具と照明で照らされていた。
七番目の部屋は、黒のベルベットのタペストリーに包まれていた。タペストリーは天井から壁一面に垂れ下がり、同じ素材と色調のカーペットの上に折り重なっていた。しかし、この部屋だけは、窓の色が装飾と一致していなかった。ここの窓ガラスは緋色、つまり深い血の色をしていたのだ。
七つの部屋のうち、どの部屋にもランプや燭台はなく、きらびやかな金色の装飾品があちこちに置かれたり、天井から垂れ下げられたりして、個々に反射する光を放っていた。部屋には、ランプやロウソクから発せられる、いかなる種類の光源も存在しなかった。しかし、それらの部屋に付随する回廊には、それぞれ窓の反対側に、火鉢を乗せた重い三脚が置かれていて、その火鉢が色付きのステンドグラス越しに強い光を放ち、部屋の中を色とりどりにまぶしく照らしていた。
このようにして、多くの派手で幻想的な景観が生み出された。ところが、西端の黒い部屋では、血に染まったような緋色のステンドグラスを通して、真っ黒な吊るし物を照らしだす火炎の光の効果は、極端に恐ろしいもので、部屋の中に入った人の表情があまりにもおびえたものになったので、そこに足を踏み入れる勇気のある人はほとんどいなかった。
この部屋の西の壁には、黒檀の巨大な時計が置かれていた。その振り子は、鈍く重い単調な音を立てて、行ったり来たりした。分針が文字盤を一周して、正時を刻む時、時計の凍てついた「肺」から、はっきりした金属音と音楽的な深い響きが大音量で鳴り響くのだった。
そのため、一時間ごとに、オーケストラの音楽家たちは演奏の一時休止を余儀なくされ、時計が鳴っている間、さっきまで陽気に騒いでいた人たちも顔色を悪くし、年老いた人や静かにしていた人たちは困惑したように眉の上に手を置いた。
しかし、時計の反響が完全に止まったとき、軽やかな笑い声がすぐに舞踏会を覆った。音楽家たちはお互いを見て、まるで自分たちの緊張と愚かさに苦笑するかのように、次の時計の鐘が鳴っても同じような感情を起こさないように、お互いにささやくように誓った。ところが、六十分が経過した後(三千六百秒が飛ぶように)、またも時計の音が鳴り響いて、さっきと同じような不穏さと震えと沈黙を宴に起こしたのだった。
しかし、このようなことがあったにしても、宴はおおむね陽気で壮大な喜びにあふれていた。王子の趣味は独特であった。
彼は色彩とその効果について才能のある目を持っていた。彼は単なる様式美を無視した。彼の考えは燃えるように大胆で、その発想は野蛮な輝きを放っていた。彼を狂人だと思った者もいるが、彼を慕う友人たちは、狂ってはないと考えた。彼が狂っていないかどうかを確かめるためには、彼の話を実際に聞いて、見て、触れてみなければならない。
王子は今夜のお祭り騒ぎのために七つの部屋の装飾の大部分を 彼自身が指示して用意したのだが、仮面舞踏家たちのマスクには特にこだわった。彼自身の好みである、グロテスクな仮面では確かにあったが、眩しさ、輝き、派手さ、幻想性、つまり演劇が古典的なものからロマン的なゴシック様式になってから見られる新しい要素がたくさん含まれていた。
アラビア風のつる草の模様で飾られた妙な手足をしたもの、狂ったような狂喜乱舞、美しいものもあれば、卑猥なものもあり、奇妙なものもあれば、恐ろしいものもあり、嫌悪感を覚えるようなものも少なからずあった。七つの部屋のあちこちで、たくさんの夢幻があった。その夢は、部屋の中に、そして部屋の周りを浸食し、部屋の色相をまとい、オーケストラは、仮面をかぶった彼らの足音の響きのように強く激しく演奏した。
そしてまた、ベルベットの広間に立つ黒檀の時計が時を叩いた。その一瞬、すべてが静止し、時計の音だけが静かな会場に反響する。夢は立ったまま固く凍りついた。やがて、時計の反響は消えた。宴の参加者たちは短い時間しか沈黙に我慢せず、すぐに軽くて皮肉のまじった笑い声を、時計の音の跡を覆うように浮かびあがらせた。
再び音楽がうねり、夢幻は生きかえり、三脚の火鉢からの光が差し込む窓の色々は、これまで以上に陽気にゆらゆらと動いていった。ただ、相変わらず七つの部屋で最も西に位置する黒い部屋には、そこに踏み入れようとする勇気のある仮面の踊り手は誰一人としていないのだった。なぜなら夜はさらに深く暗くなっていたからである。
しかし、この他の部屋は人々が密集を続けており、そこでは生命の鼓動が熱狂的に淫靡なまでに高まっていた。宴は渦を巻いて進行し、やがて真夜中の時計の音が鳴り始めた。そして、さきほどと同じように、また音楽が止まり、ワルツのステップは静かになり、すべての人とものが不安定な停止状態になった。時計の鐘は十二回の大音響を鳴らすことになるはずである。一日で一番多い回数は、宴を楽しんでいた人々の心にもより長い沈黙と思慮を呼びこんだ。
最後の音の、最後の反響が完全に静寂の中に沈む直前、それまで誰の注意も惹かなかった仮面を被った人物の存在に気づく人がいた。群衆の中で気づく人数はぽつぽつと増えていった。そして、この新しい不気味な存在の噂がささやくように会場に広がり、やがて、全体からざわめきとつぶやきがあがり、宴の空気は、不信感と驚き、次には恐怖と戦慄、吐き気を催す嫌悪感が満ち溢れていった。
これまで述べたように、幻想的な雰囲気を楽しんでいた宴の参加者に、普通の仮装程度ではこれほどの衝撃は与えられなかっただろう。実際、この夜の仮装はほぼ無礼講であったのだが、問題の人物は、彼らキリスト教徒の禁忌の仮装である救世主の誕生を恐れて幼児を虐殺したユダヤ王ヘロデを出し抜くほどで、主催者の王子が考えていた無礼講の枠と意味とも超えていた。疫病から逃れて大騒ぎを楽しむ無謀な者たちにも、感情的に超えてはならない一線があった。「生」と「死」はどちらも同じくらいにウィットに富んだ言葉だが、冗談では済まされないこともある。宴の参加者は、この見知らぬ人の衣装と身なりが、冗談にも礼儀にも通じていないことに深く衝撃を受けた。
この男は背が高くて痩せていて、頭から足元まで墓場から来たような格好で覆われていた。素顔を隠している仮面は、硬直した死体の顔にそっくり似せて作られていた。かなり近くで見ても、作り物と見抜くのは困難なくらいであった。死体の仮装というだけならば、多くの人の顰蹙をかっても、まだ我慢することができたかもしれない。
しかし、仮面をつけた無言の男は、例の「赤死病」に侵された姿をしていたのだ。彼の外套は血にまみれており、そのマスク全体に黒く赤ずんだ緋色の恐怖がまとわりついていた。
厳粛であるかのようにゆっくりと、この妖鬼はワルツを踊る人々の間をずるずると歩き回りだした。その異様な侵入者をプロスペロー王子の目がとらえた。王子は最初に見た瞬間、恐怖か嫌悪かのどちらかで強く体を震わせたが、次の瞬間には、彼の眉毛は怒りで真っ赤になった。
「誰の仕業だ?」
王子は近くに立っていた延臣に甲高い声で詰問した。
「やつを捕らえてマスクをはいで正体をさぐれ! 日の出とともにそいつを城壁から吊るしてしまえ」
プロスペロー王子がこの言葉を口にしたのは、黒い部屋とは一番離れた東側の青い部屋の中だった。その言葉は、七つの部屋中に大きくはっきりと響き渡った。王子は大胆で強靭な男で、手を振るとオーケストラの音楽は静かになった。
青い部屋の中には、王子が堂々と立っていて、その傍らには青白い顔をした廷臣たちがいた。王子が怒鳴っているので、延臣の一部が侵入者の方に急いで駆け寄ろうとしたが、侵入者はゆっくりと歩み、逃げるのではなく、むしろ怒鳴っている王子のほうに近づいてきた。
しかし、廷臣たちや宴の参加者はこの狂人がみなに与えた衝撃と恐怖の大きさから、男を捕まえようと踏み出せるものはいなかった。それで、誰にも妨げられることなく、男は王子の客人たちの真ん中を通ったが、男が進むたび、一つの赤い水滴が水面に落ちるように、広大な集会の部屋の中心にいた人波はさっと壁側に縮まってわかれた。
男は途切れることなく歩みを進め、王子のいる青い部屋まで来ると踵を返し、ずっと変わらない荘厳でゆっくりとした歩みで、青い部屋を通り紫の部屋へ、紫から緑へ、緑からオレンジへ、それから白へ、そしてすみれ色から、黒い部屋に戻りかけたころ、ようやく男を捕まえようとする動きがあった。
一瞬ひるんでいたプロスペロー王子だったが、怒りと自らの臆病さを恥じて、侵入者に向かって六つの部屋を駆け抜けて追いかけた。だが、宴の参加者はだれも、あまりの恐怖のために王子に続こうとはせず、壁に張り付いたままだった。王子は短剣を抜いて振りかざし、急速な勢いで、後ろを向いて黒の部屋の手前まで後退した不審者まであと三、四フィート(約一メートル)の距離まで近づいたとき、ベルベットの黒い部屋の隅にたどり着いた仮面の男が突然振り返り、追ってきた王子とまじかに対峙した。
王子は短く鋭い叫び声をあげて、短剣を黒い毛皮の絨毯の上に落とした。短剣はきらきら光り輝くように落ちた。
王子が悲鳴とともに臥して倒れこんだのを見た、宴の参加者たちは、我に返り、荒々しい勇気をなんとか呼び覚まして、すぐに黒い部屋に身を投じ、黒檀の時計の影の中に直立して動かない背の高い仮面の男を捕まえると、その死人を模したような仮面をはぎ取ろうとした。が、それは仮面などではなく、素の顔であることを知って絶句した。
とうとう今、壁の中でも赤死病の存在がはっきりしたのだ。この疫病は夜中に泥棒のように忍び込んできた。そして宴の場にいた者たちすべてを一人ずつ血まみれにさせていき、みながそれぞれ絶望的な姿勢のまま死んでいった。黒檀の時計は最後の一人の命が尽きたと同時に動きを止めた。三脚の火鉢の炎もやがて燃え尽きた。闇と腐敗と赤き死がすべてを支配していた。
終わり
原典 Edgar Allan Poe The Masque of the Red Death (1842年)
エドガー・アラン・ポーの作品はパブリックドメインです。




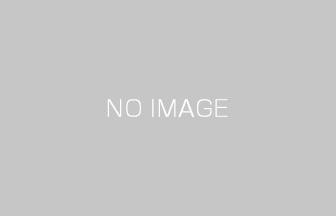
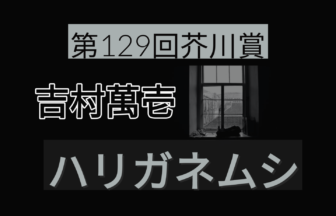



この記事へのコメントはありません。