谷崎潤一郎(たにざきじゅんいちろう)[1886―1965年]は『細雪(ささめゆき)』や『痴人の愛』などを書いた日本文学史上に輝く作家です。
この「猫と庄造と二人のをんな」は、隠れた名作と言われています。タイトルにあるように「猫」が主役です。とんでもない猫のかわいらしさ(=小憎らしさ)がたまらない表現力で描かれており、猫好きはもちろん犬好きも、「猫かわいーーー」ともだえること間違いありません。
青空文庫に掲載されていますが、旧仮名遣いや表現、最低限の注釈、行替えなどを原文をできるだけいかしながら、すらすら読めるように現代語訳しました。原文には章や見出しはありませんが、追加しました。
猫と庄造と二人のをんな(谷崎潤一郎)
コンテンツ
元女房からの手紙
福子さんどうぞゆるして下さい。この手紙、雪ちゃんの名、借りましたけど、本当は雪ちゃんではありません、そう言うたら無論あなたは私が誰だかお分かりになったでしょうね、いえいえあなたはこの手紙の封切って開けた瞬間、「さてはあの女か」ともうちゃんと気がおつきになるでしょう。
そしてきっと腹立てて、まあ失礼な、………友達の名前、無断で使って、私に手紙よこすとは何と言う厚かましい人と、お思いになるでしょう。でも福子さん察して下さいな、もしも私が封筒の裏へ自分の本名書いたら、きっとあの人が見つけて、中途で横取りしてしまうことよう分かってるのですもの。
あなたに読んでいただこう、思うたらこうするよりほかないのですもの、けれど安心して下さいませ、私けっしてあなたに恨み言うたり、泣き言聞かしたりするつもりではないのです。そりゃ、本気で言うたらこの手紙の十倍も二十倍もの長い手紙書いたかて、足りないくらいに思いますけど、今さらそんなこと言うても何にもなりわしませんものねえ。オホホヽヽヽヽヽ。
私も苦労しました。おかげで大変強くなりましたのよ、そういつもいつも泣いてばかりいませんのよ。泣きたいことや悔しいこと、タンとタンとありますけど、もうもうないことにして、できるだけ朗らかに暮らす決心しましたの。本当に、人間の運命いうものいつ誰がどうなるか、神様よりほか知る者はありませんのに、他人の幸福をうらやんだり憎んだりするなんて馬鹿げてますわねぇ。
私がなんぼ無教育な女でも、直接あなたに手紙上げたら失礼なことぐらい心得てますのよ。それかて、この事は塚本さんからたびたび言うてもらいましたけど、あの人どうしても聞き入れてくれませんので、今はあなたにお願いするより手段ないようになりましたの。
でもこう言うたら何や、たいそうむずかしいお願いするように聞えますけど、決して決してそんな面倒なことではありません。私あなたの家庭からただ一つだけ頂きたいものがあるのです。
と言うたからとて、もちろん、あなたのあの人を返せと言うのではありません。実はもっともっと下らないもの、つまらないもの、………リリーちゃんがほしいのです。
塚本さんの話では、あの人はリリーなんぞくれてやってもよいのだけれど、福子さんが離すのイヤヤ言うてなさると言うのです、ねえ福子さん、それ本当でしょうか? たった一つの私の望み、あなたが邪魔してらっしゃるのでしょうか。
福子さんどうぞ考えて下さい。私は自分の命よりも大切な人を、………いいえ、そればかりか、あの人と作っていた楽しい家庭のすべてのものを、残らずあなたにお譲りしたのです。茶碗のかけ一つも持ち出した物はなく、嫁入りの時に持って行った自分の荷物さえ満足に返してはもらいません。
でも、悲しい思い出の種になるようなものないほうがよいかも知れませんけれど、せめてリリーちゃん譲ってくだすってもよくはありません? 私はほかに何も無理なこと申しません、踏まれ蹴られ叩かれてもじっと辛抱して来たのです。その大きな犠牲に対して、たった一匹の猫をいただきたいと言うたら、厚かましいお願いでしょうか。
あなたにとっては、ほんにどうでもよいような小さい獣ですけれど、私にしたらどんなに孤独、慰められるか、………私、弱虫と思われたくありませんが、リリーちゃんでもいててくれなんだら淋しくてしょうがありませんの、………猫よりほかに私を相手にしてくれる人間、世の中に一人もいないのですもの。
あなたは私をこんなにも打ち負かしておいて、このうえ苦しめようとなさるのでしょうか。今の私の淋しさや心細さに一点の同情も寄せて下さらないほど、無慈悲なお方なのでしょうか。
いえいえ、あなたはそんなお方ではありません、私よく分かっているのですが、リリーちゃんを離さないのは、あなたでなくて、あの人ですわ、きっときっと、そうですわ。
あの人はリリーちゃんが大好きなのです。あの人いつも「お前となら別れられても、この猫とやったらよう別れん」と言うてたのです。そしてご飯の時でも夜寝る時でも、リリーちゃんのほうがずっと私より可愛がられていたのです。けど、そんなら何で正直に「自分が離しともないのだ」と言わんと、あなたのせいにするのでしょう? さぁその訳をよう考えてごらんなさりませ、………。
あの人は嫌な私を追い出して、好きなあなたと一緒になりました。私と暮らしてたあいだこそリリーちゃんが必要でしたけど、今になったらもうそんなもん邪魔になるはずではありませんか。それともあの人、今でもリリーちゃんがいなかったら不足を感じるのでしょうか。
そしたらあなたも私と同じに、猫以下と見られてるのでしょうか? まぁごめんなさい、つい心にもないこと言うてしまうて。………よもやそんな阿呆らしいことあろうとは思いませんけれど、でもあの人、自分の好きなこと隠してあなたのせいにする言うのは、やっぱりいくらか気がとがめている証拠では、………オホホヽヽヽヽヽ
もうそんなこと、どっちにしたかて私には関係ないのでしたわねぇ、けど本当にご用心なさいませ、たかが猫ぐらいと気を許していらしゃったら、その猫にさえ見かえられてしまうのですわ。私決して悪いことは申しません、私のためよりあなたのため思ってあげるのです、あのリリーちゃん、あの人のそばから早う離してしまいなさい、あの人それを承知しないならいよいよ怪しいではありませんか。………
晩酌で猫のリリーとダンス
福子はこの手紙の一字一句を胸に置いて、庄造とリリーのすることにそれとなく眼をつけているのだが、小アジの二杯酢を肴(さかな)にしてチビリチビリ傾けている庄造は、ひと口飲んではおちょこを置くと、
「リリー」
と言って、アジの一つを箸で高々と摘まみ上げる。リリーは後脚で立ち上って小判型のちゃぶ台の縁に前脚をかけ、皿の上の肴をじっとにらんでいる格好は、バーのお客がカウンターに寄りかかっているようでもあり、ノートルダムの怪獣のようでもあるのだが、いよいよ餌がつまみ上げられると、急に鼻をヒクヒクさせ、大きな、利口そうな眼を、まるで人間がびっくりした時のようにまんまるく開いて、下から見上げる。だが庄造はそう易々とは投げてやらない。
「そうれ!」
と、鼻の先まで持って行ってから、逆に自分の口の中へ入れる。そして魚にしみている酢をスッパスッパ吸い取ってやり、堅そうな骨は噛み砕いてやってから、又もう一遍つまみ上げて、遠くしたり、近くしたり、高くしたり、低くしたり、いろいろにして見せびらかす。
それにつられてリリーは前脚をちゃぶ台から離し、幽霊の手のように胸の両側へ上げて、よちよち歩き出しながら追いかける。すると獲物をリリーの頭の真上へ持って行って静止させるので、今度はそれに狙いを定めて、一生懸命に跳びつこうとし、跳びつく拍子に素早く前脚で目的物をつかもうとするが、あわやと言うところで失敗してはまた跳び上る。
こうしてようやく一匹のアジをせしめるまでに五分や十分はかかるのである。
この同じことを庄造は何度も繰り返しているのだった。一匹やっては一杯飲んで、
「リリー」
と呼びながら次の一匹を摘まみ上げる。皿の上には約二寸(約6センチ)程の長さの小アジが十二・三匹は載っていたはずだが、おそらく自分が満足に食べたのは三匹か四匹にすぎまい、あとはスッパスッパ二杯酢の汁をしゃぶるだけで、身はみんなくれてやってしまう。
「あ、あ、あ痛! 痛いやないか、こら!」
やがて庄造は素っ頓狂な声を出した。リリーがいきなり肩の上へ跳び上って、爪を立てたからなのである。
「こら! 降り! 降りんかいな!」
残暑もそろそろ衰えかけた九月の半ば過ぎだったけれど、太った人にはお定まりの、暑がりやで、汗っかきの庄造は、このあいだの水害で泥だらけになった裏の縁側の端へちゃぶ台を持ち出して、半袖のシャッの上に毛糸の腹巻をし、麻の半股引をはいた姿のまま、あぐらをかいているのだが、その丸々と膨らんだ、丘のような肩の肉の上へ跳び着いたリリーは、つるつる滑り落ちそうになるのを防ぐために、勢い爪を立てる。
と、たった一枚のちぢみのシャッを透して、爪が肉に喰い込むので、
「あ痛! 痛!」
と、悲鳴をあげながら、
「ええい、降りんかいな!」
と、肩を揺すったり一方へ傾けたりするけれども、そうするとなお落ちまいとして爪を立てるので、しまいにはシャツにポタポタ血がにじんで来る。でも庄造は、
「無茶しよる」
とボヤキながらも決して腹は立てないのである。リリーはそれをすっかりのみ込んでいるらしく、ほっぺたへ顔をすりつけてお世辞を使いながら、彼が魚をふくんだと見ると、自分の口を大胆に主人の口の端へ持って行く。
そして庄造が口をもぐもぐさせながら、舌で魚を押し出してやると、ヒョイとそいつへかみつくのだが、一度に喰いちぎってくることもあれば、ちぎったついでに主人の口の周りを嬉しそうに舐め廻すこともあり、主人と猫とが両端をくわえて引っぱりあっていることもある。
その間、庄造は「うッ」とか、「ペッ、ペッ」とか、「ま、待ちぃな!」とか合いの手を入れて、顔をしかめたり、つばを吐いたりするけれども、実はリリーと同じ程度に嬉しそうに見える。
新妻の要求
「おい、どうしたんや?―――」
だが、やっとのことでひと休みした彼は、なにげなく女房のほうへ杯をさし出すと、途端に心配そうな上眼使いをした。
どうした訳か今しがたまで機嫌のよかった女房が、酌をしようともしないで、両手を懐に入れてしまって、真正面からぐっとこちらを見つめている。
「そのお酒、もうないのんか?」
出した杯を引っ込めて、オッカナビックリ眼の中を覗き込んだが、相手はたじろぐ様子もなく、
「ちょっと話があるねん」
と、そう言ったきり、口惜しそうに黙りこくった。
「なんや? え、どんな話?―――」
「あんた、その猫品子さんに譲ったげなさい」
「何でやねん?」
藪から棒に、そんな乱暴な話があるものかと、つづけざまに眼をパチクリさせたが、女房のほうも負けず劣らず険悪な表情をしているので、いよいよ分からなくなってしまった。
「何でまた急に、………」
「何ででも譲ったげなさい、明日塚本さん呼んで、早よ渡してしまいなさい。」
「いったい、それ、どう言うこッちゃねん?」
「あんた、いややのん?」
「ま、まあ待ち! 訳も言わんとそう言うたかて無理やないか。何ぞお前、気に触ったことあるのんか?」
リリーに対する焼餅?―――と、一応思いついてみたが、それも腑(ふ)に落ちないと言うのは、もともと自分も猫が好きだったはずなのである。まだ庄造が前の女房の品子と暮らしていた時分、品子がときどき猫のことで焼餅を焼く話を聞くと、福子は彼女の非常識を笑って、嘲弄(ちょうろう)の種にしたものだった。
そのくらいだから、もちろん庄造の猫好きを承知の上で来たのであるし、それからこちら、庄造ほど極端ではないにしても、自分も彼と一緒になってリリーを可愛がっていたのである。
現にこうして、三度三度の食事には、夫婦さし向いのちゃぶ台の間へ必ずリリーが割り込むのを、今までとやかく言ったことは一度もなかった。
それどころか、いつでも今日のようなふうに、夕飯の時にはリリーとゆっくりたわむれながら晩酌を楽しむのであるが、亭主と猫とが演出するサーカスの曲芸にも似た珍風景を、福子とても面白そうに眺めているばかりか、時には自分も餌を投げてやったり跳びつかせたりするくらいで、リリーの介在することが、新婚の二人を一層仲よく結びつけ、食卓の空気を明朗化する効能はあっても、邪魔になってはいないはずだった。
とすると一体、何が原因なのであろう。
つい昨日まで、いや、ついさっき、晩酌を五・六杯重ねるまでは何のこともなかったのに、いつの間にか形勢が変わったのは、何かほんの些細なことが癪(しゃく)に触ったのでもあろうか。それとも「品子に譲ってやれ」と言うのを見ると、急に彼女が可哀そうにでもなったのか知らん。
元女房品子の言い分
そういえば、品子がここを出て行く時に、交換条件の一つとしてリリーを連れて行きたいと言う申し出があり、その後も塚本を仲に立てて、二・三度その希望を伝えて来たことは事実である。だが庄造はそんな言い草は取り上げないほうがよいと思って、そのつど断っているのであった。
塚本の説明では、連れ添う女房を追い出してよその女を引きずり込むような不実な男に、何の未練もないと言いたいところだけれども、やっぱり今も庄造のことが忘れられない、恨んでやろう、憎んでやろうと努めながら、どうしてもそんな気になれない、ついては思い出の種になるような記念の品が欲しいのだが、それにはリリーちゃんをこちらへ寄越してもらえまいか、一緒に暮していた時分には、あんまり可愛がられているのがいまいましくて、陰でいじめたりしたけれども、今になっては、あの家の中にあった物が皆なつかしく、分けてもリリーちゃんが一番なつかしい、せめて自分は、リリーちゃんを庄造の子供だと思って精一杯可愛がってやりたい、そうしたら辛い悲しい気持ちがいくらか慰められるであろう―――
「なあ、石井君、猫一匹ぐらいなんだんね、そない言われたら可哀そうやおまへんか。」
と、そう言うのだったが、
「あの女の言うこと、真に受けたらアキまへんで。」
と、いつも庄造はそう答えるにきまっていた。
あの女はとかく駆け引きが強くって、底に底があるのだから、何を言うやら眉唾物である。第一剛情で、負けず嫌いのくせに、別れた男に未練があるの、リリーが可愛くなったのと、しおらしいことを言うのが怪しい。あいつが何でリリーを可愛がるものか。
きっと自分が連れて行って、思うさまいじめて、腹いせをする気なのだろう。そうでなかったら、庄造の好きな物を一つでも取り上げて、意地悪をしようと言うのだろう。―――いや、そんな子供じみた復讐心より、もっともっと深いたくらみがあるのかも知れぬが、頭の単純な庄造には相手の腹が見通せないだけに、変に薄気味が悪くもあれば、反感も募るのだった。
それでなくてもあの女は、随分勝手な条件を沢山持ち出しているではないか。しかしもともとこちらに無理があるのだし、一日も早く出てもらいたいと思ったればこそ、大概なことは聞いてやったのに、その上リリーまで連れて行かれてたまるものか。
それで庄造は、いくら塚本がしつこく言って来ても、彼一流の婉曲な口実でやんわり逃げているのであったが、福子もそれに賛成なのは無論のことで、庄造以上に態度がはっきりしていたのである。
夫庄造が新妻福子に反論も再反論される
「訳を言いな! 何のこっちゃ、僕さっぱり見当がつかん。」
そう言うと庄造は、銚子を自分で引き寄せて、手酌で飲んだ。それから股をぴたッと叩いて、
「蚊取り線香、あれへんのんか。」
と、ウロウロその辺を見廻しながら、半分ひとりごとのように言った。あたりが薄暗くなったので、つい鼻の先の板塀のすそから、蚊がワンワンいって縁側のほうへ群がって来る。少し食い過ぎたという格好でちゃぶ台の下にうずくまっていたリリーは、自分のことが問題になり出した頃こそこそと庭へ下りて、塀の下をくぐって、どこかへ行ってしまったのが、まるで遠慮でもしたようでおかしかったが、たらふくご馳走になった後では、いつでも一遍すうっと姿を消すのであった。
福子は黙って台所へ立って行って、渦巻の線香をさがして来ると、それに火をつけて、ちゃぶ台の下へ入れてやった。そして、
「あんた、あのアジ、みんな猫に食べさせなはったやろ? 自分が食べたのん二つか三つよりあれしまへんやろ?」
と、今度は調子をやわらげて言い出した。
「そんなこと僕、覚えてぇへん。」
「わてちゃんと数えててん。そのお皿の上に最初十三匹あってんけど、リリーが十匹食べてしもて、あんたが食べたのん三匹やないか。」
「それが悪かったのんかいな。」
「何で悪い言うこと、分かってなはんのんか。なあ、よう考えてごらん。わて猫みたいなもん相手にして焼餅焼くのんと違いまっせ。けど、アジの二杯酢、わては嫌いや言うのんに、僕好きやよってにこしらえてほしい言いなはったやろ。そない言うといて、自分ちょっとも食べんとおいといてからに、猫にばっかりやってしもて、………」
彼女の言うのは、こうなのである。―――
阪神電車の沿線にある町々、西宮、芦屋、魚崎、住吉あたりでは、地元の浜で獲れるアジやイワシを、「アジの取れ取れ」「イワシの取れ取れ」と呼びながら大概毎日売りに来る。
「取れ取れ」とは「取りたて」と言う意味で、値段は一杯十銭から十五銭ぐらい、それで三・四人の家族のおかずになるところから、よく売れると見えて一日に何人も来ることがある。が、アジもイワシも夏の間は長さ一寸(3センチ)ぐらいのもので、秋口になるほどおいおい寸が伸びるのであるが、小さいうちは塩焼きにもフライにも都合が悪いので、素焼きにして二杯酢に漬け、ショウガを刻んだのをかけて、骨ごと食べるよりしかたがない。
ところが福子は、その二杯酢が嫌いだと言ってこの間から反対していた。彼女はもっと温かい脂っこいものが好きなので、こんな冷めたいモソモソしたものを食べさせられては悲しくなると、彼女らしい贅沢を言うと、庄造は又、お前はお前で好きなものをこしらえたらよい、僕は小アジが食べたいから自分で料理すると言って、「取れ取れ」が通ると勝手に呼び込んで買うのである。
福子は庄造と従兄弟同士で、嫁に来た事情が事情だから、姑には気がねがいらなかったし、来た明くる日から我が儘一杯に振る舞っていたけれど、まさか亭主が包丁を持つのを見ている訳に行かないから、結局自分がその二杯酢をこしらえて、いやいやながら一緒にたべることになってしまう。
おまけにそれが、もうここのところ五・六日も続いているのであるが、二・三日前にふと気が付いたことというのは、女房の不平を犯してまでも食膳にのせるほどのものを、庄造は自分で食べることか、リリーにばかり与えている。
それでだんだん考えて見たら、なるほどあのアジは姿が小さくて、骨が柔らかで、身をむしってやる面倒がなくて、値段のわりに数がある、それに冷めたい料理であるから、毎晩あんな風にして猫に食わせるには最も適している訳で、つまり庄造が好きだと言うのは、猫が好きだと言うことなのである。
ここの家では、亭主が女房の好き嫌いを無視して、猫を中心に晩のおかずを決めていたのだ。そして亭主のためと思って辛抱していた女房は、その実、猫のために料理をこしらえ、猫のおつきあいをさせられていたのだ。
「そんなことあれへん、僕、いつかて自分が食べよう思って頼むねんけど、リリーの奴があないにしつこう欲しがるさかいに、ついウカッとして、後から後から投げてまうねんが。」
「嘘言いなさい、あんたはじめからリリーに食べさそう思って、好きでもないもん好きや言うてるねんやろ。あんた、わてより猫が大事やねんなぁ。」
「ま、ようそんなこと。………」
ぎょうさんに、吐き出すようにそう言ったけれど、今の一言ですっかりしおれた形だった。
「そんなら、わてのほうが大事やのん?」
「きまってるやないか! 阿呆らしなって来るわ、ほんまに!」
「口でばっかりそない言わんと、証拠見せてェな。そやないと、あんたみたいなもん信用せェへん。」
「もう明日からアジ買うのんやめにしよう。な、そしたら文句ないねんやろ。」
「それより何より、リリーやってしまいなはれ。あの猫いんようになったら一番ええねん。」
まさか本気で言うのではないだろうけれど、タカをくくりすぎて意固地になられては厄介なので、ぜひなく庄造は膝頭をそろえ、キチンとかしこまって座り直すと、前屈みに、その膝の上へ両手をつきながら、
「そうかてお前、いじめられること分かっててあんな所へやれるかいな。そんな無慈悲なこと言うもんやないで。」
と、哀れっぽく持ちかけて、嘆願するような声を出した。
「なあ、頼むさかいに、そない言わんと、………」
「ほれごらん、やっぱり猫のほうが大事なんやないかいな。リリーどないぞしてくれへなんだら、わて、いなしてもらいまっさ。」
「無茶言いな!」
「わて、畜生と一緒にされるのん、嫌ですよってにな。」
あんまりムキになったせいか、急に涙が込み上げて来たのが、自分にも不意討ちだったらしく、福子は慌てて亭主のほうへ背中を向けた。
新妻福子の葛藤
雪子の名を使った品子のあの手紙が届いた朝、最初に彼女が感じたのは、こんないたずらをして私達の間へ水を挿そうとするなんて、何と言う嫌な人だろう、誰がその手に乗ってやるもんか、と言うことだった。
品子の腹は、こう言う風に書いてやったら、結局福子はリリーのいることが心配になって、こちらへ寄越すかも知れない、そうなったら、それ見たことか、人を笑ったお前さんも猫に焼餅を焼くじゃないか、やっぱりお前さんだってそう御亭主に大事にされてもいないのだねえと、手を叩いてあざけってやろう、そこまで巧く行かないとしても、この手紙をキッカケに家庭に風波が起こるとしたら、それだけでも面白いと、そう思っているに違いないので、その鼻を明かしてやるのには、いよいよ夫婦が仲よく暮らすようにして、こんな手紙などてんで問題にならなかったと言う所を見せてやり、二人が同じようにリリーを可愛がって、とても手放す気がないことをもっとハッキリ知らしてやる、―――もうそれに越したことはないのであった。
だが、あいにくなことにこの手紙の来た時期が悪かった。と言うのは、ちょうどこの二・三日小アジの二杯酢の一件が福子の胸につかえていて、いっぺん亭主を取っちめてやろうと考えていた矢先だったのである。
一体、彼女は庄造が思っているほど猫好きではないのだが、庄造の気持ちを迎えるためと、品子への面当てと、両方の必要から自然猫好きになってしまい、自分もそう思えば人にも思わせていたのであって、それは彼女がまだこの家へ乗り込まない時分、陰で姑(しゅうとめ)のおりんなどとグルになってもっぱら品子の追い出し策にかかっている間のことだった。
そんな次第で、ここへ来てからもリリーを可愛がってやって、せいぜい猫好きで通していたのだが、だんだん彼女はその一匹の小さい獣の存在を、呪わしく思うようになった。
何でもこの猫は西洋種だと言うことだったが、以前、ここへお客で遊びに来て膝の上などへ乗せてやると、手触りの具合が柔らかで、毛なみと言い、顔だちと言い、姿と言い、ちょっとこの辺には見当らない綺麗な雌猫であったから、その時は本当に愛らしいと思い、こんなものを邪魔にするとは品子さんと言う人も変っている、やっぱり亭主に嫌われると、猫にまでひがみを持つのかしらんと、面当てでなくそう感じたものだったけれど、今度自分が後釜へ直ってみると、自分は品子と同じ扱いを受ける訳でもなく、大切にされていることは分かっていながら、どうも品子を笑えない気持ちになって来るのが不思議であった。
それと言うのは、庄造の猫好きが普通の猫好きのたぐいではなくて、度を越えているせいなのである。実際、可愛がるのもいいけれども、一匹の魚を(しかも女房の見ている前で!)口移しにして、引っ張り合ったりするなどは、あまり遠慮がなさすぎる。
それから晩の御飯の時に割り込んで来られることも、正直のところは愉快でなかった。夜は姑が気を利かして、自分だけ先に食事を済まして二階へ上ってくれるのだから、福子にしてみればゆっくり水入らずを楽しみたいのに、そこへ猫の奴がはいって来て亭主を横取りしてしまう。
よいあんばいに今夜は姿が見えないなと思うと、ちゃぶ台の脚を開く音、皿小鉢のカチャンという音を聞いたらすぐどこかから帰って来る。
たまに帰らないことがあると、怪しからないのは庄造で、「リリー」「リリー」と大きな声で呼ぶ。帰って来るまでは何度でも、二階へ上ったり、裏口へ廻ったり、往来へ出たりして呼び立てる。今に帰るだろうから一杯飲んでいらっしゃいと、彼女がお銚子を取り上げても、モジモジしていて落ち着いてくれない。
そう言う場合、彼の頭はリリーのことで一杯になっていて、女房がどう思うかなどと、ちょっとも考えてみないらしい。
おふとんに入るお利口リリー
それにもう一つ愉快でないのは、寝る時にも割り込んで来ることである。庄造は今まで猫を三匹飼ったが、蚊帳をくぐることを知っているのはリリーだけだ、全くリリーは利口だと言う。
なるほど、見ていると、ぴったり頭を畳へ擦り付けて、するすると裾をくぐり抜けてはいる。そして大概は庄造の布団のそばで眠るけれども、寒くなれば布団の上へ乗るようになり、しまいには枕のほうから、蚊帳をくぐるのと同じ要領で夜具の隙間へもぐり込んで来ると言う。そんな風だから、この猫にだけは夫婦の秘密を見られてしまっているのである。
それでも彼女は、今さら猫好きの看板を外して嫌いになり出すキッカケがないのと、「相手はたかが猫だから」と言ううぬぼれに引き擦られて、腹の虫を押さえて来たのであった。
あの人はリリーを玩具にしているだけなので、本当は私が好きなのである、あの人にとって天にも地にもかけがえのないのは私なのだから、変な具合に気を廻したら、自分で自分を安っぽくする道理である。
もっと心を大きく持って、何の罪もない動物を憎むことなんか止めにしようと、そう言う風に気を向けかえて、亭主の趣味に歩調を合わせていたのだが、もともとこらえ性のない彼女にそんな我慢が長つづきするはずがなく、少しずつ不愉快さが増してきて顔に出かかっていたところへ、降って湧いたのが今度の二杯酢の一件だった。
亭主が猫を喜ばすために、女房の嫌いなものを食膳にのせる、しかも自分が好きなふりをして、女房の手前をつくろってまでも!―――これは明らかに、猫と女房とを天秤にかけると猫のほうが重い、と言うことになる。彼女は見ないようにしていた事実をまざまざと鼻先へ突き付けられて、もはやうぬぼれの有する余地がなくなってしまった。
ありていに言うと、そこへ品子の手紙が舞い込んで来たことは、彼女の焼餅を一層煽ったようでもあるが、一面には又、それを爆発の一歩手前で抑制すると言う働きをした。
品子さえおとなしくしていたら、リリーの介在をもう一日も黙視出来なくなった彼女は、早速亭主に談判して品子のほうへ引き渡させるつもりでいたのに、あんないたずらをされてみると、素直に注文を聴いてやるのが忌まいましい。
つまり亭主への反感と、品子への反感と、どっちの感情で動いたらよいか板挟みになってしまったのである。手紙の来たことを亭主に打ち明けて相談すれば、事実はそうでないにもかかわらず品子にケシカケられたような形になるのが心外であるから、それは内緒にしておいて、どっちが余計憎らしいかと考えると、品子のやり方も腹が立つけれども、亭主の仕打ちも堪忍がならない。
ことにこのほうは毎日眼の前で見ているのだから、どうにもムシャクシャする訳だし、それに、本当のことを言うと、「用心しないとあなたも猫に見換えられる」と書いてあったのが、案外グンと胸にこたえた。
まさかそんな馬鹿げたことがとは思うけれども、リリーを家庭から追い払ってしまいさえすれば、イヤな心配をしないでも済む。ただそうすると品子に溜飲を下げさせることになるのが、いかにも残念でたまらないので、その方の意地が昂じて来ると、猫のことぐらい辛抱しても誰があの女の計略なんぞにと、言う風になる。
―――で、今日の夕方ちゃぶ台の前にすわるまでは、彼女はそう言うグルグル廻りの状態に置かれてじれていたのだが、皿の上の鰺が減って行くのを数へながらいつものいちゃつきを眺めていると、ついカアッとして亭主のほうへ鬱憤を破裂させてしまったのである。
追い出されるリリー
しかし最初は嫌がらせにそう言ったまでで、本気でリリーを追い出すつもりはなかったらしいのであるが、へんに問題をコジレさせてのっぴきならないようにしたのは、庄造の態度が大いに原因しているのである。
庄造としては、福子が腹を立てたのは至極もっともなのであるから、イザコザなしに、あっさり彼女の希望を入れて納得してしまえば一番よかった。そうして意地を通してさえやったら、かえって後は機嫌が直って、それには及ばぬと言うことになったかも知れないのに、道理のないところへ道理をつけて、逃げを打った。
これは庄造の悪い癖なので、イヤならイヤときっぱり言ってしまうならいいのだが、なるたけ相手を怒らせないように、追い詰められるまではひょうたんなまずに受け流していて、土壇場へ来るとヒョイと寝返る。
もう少しで承知しそうな口ぶりを見せて、その実、決して「うん」と言わない。気が弱そうで、案外ネチネチしたずるい人だと言う印象を与える。福子は亭主が、ほかのことなら彼女のわがままを通すくせに、この問題に関する限り、「たかが猫なんぞ」と何でもなさそうに言いながら、中々同意しないのを見ると、リリーに対する愛着が想像以上に深いものとしか思えないので、いよいよ捨てて置けない気がした。
「ちょっと、あんた!………」
その晩彼女は、蚊帳の中にはいってからまた始めた。
「ちょっと、こちら向きなさい。」
「ああ、僕眠たい、もう寝さして。………」
「あかん、さっきの話きめてしまはなんだら、寝させへん。」
「今夜に限ったことあるかいな、明日にして。」
表は四枚のガラス戸にカーテンを引いてあるだけなので、軒燈(けんとう)のあかりがぼんやり店の奥へ洩れて来て、もやもやと物が見える中で、庄造は掛け布団をすっかり剥いで仰向きに寝ていたが、そう言うと女房のほうへ背中を向けた。
「あんた、そっち向いたらあかん!」
「頼むさかいに寝さしてエな、ゆうべ僕、蚊帳ん中に蚊ァはいっててちょっとも寝られへなんでん。」
「そしたら、わての言う通りしなはるか。早う寝たいなら、それきめなさい。」
「殺生やなあ、何をきめるねん。」
「そんな、寝惚けたふりしたかて、ごまかされまっかいな。リリーやんなはるのんかどっちだす? 今はっきり言うて頂戴。」
「明日、―――明日まで考えさしてもらお。」
そう言っているうちに、早くも心地よさそうな寝息を立てたが、
「ちょっと!」
と言うと、福子はムックリ起き上がって亭主のそばにすわり直すと、いやと言うほど尻の肉をつねった。
「痛い! 何をするねん!」
「あんた、いつかてリリーに引っ掻かれて、生傷絶やしたことないのんに、わてがつねったら痛いのんか。」
「痛! ええい、止めんかいな!」
「これぐらいなんだんね、猫に掻かすぐらいやったら、わてかて体じゅう引っ掻いたるわ!」
「痛、痛、痛、………」
庄造は、自分も急に起き直って防御の姿勢を取りながら、続けざまに叫んだ。二階の年寄に聞かせたくないので、大きな声は立てなかったが、つねるかと思うと今度は引っ掻く。顔、肩、胸、腕、腿、ところ嫌わず攻めて来るので、慌てて避けるたびごとにバタン! と言う地響きが家じゅうへ伝わる。
「どないや?」
「もう堪忍、………堪忍!」
「眼エ覚めなはったか?」
「覚めいでかいな! ああ痛、ヒリヒリするわ。………」
「そしたら、今のこと返事しなさい、どっちだす?」
「ああ痛、………」
それには答えないで、顔をしかめながら方々をさすっていると、
「又だっか、ごまかしたらこれだっせ!」
と、二・三本の指でモロに頬っぺたをがりッといかれたのが、飛び上がるほど痛かったらしく、思わず、
「いたア―――」
と泣き声を出したが、途端にリリーまでがびっくりして、蚊帳の外へ逃げ出して行った。
「僕、何でこんな目に遭わんならん。」
「ふん、リリーのためや思うたら、本望だっしゃろが。」
「そんな阿呆らしいこと、まだ言うてるのんか。」
「あんたがはっきりせんうちは、何ぼでも言いまっせ。―――さあ、わてをいなすかリリーやんなはるか、どっちだす?」
「誰がお前をいなす言うた?」
「そんならリリーやんなはるのんか?」
「そないどっちかにきめんならんこと………」
「あかん、きめて欲しいねん。」
そう言うと福子は、胸ぐらを取って小突き始めた。
「さあどっちや、返事しなさい、早う! 早う!」
「何とまあ手荒な、………」
「今夜はどないなことしたかて堪忍せエしまへんで。さあ、早う! 早う!」
「ええ、もう、ショウがない、リリーやってしもたるわ。」
「ほんまだっかいな。」
「ほんまや。」
庄造は眼をつぶって、観念のほぞを固めたと言う顔つきをした。
「―――そのかわり、あと一週間待ってくれへんか。なあ、こないに言うたらまた怒られるか知れへんけど、なんぼ畜生にしたかて、ここの家に十年もいてたもん、今日言うて今日追い出す訳に行くかいな。そやさかいに、心残りのないようにせめてもう一週間置いてやって、たんと好きなもん食べさして、出来るだけのことしてやりたいねん。なあ、どないや? お前かてその間ぐらい機嫌直して可愛がってやりいな。猫は執念深いよってにな。」
いかにも駆け引きのない真情らしく、そうしんみりと訴えられてみると、それには反対が出来なかった。
「そしたら一週間だっせ。」
「分かってる。」
「手エ出しなさい。」
「何や?」
と言っている隙に、素早く指切りをさせられてしまった。
猫をあげるのを回避しようとする庄造
「お母さん」
それから二・三日過ぎた夕方、福子が銭湯へ出かけた留守に、店番をしていた庄造は奥の間へ声をかけながらはいって来ると、自分だけの小さなお膳で食事している母親のそばへ、モジモジしながら中腰にかがんだ。
「お母さん、ちょっと頼みがありまんねん。―――」
毎朝別に炊いている土鍋の御飯の、お粥のように柔らかいのがすっかり冷えてしまったのを茶碗に盛って、塩昆布を載せて食べている母親は、お膳の上へ背を丸々と覆いかぶさるようにしていた。
「あのなあ、福子が急にリリー嫌いや言い出してなあ、品子んとこへやってしまえ言いまんね。………」
「このあいだ、えらい騒ぎしてたやないか。」
「お母さん知ってなはったんか。」
「夜中にあんな音さすよって、わてびっくりして、地震か思うたわ。あれ、そのことでかいな?」
「そうだんが。これ見て御覧、―――」
と、庄造は両腕を突き出して、シャツの袖をまくり上げた。
「これ、そこらじゅうミミズ腫れやあざだらけだ。顔にかてこれ、まだ痕残ってるやろ。」
「何でそんなことしられたんや?」
「焼餅だんが。―――阿呆らしい、猫可愛がり過ぎる言うて焼餅やくもん、どこの国にあるか知らん、気違い沙汰や。」
「品子かてようなんのかんの言うてたやないか。お前みたいに可愛がったら、誰にしたかて焼餅ぐらい起こすわいな。」
「ふうん、―――」
幼い時から母親に甘える癖がついているのが、この歳になってもまだ抜け切れない庄造は、駄々っ子のように鼻の孔を膨らがして、さも面白くなさそうに言った。
「―――お母さん福子のこと言うたら、味方ばっかりするねんなあ。」
「けどお前、猫であろうと人間であろうと、ほかのもん可愛がってて、来たばかりの嫁のこと思ってやらなんだら、気イ悪うするのん当り前やで。」
「そら可笑しい。僕、いつかて福子のこと思ってまんが。一番大事にしてまんが。」
「そうに違いないのんやったら、ちょっとぐらいの無理聴いてやりいな。わてあの娘からもその話聞かされてるねんが。」
「それ、いつのことだんね?」
「昨日そない言うてなあ、―――リリーいてたらよう辛抱せんさかい、五・六日うちに品子のほうへ渡すことに、もうちゃんと約束したある言うねんけど、ほんまかいな。」
「それや。―――したことはしたけど、そんな約束実行せんかて済むように、何とかそこんとこ、あんじょう言うてもらえんやろか。僕お母さんにそれ頼もう思っててん。」
「そうかて、約束通りしてくれなんだら、いなしてもらう言うてるねんで。」
「威嚇しや、そんなこと。」
「威嚇しかも知れんけど、そないまでに言うもん聴いてやったらどないや? 又うるさいで、約束違えたら。―――」
庄造は酸っぱいような顔をして、口を尖らせてうつむいてしまった。母から言わせて福子をなだめる目算でいたのが、すっかり外れてしまったのである。
「あの娘あんな気性やよってに、ほんまに逃げて行くかも知れん。それもええけど、嫁を放っといて猫可愛がるようなとこへうちの娘やっとけん! 言われたらどないする? お前よりわてが困るわいな。」
「そしたら、お母さんもリリー追い出してしまえ言やはりまんのんか。」
「そやさかいにな、とにかくここのとこはあの娘の気持ち済むように、一遍すうッと品子のほうへやってしまいイな。そないしといて、ええ折を見て、機嫌直った時分に取り戻すこと出来んもんかいな。―――」
そんな、渡してしまったものを先方が返すはずもなし、受け取る筋でもないことは分かっていながら、庄造が母親に甘えるように、母親も見え透いた気休めを言って、子供をすかすような風に庄造をあやなす癖があった。そして彼女は、いつでも結局このせがれを自分の思い通りに動かしているのだった。
黒幕だった母おりん
もう若い者はセル(毛織物)を着出した頃だのに、あわせの上に薄綿のはいったジンベエを着て、メリヤスの足袋を穿いている彼女は、小柄で、痩せていて、生活力の衰えきった老婆のように見えるけれども、頭の働きは案外確かで、言うことやすることにソッがないので、「息子よりも婆さんのほうがしっかりしている」と、近所ではそう言う評判だった。
品子が追い出されたのも、実は彼女が糸を操ったからなので、庄造にはまだ未練があったのだと言う人もある。
それやこれやで、この付近では母親を憎む者が多く、一般の同情は品子のほうに集まっていたが、彼女に言わせると、いくら姑の気に入らない嫁でも、せがれが好きなものならば、出るはずもないし出せる訳もない、やっぱりあれは庄造に飽かれたからだと言う。なるほどそれもそうだけれども、彼女と福子の父親が手を貸さなければ、庄造一人であの女房をいびり出す勇気はなかったと言うのが、間違いのない事実であった。
いったい母親と品子とは、どう言うものか初めから反りが合わなかった。勝気な品子は、落ち度を拾われないように気を付けて、随分姑には勤めていたけれども、そう言う風に抜け目なく立ち廻って行かれることが、又母親の癪に触った。
うちの嫁はどこと言って悪いところはないようなものの、何だか親身に世話をしてもらう気になれない、それと言うのが、心から年寄りを労わってやろうと言う優しい情愛がないからなのだと、母親はよくそう言ったが、つまり嫁も姑も、どっちもしっかり者だったのが不和の原因になったのである。
それでも一年半ばかりの間は、表面だけは無事に治まっていたのだったが、その時分から母親のおりんは嫁が面白くないと言って、始終今津の兄の所、庄造には伯父にあたる中島の家へ泊まりに行って、二日も三日も帰って来ないようになった。
あまり逗留が長いので、品子が様子を見に行くと、お前は帰って庄造を迎えに寄越せと言う。庄造が行くと、伯父や福子までが一緒になって引き止めて、晩になっても帰してくれない。それには何か魂胆があるらしいことは、庄造もうすうす気が付いていながら、甲子園の野球だの、海水浴だの、阪神パークだのと、福子に誘はれるままに、どこへでもふらふらとくっついて行って、呑気に遊んでいるうちに、とうとう彼女と妙な仲になってしまった。
この伯父と言うのは菓子の製造販売をしていて、今津の町に小さな工場を持っていたばかりでなく、国道沿線に五・六軒の家作(賃貸用住居)を建てたりして裕福に暮らしていたのだったが、福子のことではだいぶ今までに手を焼いていた。母親が早く亡くなったせいもあるのだろうが、女学校を二年の途中で止めさせられたか、勝手に止めてしまったかしてから、さっぱり尻が落ち着かない。
家出をしたことも二度ぐらいあって、神戸の新聞にすっぱ抜かれたりしたものだから、縁付けようと思っても中々もらい手がなかったし、自分も窮屈な家庭などへは行きたくない。そんなこんなで、何とか早く身を固めさせなければと、父親が焦っている事情に眼を付けたのがおりんであった。
福子は自分の娘のようなもので、気心はよく分かっているから、アラがあることは差しつかえない、品行の悪いのは困るけれども、もうそろそろ分別が出てもいい歳だから、亭主を持ったらまさか浮気をすることもあるまい、それにそんなことは大した問題でないと言うのは、この娘にはあの国道の家作が二軒ついていて、そこから上る家賃が六十三円になる。
おりんの計算だと、父親がそれを福子の名義に直したのが二年も前のことであるから、その積立てが元金だけでも一千五百十二円ある、それだけのものは持参金として持って来る上に、月々今の六十三円がはいるとすると、それらを銀行へ預けておいたら、十年もすればひと財産出来るので、これが何よりの付け目であった。
もっとも彼女は老い先の短かい体であるから欲張ったところで仕方がないが、甲斐性のない庄造がこの先どうして凌いで行くつもりか、それを考えると安心して死んで行けないのであった。何しろ芦屋の旧国道は、阪急のほうが開けたり新国道が出来たりしてから、年々さびれつつあるので、こんなところでいつまで荒物屋渡世をしていても思わしい訳はないのだけれど、動くにはこの店を売り退かなければならないし、さて売り退いてもどこで何を始めようという成算がない。
庄造はそんなことについてひどく呑気に生まれついた男で、貧乏を苦にしないかわりには、一向商売に身を入れない。十三・四の頃、夜学へ通いながら西宮の銀行の給仕に使われ、青木のゴルフ練習場のキャディーにも雇われ、年頃になってからはコックの見習いを勤めたりしたけれど、どこも長つづきがしないで怠けているうちに父親が亡くなって、それからこちら荒物屋の亭主で納まってしまった。
ぜんたい店の商売などは母親に任しておいて、とにかく男一匹が何かしら職を求めたらよいのに、国道筋でカフェを始めたいからと伯父に出資を申し込んで、意見されたことがあったほかには、猫を可愛がることと、球をつくことと、盆栽をいじくることと、安カフェの女をからかいに行くことぐらいより、何の仕事も思い付かない。そうして今から足かけ四年前、二十六の歳に畳屋の塚本を仲人に立てて、山芦屋のある邸に奉公していた品子を嫁にもらったのだが、その時分から商売のほうがいよいよ上ったりになって、毎月のやりくりに骨が折れて来た。
親の代から芦屋に住んでいるお陰で、長年の顔があるところから、しばらくは無理が利いたけれども、坪十五銭の地代が二年近くも滞って、百二・三十円にもなっているのは、どうにも返済の見込みが立たない。で、もう庄造をアテにしないことにきめた品子は、仕立物などを頼まれたりして暮らしの補いをつけていたばかりか、せっかくお給金を溜めて一通りこしらえて来た荷物にさえ手をつけて、わずかの間に減らしてしまった。
そんな訳だから、今さらその嫁を追い出そうと言うのは無慈悲な話で、近所の同情が彼女のほうへ集まったのも当然であるが、おりんにしてみれば、背に腹は換えられなかったし、子種のないと言うことが難癖をつけるのに都合が好かった。それに福子の父親までが、そうすれば娘の身が固まるし、甥の一家を救ってもやれるし、双方のためだと考えたのが、おりんの工作に油を注ぐ結果となった。
それゆえ福子が庄造と出来てしまったのには、父親やおりんの取り持ちがあったに違いないのであるが、一体そんなことがなくとも、庄造は割りに誰にでも好かれるたちであった。別に美男子なのではないが、いくつになっても子供っぽいところがあって、気だてが優しいせいかも知れない。
キャディーの時代にはゴルフ場へ来る紳士や夫人たちに可愛がられて、盆暮れの付け届けを誰よりも余計もらったし、カフェなどでも案外もてるので、わずかなお金で長く遊んで来ることを覚えてしまい、そんなところからのらくらの癖がついたのだった。が、何にしてもおりんからいえば、自分がいろいろ細工をしてやっと我が家へ迎え入れるまでに漕ぎ付けた、持参金付きの嫁御寮(嫁を敬う言い方)であるから、尻の軽い彼女に逃げられないように、せがれと二人でせいぜい機嫌を取らなければならない訳で、猫のことなどはもちろんはじめから問題でなかった。
いや、実を言うと、おりんも内々猫には閉口していたのであった。元来リリーと言う猫は、神戸の洋食屋に住み込んでいた庄造が帰って来る時に連れて来たのだが、これがいるために家の中が汚れることおびただしい。庄造に言わせると、この猫は決して粗相をしない、用をする時は必ずフンシ(糞仕、猫用のトイレ)へはいると言う。いかにもその点は感心だけれど、戸外にいてもわざわざフンシへはいるために戻って来ると言う調子なので、フンシが非常に臭くなって、その悪臭が家中に充満するのである。
おまけに尻の端へ砂を着けたまま歩き廻るので、畳がいつもザラザラになる。雨の日などは臭いが一層強く籠もってむッとするところへ持って来て、おもてのぬかるみを歩いたままで上って来るから、猫の脚あとがここかしこに点々とする。庄造は又、この猫は戸でも襖でも障子でも、引き戸でさえあれば人間と同じに開ける、こんな賢いのは珍しいと言う。
だが畜生の浅ましさには、開けるばかりで締めることを知らないから、寒い時分には通ったあとを一々締めて廻らなければならない。それもいいけれども、そのために障子は穴だらけ、襖や板戸は爪の痕だらけになる。それから困るのは、生物、煮物、焼物の類をうっかりその辺へ置くことが出来ない、ぼんやりしているとすぐ食べられてしまうので、お膳立てをするほんの僅かな間でも、水屋か蠅帳へ一応入れて置かなければならない。
いやいや、もっとひどいことは、この猫は尻の始末はよいが、口の始末が悪くて、ときどき嘔吐するのである。それと言うのは、庄造が例の曲芸に熱中していくらでも餌を投げてやるので、つい食い過ぎるせいなのであるが、晩飯の後でちゃぶ台をよけると、その辺に一杯毛が落ちていて、食いかけの魚の頭だの尻尾だのがたくさん散らばっているのである。
品子が嫁に来るまでは、台所の世話や拭き掃除は一切おりんの役だったから、リリーのためには随分泣かされている訳なのだが、今日まで我慢していたのは一つの出来事があったからだった。
と言うのは、たしか五・六年前に、無理に庄造を説き付けて、一度この猫を尼ヶ崎の八百屋へやったことがあったが、やがてひと月もした時分に、ある日ヒョッコリ芦屋の家へ独りで帰って来たのである。犬なら不思議はないけれども、猫が前の主人を慕って五・六里の道を戻って来るとは、あまりイジラシイ話なので、それ以来庄造の可愛がりようは旧に倍したのみならず、おりんも流石に不憫を感じたのか、あるいは多少薄気味悪く思ったのか、もうそれからは何も言わないようになった。
そして品子が来てからは、福子と同じ理由から、―――と言うのは嫁をいじめるために、かえってリリーの存在が便利を与えることがあるので、やさしい言葉の一つぐらいは時々かけてやっていたのである。だから庄造は、その母親までが突然福子の味方をし出した様子を見ては、心外でたまらないのであった。
とうとう渡されるリリー
「けど、リリーやったらやったかて又戻って来まっせ。なんせ尼ヶ崎からでも戻って来る猫やさかいにな。」
「ほんになあ、今度はまるきり知らん人やあれへんよって、そこは何とも分らんけど、戻って来たら又置いてやったらええがな。ま、ともかくもやってみてみいな。―――」
「ああ、どうしよう、困ったなあ。」
庄造はしきりに溜息をついて、まだ何かしら粘ってみようとしていたが、その時おもてに足音がして、福子が風呂から帰って来た。
「塚本君、分かってまんなあ? これ、なるべくそっと持って行かんと、乱暴に振ったらあきまへんで。猫かて乗物に酔うさかいになあ。」
「そない何遍も言わんかて、分かってまんが。」
「それから、これや、」
と、新聞紙にくるんだ、小さな平べったい包みを出して、
「実はなあ、いよいよこれがお別れやさかいに、出がけに何ぞおいしいもん食べさしてやりたい思いまんねんけど、乗物に乗る前に物食べさしたら、えらい苦しみまんねん。それでなあ、この猫鶏の肉が好きやよってに、僕、自分でこれ買うて来て、水煮きにしときましたさかい、あちらへ着いたらじき食べさしてやるように言うとくなはれしまへんか。」
「よろしおます。あんじょう持って行きますよって安心しなはれ。―――そんなら、もう用事おまへんか。」
「ま、ちょっと待っとくなはれ。」
そう言うと庄造は、バスケットの蓋を開けて、もう一度しっかり抱き上げて、
「リリー」
と言いながら頬ずりをした。
「お前な、あちらへ行ったらよう言うこと聴くんやで。あちらのあの人、もう先みたいにいじめたりせんと、大事にして可愛がってくれるさかいに、ちょっとも恐いことないで。ええか、分かったなあ。―――」
抱かれることが嫌いなリリーは、あまり強く締められたので脚をバタバタやらしたが、バスケットの中へ戻されると、二・三度周囲をつっついてみただけで、とても出られないとあきらめたらしく、急に静まり返ってしまったのが、ひとしお哀れをそそるのであった。
庄造は、国道のバスの停留所まで送って行きたかったのであるが、今日から当分の間、風呂へ行く以外は一歩も外出してはならぬと、女房から堅く止められているので、バスケットを提げた塚本が出て行ったあと、気抜けがしたようにぽつねんと店にすわっていた。
福子が外出を禁じた訳は、リリーの様子を気遣うあまりついふらふらと品子の家の近所ぐらいまで行くかも知れないからであったが、事実庄造自身にも、そう言う懸念がないことはなかった。そしてこのうかつな夫婦は、猫を渡してしまってから、はじめて品子の本当の腹が分かりかけて来たのである。
なるほど、リリーを囮に己を呼び寄せようと言う気だったのか。あの家の近所をうろうろしたら、掴まえて口説き落そうとでも言うのか。―――庄造はそこへ気がついてみると、いよいよ品子の陰険さ加減が憎くなったが、そんな道具に使われるリリーの身の上に、一層可哀さが増して来た。
唯一の望みは、尼ヶ崎から逃げて帰って来たように、阪急の六甲にある品子の家から逃げて来わせぬかと言うことであった。実は水害の後の仕事で忙しい塚本が、夜受け取りに来ると言ったのを、朝にしてもらったのも、明るい時に連れて行かれたら道を覚えているであろう、そうしたら逃げて来るのも容易であろうと、そんな心つもりがあったからだが、それにつけても思い出されるのは、この前、尼ヶ崎から戻って来たあの朝のことだった。
帰ってきたリリー
何でもあれは秋の半ば時分であったが、ある日、ようよう夜が明けたばかりの頃、眠っていた庄造は「ニヤア」「ニヤア」と言う耳馴れたなき声に眼を覚ました。その時分は独身者の庄造が二階に寝、母親が階下に寝ていたが、朝が早いのでまだ雨戸が締まっているのに、つい近いところで「ニヤア」「ニヤア」と猫がないているのを、夢うつつのうちに聞いていると、どうもリリーの声のように思えて仕方がない。
ひと月も前に尼ヶ崎へやってしまったものが、まさか今頃こんな所にいるはずはないが、聞けば聞くほどよく似ている。バリバリと裏のトタン屋根を踏む音がして、すぐ窓の外に来ているので、とにかく正体を突き止めようと急いで跳ね起きて、窓の雨戸を開けてみると、つい鼻の先の屋根の上を往ったり来たりしているのが、たいそうやつれてはいるけれどもリリーに違いないのであった。庄造はわが眼を疑う如く、
「リリー」
と呼んだ。するとリリーは
「ニヤア」
と答えて、あの大きな眼を、さも嬉しげに一杯に開いて見上げながら、彼が立っている肘掛窓の真下まで寄って来たが、手を伸ばして抱き上げようとすると、体をかわしてすうッと二・三尺向こうへ逃げた。しかし決して遠くへは行かないで、
「リリー」
と呼ばれると、
「ニヤア」
と言いながら寄って来る。そこを掴まえようとすると、又するすると手の中を脱けて行ってしまう。庄造は猫のこう言う性質がたまらなく好きなのであった。わざわざ戻って来るくらいだから、余程恋しかったのであろうに、そのなつかしい家に着いて、久しぶりで主人の顔を見たのでありながら、抱こうとすれば逃げてしまう。
それは愛情に甘えるしぐさのようでもあるし、しばらく会わなかったのがキマリが悪くて、はじらんでいるようでもある。リリーはそういう風にして、呼ばれるたびに「ニヤア」と答へつつ屋根の上をうろうろした。庄造は、彼女が痩せていることは最初から気が付いていたけれど、なおよく見ると、ひと月前よりは毛の色つやが悪くなっているばかりでなく、頸の周りだの尾の周りだのが泥だらけになっていて、ところどころにススキの穂などがくっついていた。
もらわれて行った八百屋の家も猫好きだと言う話であったから、虐待されていたはずはないので、これは明らかに、一匹の猫が尼ヶ崎からここまでひとりで辿って来る道中の難儀を語るものだった。こんな時刻にここへ着いたのは、昨夜じゅう歩きつづけたのに違いないけれども、多分ひと晩ぐらいではあるまい、もう幾晩も幾晩も、恐らくは数日前に八百屋の家を逃げ出して、方々で道に迷いながら、ようようここまで来たのであろう。
彼女が人家つづきの街道を一直線に来たのでないことは、あのススキの穂を見ても分る。それにしても、猫は寒がりなものであるのに、朝夕の風はどんなに身に沁みたことであろう。おまけに今は村しぐれの多い季節でもあるから、定めし雨に打たれて草むらへもぐり込んだり、犬に追われて田んぼの中へ隠れたりして、食うや食わずの道中をつづけて来たのだ。そう思うと、早く抱き上げて撫でてやりたくて、何度も窓から手を出したが、そのうちにリリーのほうも、はじらみながらだんだん体を擦り着けて来て、主人の為すがままに任せた。
その時のリリーは、一週間ほど前から尼ヶ崎のほうで姿を見なくなっていたことが、後に問い合わせて知れたのであったが、今も庄造は、あの朝のなきごえと顔つきとを忘れることが出来ないのである。そればかりでなく、この猫についてはまだこのほかにも数々の逸話があって、あの時はあんな顔をした、あんな声を出したと言う記憶が、いろいろの場合に残っているのである。たとえば庄造は、初めてこの猫を神戸から連れて来た日のことをはっきりと思い出すのであるが、それは最後に奉公をしていた神港軒から暇をもらって芦屋へ帰った時であるから、彼がちょうど二十歳の年、つまり父親が亡くなった年の、四十九日の頃だった。
リリーのかわいらしさを描写
その前彼は、三毛猫を一度、それが死んでからは「クロ」と呼んでいた真っ黒な雄猫を、コック場で飼っていたのであるが、そこへ出入りの肉屋から、欧州種の可愛らしいのがいるからと言って、生後三ヶ月ばかりになる雌の仔猫をもらったのが、リリーだったのである。それで暇をもらう時にもクロはコック場へ置いて来てしまったが、仔猫のほうは手放すのが惜しくて、行李(こうり、旅の荷物)と一緒にある商店のリヤカーの隅へ積んでもらって、芦屋の家へ運んだのであった。
肉屋の主人の話だと、イギリス人はこう言う毛並みの猫のことをベッコウ猫(錆び猫、黒と茶の毛がまだらになった模様の猫)と言うそうであるが、茶色の全身に鮮明な黒の斑点が行きわたっていて、つやつやと光っているところは、なるほど研いたベッコウの表面に似ている。何にしても庄造は、今日までこんな毛並みの立派な、愛らしい猫を飼ったことがなかった。
ぜんたい欧州種の猫は、肩の線が日本猫のように怒っていないので、撫で肩の美人を見るような、すっきりとした、イキな感じがするのである。
顔も日本種の猫だと一般に寸が長くって、眼の下あたりに凹みがあったり、頬の骨が飛び出ていたりするけれども、リリーの顔は丈が短かく詰まっていて、ちょうどハマグリをさかさまにした形の、カッキリとした輪郭の中に、すぐれて大きな美しい金眼と、神経質にヒクヒクうごめく鼻がついていた。だが庄造がこの仔猫に惹きつけられたのは、そう言う毛なみや顔だちや体つきのためではなかった。
もしも外形だけで言うなら、庄造だってもっと美しいペルシャ猫だのシャム猫だのを知っているが、でもこのリリーは性質が実に愛らしかった。芦屋へ連れて来た当座は、まだ本当に小さくて、掌の上へ乗る程であったが、そのお転婆でやんちゃなことは、とんと七つか八つの少女、―――いたずら盛りの、小学校一・二年生ぐらいの女の児と言う感じだった。
そして彼女は今よりもずっと身軽で、食事の時に食べ物をつまんで頭の上へかざしてやると、三・四尺の高さまで跳び上ったので、すわっていてはすぐ跳びつかれてしまうから、しばしば食事の最中に立ち上らねばならなかった。彼はその時分からあの曲芸を仕込んだのであるが、箸の先に摘まんだ物を、三尺(約90センチ)、四尺、五尺(約150センチ)、と言う風に、跳びつくたびにだんだん高くしていくと、しまいには着物の膝へ跳び着いて、胸から肩へすばしっこく這い上って、ネズミが梁を渡るように、箸の先まで腕を渡って行ったりした。
ある時などは店のカーテンに跳びついて、天井のほうまでクルクルと這い上って、端から端へ渡って行って、又カーテンに掴まって降りて来る、―――そんな動作を水車のように繰り返した。
それに、そう言う幼い時から非常に表情が鮮やかで、眼や、口元や、小鼻の運動や、息づかいなどで心待ちの変化をあらわすことは、人間と少しも違わなかった。なかんずくそのぱっちりした大きな眼球は、いつも生き生きとよく動いて、甘える時、いたずらをする時、物に狙いを付ける時、どんな時でも愛くるしさを失わなかったが、一番可笑しいのは怒る時で、小さい体をしている癖に、やはり猫なみに背をまるくして毛を逆立て、尻尾をピンと跳ね上げながら、脚を蹈ん張ってぐっと睨(にら)む格好と言ったら、子供が大人の真似をしているようで、誰でもほほ笑んでしまうのであった。
母になったリリーの思い出
庄造は又、リリーが初めてお産をした時の、あの訴えるようなやさしい眼差しを、忘れることが出来ないのであった。それは芦屋へ連れて来てから半年ほど過ぎた時分であったが、ある日の朝、産気づいた彼女はしきりにニヤアニヤア言いながら彼の後を追って歩くので、サイダーの空き箱へ古い座布団を敷いたのを押入れれの奥のほうに据えて、そこへ抱いて行ってやると、しばらくの間は箱にはいっているけれども、じきに襖を開けて出て来て、又なきながら追いかける。
そのなきごえは今まで彼が聞いたことのない声だった。「ニヤア」とは言っているのだが、その「ニヤア」の中に、今までの「ニヤア」が含んでいなかった異様な意味が籠もっていた。まあ言ってみれば、「ああどうしたらいいでしょう、何だか急に体の具合が変なのです、不思議な事が起こりそうな予感がします、こんな気持ちちはまだ覚えがありません、ねえ、どうしたと言うのでしょう、心配なことはないのでしょうか?」―――と、そう言うように聞こえるのであった。でも庄造が、
「心配せんかてええねんで。もうじきお前、お母さんになるねんが。………」
と、そう言って頭を撫でてやると、前脚を膝へ乗せて来て、すがりつくような様子をして、
「ニヤア」
と言いながら、彼の言葉を一生懸命理解しようとするかのように、眼の球をキョロキョロさせた。それからもう一度押入れれの所へ抱いて行って、箱の中へ入れてやって、
「ええか、ここにじっとしてるねんで。出て来たらあかんで。ええなあ? 分かってるなあ?」
と、しんみり言って聴かせてから、ふすまをしめて立とうとすると、「待って下さい、なにとぞそこにいて下さい」とでも言うように、また
「ニヤア」
と言って悲しげにないた。だから庄造もついその声にほだされて、細目に開けて覗いてみると、行李(荷物)だの風呂敷包みだのいろいろな荷物が積んである押入れの、一番奥の突きあたりにある箱の中から首を出して、
「ニヤア」
と言ってはこちらを見ている。畜生ながらまあ何と言う情愛のある眼つきであろうと、その時庄造はそう思った。全く、不思議のようだけれども、押入れの奥の薄暗い中でギラギラ光っているその眼は、もはやあのいたずらな仔猫の眼ではなくなって、たった今の瞬間に、何ともいえない媚びと、色気と、哀愁とをたたえた、一人前の雌の眼になっていたのであった。
彼は人間の女のお産を見たことはないが、もしその女が年の若い美しい人であったら、きっとこの通りの、恨めしいような切ないような眼つきをして、夫を呼ぶに違いないと思った。彼は幾度も襖をしめて立ち去りかけては、又戻って来て覗いてみたが、そのたびごとにリリーも箱から首を出して、子供が「居ないいないばあ」をするようにこちらを見た。
猫のはずかしがりや
そうしてそれが、もう十年も前のことなのである。しかも品子が嫁に来たのがようよう四年前であるから、それまで六年の間と言うもの、庄造は芦屋の家の二階で、母親のほかにはただこの猫を相手にしつつ暮らしたのである。それにつけても猫の性質を知らない者が、猫は犬よりも薄情であるとか、不愛想であるとか、利己主義であるとか言うのを聞くと、いつも心に思うのは、自分のように長い間猫と二人きりの生活をした経験がなくて、どうして猫の可愛らしさが分かるものか、と言うことだった。
なぜかと言って、猫と言うものは皆幾分かはずかしみやのところがあるので、第三者が見ている前では、決して主人に甘えないのみか、へんによそよそしく振る舞うのである。リリーも母親が見ている時は、呼んでも知らんふりをしたり、逃げて行ったりしたけれども、さし向いになると、呼びもしないのに自分のほうから膝へ乗って来て、お世辞を使った。
彼女はよく、額を庄造の顔にあてて、頭ぐるみぐいぐいと押して来た。そうしながら、あのザラザラした舌の先で、頬だの、あごだの、鼻の頭だの、口の周りだのを、ところきらわず舐め廻した。夜は必ず庄造の傍らに寝て、朝になると起こしてくれたが、それも顔じゅうを舐めて起こすのであった。寒い時分には、掛け布団の襟をくぐって、枕のほうからもぐり込んで来るのであったが、寝勝手のよい隙間を見付け出すまでは、懐の中へはいってみたり、股ぐらのほうへ行ってみたり、背中のほうへ廻ってみたりして、ようようある場所に落ち着いても、具合が悪いと又すぐ姿勢や位置を変えた。
結局彼女は、庄造の腕へ頭を乗せ、胸のあたりへ顔をつけて、向かいあって寝るのが一番都合がよいらしかったが、もし庄造が少しでも身動きをすると、勝手が違って来ると見えて、そのつど体をもぐもぐさせたり、又別の隙間をさがしたりした。だから庄造は、彼女にはいって来られると、一方の腕を枕に貸してやったまま、なるべく体を動かさないように行儀よく寝ていなければならなかった。
そんな場合に、彼はもう一方の手で、猫の一番喜ぶ場所、あの頸の部分を撫でてやると、すぐにリリーはゴロゴロ言い出した。そして彼の指に噛みついたり、爪で引っ掻いたり、涎を垂らしたりしたが、それは彼女が興奮した時のしぐさなのであった。
そういえば一度庄造が布団の中で放屁を鳴らすと、その布団の上の裾のほうに寝ていたリリーが、びっくりして眼を覚まして、何か奇態ななき声を出す怪しい奴が隠れているとでも思ったのであろう、さも不審そうな眼をしながら、大急ぎで布団の中を探し始めたことがあった。
又ある時は、嫌がる彼女を無理に抱き上げようとしたら、手から脱け出て、体を伝わって降りて行く拍子に、非常に臭いガスを洩らしたのが、まともに庄造の顔にかかった。たしかその時は食事の後で、今御馳走を食べたばかりの、ハチ切れそうにふくらんだリリーのお腹を、偶然庄造が両手でギュッと押さえたのである。そして運悪くも、ちょうど彼女の肛門が彼の顔の真下にあったので、腸から出る息が一直線に吹き上げたのだが、その臭かったことと言ったら、いかな猫好きもその時ばかりは、
「うわッ」
と言って彼女を床へ放り出した。イタチの最後ッ屁と言うのも恐らくこんな臭さであろうが、全くそれは執拗な臭いで、一旦鼻の先へこびり着いたら、拭いても洗っても、シャボン(石鹸)でゴシゴシ擦っても、その日一日じゅう抜けないのであった。
女房より長い猫との付き合い
庄造はよく、リリーのことで品子といさかいをした時分に、「僕リリーとは屁まで嗅ぎ合うた仲や」などと、嫌味めかして言ったものだが、十年の間も一緒に暮らしていたとすれば、たとえ一匹の猫であっても、因縁の深いものがあるので、考えようでは、福子や品子より一層親しいともいえなくはない。事実品子と連れ添うていたのは、足かけ四年と言うけれども正味は二年半ほどであるし、福子も今のところでは、来てからやっとひと月にしかならないのである。
そうしてみれば長の年月を共にしていたリリーのほうが、いろいろな場合の回想と密接につながっている訳で、つまりリリーと言うものは、庄造の過去の一部なのである。だから庄造は、今さら手放すのが辛いのは当り前の人情ではないか、それを物好きだの、猫気違いだのと、何か大変非常識のように言われる理由がないと思うのであった。そして福子の迫害と、母親の説教ぐらいで、もろくも腰がくだけてしまって、あの大切な友達をむざむざ他人の手へ渡した自分の弱気とふがいなさとが、恨めしくなって来るのであった。
何で自分はもっと正直に、男らしく、道理を説いてみなかったのだろう。何で女房にも母親にも、もっともっと剛情を張り通さなかったのであろう。そうしたところで最後にはやはり負かされて、同じ結果を見たかも知れぬが、でもそれだけの反抗もせずにしまったのでは、リリーに対していかにも義理が済まないのであった。
もしもリリーが、あの尼ヶ崎へやった時代にあれきり戻って来なかったとしたら?―――あの時だったら、彼も一旦同意を与えて他家へ譲ったのであるから、きれいにあきらめもしたであろう。
だがあの朝、トタン屋根の上でないていたのをやっと掴まえて、頬ずりをしながら抱き締めた瞬間に、ああ、不憫なことをした、おのれは残酷な主人だった、もうどんなことがあっても誰にもやるものか、死ぬまでここに置いてやるのだと、心に誓ったばかりでなく、リリーとも堅い約束をした気持ちだった。
それを今度、又あんな風にして追い出してしまったかと思うと、非常に薄情な、むごいことをしたと言う感じが胸に迫って来るのであった。その上可哀そうなのは、この二・三年めっきり歳を取り出して、体のこなしや、眼の表情や、毛の色つやなどに、老衰のさまがありありと見えていたのである。
全く、それもそのはずで、庄造が彼女をリヤカーへ乗せてここへ連れて来た時は、彼自身がまだ二十歳の青年だったのに、もう来年は三十に手が届くのである。
まして猫の寿命からいえば、十年と言う歳月は、多分人間の五・六十年にあたるであろう。それを思えば、もうひと頃の元気がないのも道理であるとは言うものの、カーテンの頂辺へ登って行って綱渡りのような軽業をした仔猫の動作が、つい昨日のことのように眼に残っている庄造は、腰のあたりがゲッソリと痩せて、うつむき加減に首をチョコチョコ振りながら歩く今日この頃のリリーを見ると、諸行無常の理を手近かに示された心地がして、言うに言われず悲しくなって来るのであった。
心配する庄造
彼女がいかに衰えたかと言うことを証明する事実はいくらもあるが、たとえば跳び上り方が下手になったのもその一つの例なのである。仔猫の時分には、実際庄造の身の丈ぐらいまでは鮮やかに跳んで、あやまたずに餌をとらえた。
又必ずしも食事の時に限らないで、いつ、どんな物を見せびらかしても、すぐ跳び上った。ところが歳を取るたびに跳び上る度数が少なくなり、高さが低くなっていって、もう近頃では、空腹な時に何か食物を見せられると、それが自分の好物であるか否かをたしかめた上で、はじめて跳び上るのであるが、それでも頭上一尺(約30センチ)ぐらいの低さにしなければ駄目なのである。
もしもそれより高くすると、もう跳ぶことをあきらめて、庄造の体を登って行くか、それだけの気力もない時は、ただ食べたそうに鼻をヒクヒクさせながら、あの特有な哀れっぽい眼で彼の顔を見上げるのである。「もし、どうか私を可哀そうだと思って下さい。
実はお腹がたまらないほど減っているので、あの餌に跳びつきたいのですが、何を言うにもこの歳になって、とても昔のような真似は出来なくなりました。もし、お願いです、そんな罪なことをしないで、早くあれを投げて下さい。」―――と、主人の弱気な性質をすっかり呑み込んでいるかのように、眼に物を言わせて訴えるのだが、品子が悲しそうな眼つきをしてもそんなに胸を打たれないのに、どう言うものかリリーの眼つきには不思議な傷ましさを覚えるのであった。
仔猫の時にはあんなに快活に、愛くるしかった彼女の眼が、いつからそう言う悲しげな色を浮かべるようになったかと言うと、それがやっぱりあの初産の時からなのである。
あの、押入れの奥のサイダーの箱から首を出してすべなさそうに見ていた時、―――あの時から彼女の眼差しに哀愁の影が宿り始めて、そののち老衰が加わるほどだんだん濃くなって来たのである。
それで庄造は、ときどきリリーの眼を見つめながら、利口だと言っても小さい獣に過ぎないものが、どうしてこんな意味ありげな眼をしているのか、何か本当に悲しいことを考えているのだろうかと、思う折があった。前に飼っていた三毛だのクロだのは、もっと馬鹿だったせいかも知れぬが、こんな悲しい眼をしたことは一度もない。
そうかと言って、リリーは格別陰鬱な性質だと言うのでもない。幼い頃はいたってお転婆だったのだし、親猫になってからだって、相当に喧嘩も強かったし、活発に暴れるほうであった。
ただ庄造に甘えかかったり、退屈そうな顔をして日なたぼっこなどをしている時に、その眼が深い憂いに充ちて、涙さえ浮かめているかのように、潤いを帯びて来ることがあった。もっともそれも、その時分にはなまめかしさの感じの方が強かったのだが、年を取るに従って、ぱっちりしていた瞳も曇り、眼のふちには目やにが溜って、見るもトゲトゲしい、あらわな哀傷を示すようになったのである。
で、これは事によると、彼女の本来の眼つきではなくて、その生い立ちや環境の空気が感化を与えたのかも知れない、人間だって苦労をすると顔や性質が変わるのだから、猫でもそのくらいなことがないとはいえぬ、―――と、そう考えると、なおさら庄造はリリーにすまない気がするのである。
それと言うのは、今まで十年の間と言うもの、なるほど随分可愛がってはやったけれども、いつでもたった二人きりの、淋しい心細い生活ばかり味わせて来たのであった。何しろ彼女が連れて来られたのは、母親と庄造と、親一人子一人の時代だったから、とても神港軒のコック場のように賑やかではなかった。そこへ持って来て母親が彼女をうるさがるので、せがれと猫とは二階でしんみり暮らさなければならなかった。
そう言う風にして六年の歳月を送った後に、品子が嫁に来たのであるが、それは結局、この新しい侵入者から邪魔者扱いされることになって、一層リリーを肩身の狭い者にしてしまった。
庄造の懺悔は続く
いや、もっともっとすまないことをしたと思うのは、せめて仔猫を置いてやって、養育させればよかったのに、仔が生まれるとなるべく早くもらい手を探して分けてしまい、一匹も家へ残さない方針を取ったのであった。
そのくせ彼女は実によく生んだ。ほかの猫が二度お産をする間に、三度お産をした。相手はどこの猫か分からなかったが、生まれた仔猫たちは混血児で、ベッコウ猫(錆び猫)のおもかげを幾分か備えているものだから、割合いに希望者が多かったけれども、時にはそうっと海岸へ持って行ったり、芦屋川の堤防の松の木陰などへ捨てて来たりした。
これは母親への気がねのためであることは言うまでもないが、庄造自身も、リリーが早く老衰するのは、一つは多産のせいかも知れぬ、だから妊娠を止めることが出来ないなら、乳を飲ませることだけでも控えさせたほうがよいと、そういう頭で取りはからいもしたのであった。実際彼女は、お産のたびごとに眼に見えて老けていった。庄造は、彼女がカンガルーのように腹を膨らして、切なげな眼つきをしているのを見ると、
「阿呆やなあ、そないに何遍も腹ぼてになったら、お婆さんになるばかりやないか。」
と、いつも不憫そうな口調で言った。雄なら去勢してあげるが、雌では手術しにくいと言われて、
「そんなら、エックス光線かけとくなはれしまへんか。」
と、そう言って獣医に笑われたこともあった。だが庄造にしてみれば、それやこれやも彼女のためを思ってのことで、無慈悲な扱いをしたつもりではなかったのだが、何と言っても、身の周りから血族を奪ってしまったことは、彼女をへんにうら淋しい、影の薄いものにしたことは否まれなかった。
そう言う風に数えていくと、彼は随分リリーに「苦労」をかけたと言う気がするのである。彼のほうが彼女のお陰で慰められているわりに、リリーのほうは一向楽をしていないように思えるのである。
ことに最近の一・二年、夫婦の不和と生計の困難とで始終家の中がゴタゴタしていた間、リリーもそれに巻き込まれて、どうしたらよいか身の置きどころがないようにうろたえていたことがあった。母親が今津の福子の家から迎いを寄越して、庄造に呼び出しをかけたりすると、品子より先にリリーが彼の裾へすがって、あの悲しい眼で引き止めたりした。
それでも振り切って出て行くと、犬のように後を追いかけて、一丁(一町=約109メートル)も二丁も付いて来た。だから庄造も、品子のことよりは彼女のことが心配になって、なるべく早く帰るようにしたのであったが、二日も三日も泊まって来た時などは、気のせいかも知れぬが、その眼の色に又一段と暗い影が添わっていた。
猫の余命を感じる
もうこの猫も余命幾ばくもないのではないか、―――と、この頃になって彼はしばしばそんな予感を覚えるにつけ、そういう夢を見たことも一度や二度ではないのであった。その夢の中の庄造は、親兄弟に死に別れでもしたような悲嘆に沈み、涙で顔を濡らしているのだが、もし本当にリリーの死に遭うことがあったら、彼の嘆き方は夢の中のそれにも劣らないような気がするのである。
で、そんな具合にそれからそれへと考え始めると、彼女をおめおめ譲ってしまったことが、又もう一度口惜しく、情なく、腹立たしくなって来るのであった。そして彼女のあの眼つきが、どこかの隅から恨めしそうにこちらを見ているように思えて仕方がなかった。
今さら悔んでも追っつかないことだけれども、あんなに老衰していたものを、なぜむごたらしく追いやってしまったのだろう。なぜこの家で死なしてやらなかったのだろう。………
「あんた、何で品子さんあの猫欲しがってたのんか、その訳分かってなはるか。―――」
その日の夕方、例になくひっそりとしたちゃぶ台に向って、しょんぼり杯のふちを舐めている亭主を見ながら、福子が照れ臭そうな調子で言うと、
「さあ、何でやろ。」
と、庄造はちょっとそらとぼけた。
「リリー自分のとこへ置いといたら、きっとあんたが会いに来るやろ言うところやねん。なあ、そうだっしゃろが。」
「まさか、そんな阿呆らしいこと、………」
「きっとそうに違いないねん。わて今日やっと気ィ付いたわ。あんたその手に乗らんようにしとくなはれや。」
「分かってる、誰が乗るかいな。」
「きっとやなあ?」
「ふふ」
と庄造は鼻の先で笑って、
「念押すまでもないこッちゃないか。」
と、また杯のふちを舐めた。
元妻の品子の場合
今日は忙しおますさかいに、もう上らんと帰りますわと、玄関先にバスケットを置いて、塚本が出て行ってしまってから、品子はそれを提げたまま狭い急な段はしごを上って、自分の部屋にあてられた二階の四畳半にはいって行った。そして、出入口の襖だのガラス障子だのをすっかり締め切ってしまってから、バスケットを部屋のまん中に据えて、蓋を開けた。
奇妙な事に、リリーは窮屈な籠の中からすぐには外へ出ようとせずに、不思議そうに首だけ伸ばしてしばらく室内を見廻していた。それから漸く、ゆるゆるとした足どりで出て来て、こう言う場合に多くの猫がするように、鼻をヒクつかせながら部屋じゅうの匂いを嗅ぎ始めた。品子は二・三度、
「リリー」
と呼んでみたけれども、彼女のほうへはチラリとそっけない流し目を与えたきりで、まず出入口と押入れの敷居ぎわへ行って匂いを嗅いで見、次ぎには窓の所へ行ってガラス障子を一枚ずつ嗅いで見、針箱、座布団、物差し、縫いかけの衣類など、その辺にあるものを一々丹念に嗅いで廻った。品子はさっき、鶏肉の新聞包を預かったことを思い出して、その包みのまま通り道へ置いてみたけれども、それには興味を感じないらしく、ちょっと嗅いただけで、振り向きもしない。そして、バサリ、バサリ、………と、畳の上に無気味な足音をさせながら、ひと通り室内捜索をしてしまうと、もう一遍出入口の襖の前へ戻って来て、前脚をかけて開けようとするので、
「リリーや、お前きょうからわての猫になったんやで。もうどこへも行ったらあかんねんで。」
と、そう言ってそこに立ち塞がると、又仕方なくバサリ、バサリと歩き廻って、今度は北側の窓ぎわへ行き、恰好な所に置いてあった小裂(こぎれ)箱の上に上って、背伸びをしながらガラス障子の外を眺めた。
九月も昨日でおしまいになって、もう本当の秋らしく晴れた朝であったが、少し寒いくらいの風が立って、裏の空地にそびえている五・六本のポプラの葉が白くチラチラ顫えている向こうに、摩耶山と六甲の頂きが見える。人家がもっと建て込んでいる芦屋の二階の景色とは、大分様子が違うのだけれども、リリーはいったいどんな気持ちで見ているのだろうか。
品子は図らずも、よくこの猫と二人きりで置き去りにされたことがあったのを思い出した。庄造も、母親も、今津へ出かけたきり帰らないので、一人ぼっちでお茶漬けをかっ込んでいると、その音を聞いてリリーが寄って来る。
ああ、そうだった、御飯をやるのを忘れていたが、お腹が減っているのだろうと、さすがに可哀そうになって、残飯の上に出し雑魚を載せてやると、贅沢な食事に馴れているせいか嬉しそうな顔もしないで、ほんの申し訳ぐらいしか食べないものだから、つい腹が立って、せっかくの愛情も消し飛んでしまう。夜は夫の寝床を敷いて、帰るかどうか分らない人を待ちわびていると、その寝床の上へ遠慮会釈もなく乗って来て、のうのうと脚を伸ばす憎らしさに、寝かけたところを叩き起こして追い立ててやる。
そんな具合に、随分この猫には当り散らしたものだけれども、再びこうして一緒に暮すようになったのは、やっぱり因縁と言うのであろう。品子は自分が芦屋の家を追い出されて来て、初めてこの二階に落ち着いた時にも、あの北側の窓から山のほうを眺めながら、夫恋いしさの思いにかられたことがあるので、今のリリーがああして外を見ている心待ちちもぼんやり分るような気がして、ふと眼頭が熱くなって来るのであった。
猫の態度に困る品子
「リリーや、さ、こちらへ来て、これ食べなさい。―――」
やがて彼女は、押入れのふすまを開けて、かねて用意をしておいたものを取り出しながら言うのであった。
彼女は昨日塚本の端書を受け取ったので、いよいよここへ連れて来られる珍客を歓待するために、今朝はいつもより早起きをして、牧場から牛乳を買って来るやら、皿やお椀を揃えておくやら、―――この珍客にはフンシが必要だと気が付いて、昨夜慌てて炮烙(ほうろく、素焼きの土鍋)を買いに行ったのはいいが、砂がないのには困ってしまって、五・六丁先の普請場(工事現場)から、コンクリートに使う砂を闇にまぎれて盗んで来るやらして、そんなものまで押入れの中にこつそり忍ばせて置いたのである。
で、その牛乳と、花鰹節をふりかけた御飯のお皿と、剥げちょろけの、縁のかけたお椀を取り出すと、ビンの牛乳をお椀へ移して、部屋のまん中へ新聞紙をひろげた。それからお土産の包みを開いて、水煮きにしてある鶏の肉を、筍(タケノコ)の皮ぐるみそれらの御馳走と一緒に並べた。そして「リリーや、リリーや」とつづけさまに呼びながら、皿と罎とをカチャカチャ打ちつけてみたりしたけれども、リリーはてんで聞えないふりをして、まだ窓ガラスにしがみついているのであった。
「リリーや」
と、彼女は躍起になって呼んだ。
「お前、何でそない表ばかり見てんのん? お腹すいてエへんのんか?」
さっきの塚本の話では、乗物に酔うといけないと言う庄造の心づかいから、今朝は朝飯を与えていないのだそうであるから、余程空腹を訴えなければならないはずで、本来ならば皿小鉢の鳴る音を聞いたらたちまち飛んで来るところだのに、今はその音も耳にはいらず、ひもじいことも感じないくらい、ここを逃れたい一念に駆られているのであろうか。
彼女はかつてこの猫が尼ヶ崎から戻って来た一件を聞かされているので、当分の間は眼が放されないことであろうと、覚悟していたものの、でも食べものを食べてくれて、フンシへ小便を垂れるようになってくれたら大丈夫だと、それを頼みにしていたのだが、来るそこそこからこんな調子では、すぐにも逃げられてしまいそうに思えた。
そして動物を手なづけるには、自分のように性急にしてはいけないのだと知りながら、何とかして食べるところを見届けたさに、無理に窓際から引き離して、部屋のまん中へ抱いて来て、食べものの上へ順々に鼻を押しつけてやると、リリーは脚をバタバタやらして、爪を立てたり引っ掻いたりするので、仕方がなしに放してしまうと、また窓際へ戻って行って、小裂箱の上へ登る。
「リリーや、これ、これを見てごらん。ここにお前のいっち好きなもんあるのんに、これが分らんかいな。」
と、こちらも意固地に追いかけて行って、鶏の肉だの牛乳だのをしつこく持ち廻りながら、鼻の先へ擦り着けるようにしてやっても、今日ばかりはその好物の匂いにも釣られなかった。
これが全く見も知らぬ人に預けられたと言うのではなし、ともかくも足かけ四年の間同じ屋根の下に住み、同じ竈の御飯をたべて、時にはたった二人きりで三日も四日も留守番をさせられた仲であるのに、あんまり無愛想過ぎるではないか。
それとも私にいじめられたことを今も根に持っているのだとすれば、畜生の癖に生意気なと、つい腹も立って来るのであったが、ここでこの猫に逃げられてしまったら、せっかくの計画が水の泡になった上、芦屋のほうでそれ見たことかと手を叩いて笑うであろう、もうこの上は根較べをして、気が折れて来るのを待つよりほかに仕方がない、なあに、ああして食い物とフンシとを眼の前に当てがっておきさえすれば、いくら剛情を張ったって、しまいにはお腹が減って来るから食わずにいられないであろうし、小便だって垂れるであろう、そんなことより今日は私は忙しいのだ、ぜひ晩までにと請け合った仕事があったのに、朝から何一つ手を付けていないのだったと、ようよう彼女は思い返して、針箱の傍らにすわった。
そして男物の銘仙(めいせん、絹織物の一種)の綿入を、それからせッせと縫いにかかったが、ものの一時間もそうしているうちに、すぐまた心配になって来るので、ときどき様子に気を付けていると、やがてリリーは部屋の隅ッこのほうへ行って、壁にぴったり寄り添うてうずくまったまま、身動き一つしないようになってしまった。それは全く、畜生ながらも逃れる道のないことを悟って、観念の眼を閉じたとでも言うのであろうか。
人間だったら、大きな悲しみにとざされたあまり、あらゆる希望をなげうって、死を覚悟したと言うところでもあろうか。品子は薄気味悪くなって、生きているかどうかを確かめるために、そうっと傍らへ寄って行って、抱き起こして見、呼吸を調べて見、突き動かして見ると、何をされても抵抗もしないかわりに、まるでアワビの身のように体じゅうを引き締めて、固くなっている様が指先に感じられる。まあ、本当に、何と言う剛情な猫であろう。こんな具合で、いつになったら懐く時があるであろう。
だが事によると、わざとああいう風をして、こちらの油断を見すましているのではないか。今はああして、あきらめたようにしているけれども、重い板戸をさえ開ける猫であるから、うっかり部屋を留守にしたら、その間にいなくなってしまうのではないか。そう思うと彼女は、他人のことよりも自分自身が、ご飯を食べに行くことも厠(トイレ)へ立つことも出来ないのであった。
お昼になって、妹の初子が
「姉さん、ご飯」
と、段はしごの下から声をかけると、
「はい」
と品子は立ち上りながら、しばらく部屋の中をうろうろした。
そして結局、メリンス(羊毛)の腰ひもを三本つないで、リリーの肩から腋の下へ、十文字にたすきをかけて、強く締め過ぎないように、そうかと言ってスッポリ抜けられないように、何度も念を入れて締め直して、背中でしっかり結び玉を作った。
それからそのひものもう一方の端を持って、又ひとしきりうろうろしていたが、とうとう天井から下っている電灯のコードにくくり着けると、やっと安心して階下へ降りた。
リリーと品子の根比べ
が、食事の間も気にかかるので、そこそこにして上って来てみると、縛られたままやはり隅ッこのほうへ行って、前よりもなお体を縮めているではないか。
彼女はいっそ、自分がいないほうがいいのかも知れない、しばらくひとりにしておいたら、その間に食べるものは食べ、垂れるものは垂れるかも知れないと、そうも期待していたのであったが、もちろんそんな形跡もない。彼女は「チヨッ」と舌打ちをして、今も部屋のまん中に空しく置かれてあるご馳走のお皿と、砂が少しも濡れていない綺麗なフンシとを恨めしそうに睨みながら、針箱の傍らにすわる。
かと思うと、ああ、そうだった、あんまり長く縛っておいては可哀そうだと、又立ち上がって、ほどきに行って、ついでになでてみたり、抱いてみたり、駄目と知りながらも食べものをすすめてみたり、フンシの位置を換えてみたり、それを幾度か繰り返すうちに日が暮れて来て、夕方の六時頃になると、階下から初子が晩の御飯を知らせるので、又ひもを持って立ち上る。
そんな風にして、その日は一日猫のことにかまけて、請け合った仕事も出来ないままに秋の夜長が更けてしまった。
十一時が鳴ると、品子は部屋を片づけてから、もう一度リリーを縛って、座布団を二枚も敷いた上へ寝かして、御飯と便器とを身近な所へ並べてやった。
それから自分の寝床を伸ばし、あかりを消して眠りについたが、せめて朝になるまでには、牛乳でも鶏でも何でもいいから、どれか一つぐらい食べていてくれないだろうか、明日の朝眼を開いた時あのお皿が空になっていてくれたら、そうしてフンシが濡れていてくれたら、どんなに嬉しいであろうなどと思うと、眼が冴えてきて寝られないままに、リリーの寝息が聞えるか知らんと闇の中で耳を澄ますと、しーんと水を打ったようで、微かな音もしていない。
あまり静か過ぎるのが気になって、枕から首をもたげると、窓のほうは薄ぼんやりと明るいけれども、リリーがいるはずの隅ッこのほうはあいにく真っ暗で何も見えない。ふと思いついて、頭の上を手さぐりして、天井から斜っかいに引っ張られているひもを掴んで、手繰り寄せると、大丈夫手ごたえがある。
でも念のために電灯を付けて見ると、なるほどいることはいるけれども、あの、拗ねたようにちじこまって、まるくなっている姿勢が、昼間と少しも変っていないし、食べ物もフンシもそつくりそのまま並んでいるので、又がっかりして明かりを消す。そのうちにしばらくとろとろとしかけて、しばらくしてから眼を覚ますと、もういつの間にか夜が明けていて、見ればフンシの砂の上に大きな塊が落としてあり、牛乳のお皿と御飯のお皿がすっかり平らげられているので、しめたと思うとそれが夢だったりするのである。
だが、一匹の猫を手なずけるのは、こんなに骨の折れることなのだろうか。それともリリーという猫が特別に剛情なのだろうか。もっともこれがまだあどけない仔猫であったら、わけなく懐くのであろうけれども、こういう老猫になって来ると、人間と同じで、習慣や環境の違った場所へ連れて来られると言うことが、非常な打撃なのかも知れない。
そして遂には、それが原因で死ぬようなことになるのかも知れない。品子はもともと、腹に一つの目算があって好きでもない猫を引き取ったので、こんなに手数がかかるものとは知らなかったが、言わば以前は敵同士であった獣のお陰で、夜もおちおち寝られないほど苦労をさせられる因縁を思い合わせると、不思議にも腹が立たないで、猫も可哀そうなら自分も可哀そうだと言う気持ちが湧いて来るのであった。
考えてみれば、自分だって芦屋の家を出て来た当座は、ここの二階にひとりでしょんぼりしていることがこの上もなく悲しくって、妹夫婦が見ていない時は、毎日毎晩泣いてばかりいたではないか。自分だって、二日三日は何をする元気もなく、ろくろく物も食べなかったではないか。
そうしてみれば、リリーにしたって芦屋が恋いしいのは当り前だ。庄造さんにあんなに可愛がられていたのだものを、そのくらいな情がなければ恩知らずだ。ましてこんなに年を取って、住み馴れた家を追われ、嫌いな人の所へなんか連れて来られて、どんなにやるせないであろう。
もし本当にリリーを手なずけようと言うなら、その心待ちちを察してやり、何よりも安心と信頼を持たせるように仕向けなければならない。悲しい感情で胸が一杯になっている時に、無理にご馳走をすすめたら、誰だって腹が立つではないか。
だのに自分は、「食べるのが嫌なら小便をしろ」と、フンシまでも突き付けた。あまりといえば手前勝手な、心なしのやり方だった。いや、そのくらいはまだいいとして、縛ったのが一番よくなかった。相手に信頼されたかったら、まずこちらから信頼してかからなければならないのに、あれではますます恐怖心を起こさせる。いくら猫でも、縛られていては食欲も出ないであろうし、小便も詰まってしまうであろう。
明くる日になると、品子は縛ることを止めにして、逃げられたら逃げられたで仕方がないと、度胸をきめた。そしてときどき、五分か十分ぐらいの間、試しに独り放っておいて、部屋を留守にしてみると、まだ剛情にちじこまってはいるけれども、いい塩梅に逃げ出しそうな風も見えない。それでにわかに気を許したことが悪かったのだが、お昼の御飯に、今日はゆっくり食べようと思って、三十分ほど階下へ降りている時だった、二階で何か、ガサッという音がしたようなので、急いで上って来てみると、襖が五寸ほど開いている。多分リリーは、そこから廊下へ出て、南側の、六畳の間を通り抜けて、折悪く開け放しになっていたそこの窓から屋根へ飛び出したのであろう、もうその辺には影も形も見えなかった。
「リリーや、………」
彼女はさすがに大きな声でわめこうとして、ついその声が出ずにしまった。あんなに辛苦したかいもなく、やっぱり逃げられたかと思うと、もう追いかける気力もなく、何だかホッとして、荷が下りたような具合であった。どうせ自分は動物を馴らすのが下手なのだから、おそかれ早かれ逃げられるにきまっているものなら、早く片がついたほうがいいかも知れない。
これで却ってサバサバして、今日からは仕事も捗るであろうし、夜ものんびり寝られるであろう。それでも彼女は、裏の空地へ出て行って、雑草の中をあちらこちら掻き分けながら、
「リリーや、リリーや」
と、しばらく呼んでみたけれども、今頃こんな所にぐずぐずしているはずがないことは、分かりきっていたのであった。
帰ってきたリリー
リリーが逃げて行ってから、当日の晩も、その明くる晩も、又その明くる晩も、品子は安心して寝られるどころか、さっぱり眠れないようになってしまった。
いったい彼女は癇性(かんしょう、怒りやすい)のせいか、二十六と言う歳のわりにはめざといほうで、下女奉公をしていた時代から、どうかすると寝られない癖があったものだが、今度もこの二階に引き移ってから、多分寝所の変わったのが原因であろう、ほとんど正味三・四時間しか寝ない晩が長い間つづいていて、ようよう十日ばかり前から少し寝られるようになりかけた所だったのである。
それがあの晩から、又眠れなくなったのはどうしてか知らん? 彼女は詰めて仕事をすると、じきに肩が凝って来たり興奮したりするのであるが、この間からリリーのためにおくれていたのを取り返そうとして、あまり縫い物に熱中し過ぎたせいか知らん? それに元来が冷え性なので、まだ十月の初めだと言うのにそろそろ足が冷えて来て、布団へはいっても容易にぬくもらないのである。
彼女は夫にそらんぜられたそのそもそものキッカケを、ふと想い出して来るのであるが、それも今から考えれば、全く自分の冷え性から起こったことなのであった。ひどく寝つきのいい庄造は、布団へはいって五分もすれば眠ってしまうのに、そこへ突然氷のような足に触られて、起こされてしまうのが溜らないから、お前はそっちで寝てくれろと言う。
そんなことからつい別々に寝るようになったが、寒い時分には湯たんぽのことでよく喧嘩をした。なぜかと言って、庄造は彼女と反対に、人一倍上気せ性なのである。
分けても足が熱いと言って、冬でも少し布団の裾へ爪先を出すくらいにしないと、寝られない男なのである。だから湯たんぽで暖めてある布団へはいることを嫌って、五分と辛抱していなかった。もちろんそれが不和を醸した根本の理由ではないけれども、しかしそう言う体質の相違がよい口実に使われて、だんだん独り寝の習慣を付けられてしまったのであった。
彼女は右の首筋から肩のほうへしこりが出来て恐しく張っているようなので、ときどきそこを揉んでみたり、寝返りを打って枕の当るところを換えてみたりした。毎年夏から秋へかけて、陽気の変り目に右の下あごの虫歯が痛んで困るのであるが、昨夜あたりから少しズキズキし出したようである。
そういえば、この六甲と言う所は、これから冬になって来ると、毎年六甲おろしが吹いて、芦屋などよりずっと寒さが厳しいのであると聞いていたけれども、もうこの頃でも夜は相当に冷え込むので、同じ阪神の間でありながら、何だか遠い山国へでも来たような気がする。
彼女は体を海老のようにちじこめて、無感覚になりかけた両方の足を擦り合わせた。芦屋時代には、もう十月の末になると、夫と喧嘩しながらも湯たんぽを入れて寝たのであったが、こんな具合だと、ことしはそれまで待てないかも知れない。………
寝付かれないものとあきらめてしまって、電灯を付けて、妹から借りた先月号の「主婦之友」を、横向きに寝ながら読み出したのが、ちょうど夜中の一時であったが、それから間もなく、遠くのほうからざあッという音が近寄って来て、直きにざあッと通り過ぎて行くのが聞えた。
おや、時雨かな、と思っていると、又ざあッとやって来て、屋根の上を通る時分には、パラバラとまばらな音を落して、忍び足に消えて行く。しばらくすると、又ざあッとやって来る。それにつけても、リリーは今頃どこにいるか、芦屋へ帰っているならいいが、もしそうでもなく、道に迷っているなら、こんな晩にはさぞ雨に濡れているであろう。
実を言うと、まだ塚本には逃げられたことを知らせてやらないのであるが、あれからこちら、ずっとそのことが頭に引っかかっているのであった。
彼女としては早く知らしてやったほうが行き届いていることは分かっていたのだが、「はばかりながら、とうに戻って来ておりますから御安心下すって結構です、いろいろお手数をかけましたが、もう御入用はありますまいな」と、皮肉交りに言われそうなのが業腹で、つい延びのびにしていたのである。
しかし戻っているとしたら、こちらの通知を待つまでもなく、向こうからも挨拶がありそうなものだのに、何とも言って来ないのをみると、どこかにまごついているのであろうか。
尼ヶ崎の時は、姿が見えなくなってから一週間目に戻ったと言うのだが、今度はそんなに遠い所ではないのだし、つい三日前に通って来たばかりの道なのだから、よもや迷うことはないであろう。ただ近頃は耄碌していて、あの時分よりはカンも悪く、動作も鈍くなっているから、三日かかるところが四日かかるようなことはあるかも知れない。
そうだとしても、おそくも明日か明後日のうちには無事に戻って行くであろう。するとあの二人がどんな喜びようをするか。そしてどんなに溜飲を下げるか。きっと塚本さんまでが一緒になって、「それ見ろ、あれは亭主に捨てられるばかりか、猫にまで捨てられるような女だ」と言うであろう。いやいや、階下の妹夫婦もお腹の中ではそう思うであろうし、世間の人がみんな笑い物にするであろう。
その時、しぐれがまた屋根の上をパラパラと通って行った後から、窓のガラス障子に、何かがバタンとぶつかるような音がした。風が出たな、ああ、イヤなことだ、と、そう思っているうちに、風にしては少し重みのあるようなものが、つづいて二度ばかり、バタン、バタンと、ガラスを叩いたようであったが、かすかに、
「ニヤア」
と言う声が、どこかに聞えた。まさか今時分、そんなことが、………と、ぎくッとしながら、気のせいかも知れぬと耳を澄ますと、やはり、
「ニヤア」
とないているのである。そしてそのあとから、あのバタンと言う音が聞えて来るのである。彼女は慌てて跳ね起きて、窓のカーテンを開けてみた。と、今度はハッキリ、
「ニヤア」
と言うのがガラス戸の向こうで聞えて、バタン、………と言う音と同時に、黒い物の影がさっとかすめた。そうか、やっぱりそうだったのか、―――彼女はさすがに、その声には覚えがあった。この間ここの二階にいた時は、とうとう一度もなかなかったが、それは確かに、芦屋時代に聞き馴れた声に違いなかった。
急いで挿し込みのネジを抜いて、窓から半身を乗り出しながら、室内から射す電灯のあかりをたよりに暗い屋根の上を透かしたけれども、一瞬間、何も見えなかった。
想像するに、その窓の外に手すりの付いた張り出しがあるので、リリーは多分そこへ上って、なきながら窓を叩いていたのに違いなく、あのバタンという音とたった今見えた黒い影とは正しくそれだったと思えるのであるが、内側からガラス戸を開けた途端に、どこかへ逃げて行ったのであろうか。
「リリーや、………」
と、階下の夫婦を起こさないように気がねしながら、彼女は闇に声を投げた。瓦が濡れて光っているので、さっきのあれが時雨だったことは疑う余地がないけれども、それがまるで嘘だったように、空には星がきらきらしている。
リリーや!ニャァ!
眼の前を覆う摩耶山の、幅広な、真っ黒な肩にも、ケーブルカーのあかりは消えてしまっているが、頂上のホテルに灯のともっているのが見える。彼女は張り出しへ片膝をかけて、屋根の上へノメリ出しながら、もう一度、
「リリーや」
と、呼んだ。すると、
「ニヤア」
と言う返事をして、瓦の上をこちらへ歩いて来るらしく、燐(りん、青白い)色に光る二つの眼の玉がだんだん近寄って来るのである。
「リリーや」
「ニヤア」
「リリーや」
「ニヤア」
何度も何度も、彼女が頻繁に呼び続けると、その度毎にリリーは返事をするのであったが、こんなことは、ついぞ今までにないことだった。
自分を可愛がってくれる人と、内心嫌っている人とをよく知っていて、庄造が呼べば答えるけれども、品子が呼ぶと知らん顔をしていたものだのに、今夜は幾度でもおっくうがらずに答えるばかりでなく、次第に媚びを含んだような、何ともいえない優しい声を出すのである。
そして、あの青く光る瞳をあげて、体に波を打たせながら手すりの下まで寄って来ては、又すうっと向こうへ行くのである。おおかた猫にしてみれば、自分が無愛想にしていた人に、今日から可愛がってもらおうと思って、いくらか今までの無礼を詑びる心待ちもこめて、あんな声を出しているのであろう。
すっかり態度を改めて、庇護をあおぐ気になったことを、何とかして分かってもらおうと、一生懸命なのであろう。品子は初めてこの獣からそんな優しい返事をされたのが、子供のように嬉しくって、何度でも呼んでみるのであったが、抱こうとしてもなかなか掴まえられないので、しばらくの間、わざと窓際を離れてみると、やがてリリーは身をおどらして、ヒラリと部屋へ飛び込んで来た。
それから、全く思いがけないことには、寝床の上にすわっている品子のほうへ一直線に歩いて来て、その膝に前脚をかけた。
これはまあ一体どうしたことか、―――彼女が呆れているうちに、リリーはあの、哀愁に充ちた眼差しでじっと彼女を見上げながら、もう胸のあたりへもたれかかって来て、綿フランネルの寝間着の襟へ、額をぐいぐいと押し付けるので、こちらからも頬ずりをしてやると、あごだの、耳だの、口の周りだの、鼻の頭だのを、やたらに舐め廻すのであった。
これだったのか!猫の愛情は
そういえば、猫は二人きりになると接吻をしたり、顔をすり寄せたり、全く人間と同じような仕方で愛情を示すものだと聞いていたのは、これだったのか、いつも人の見ていない所で夫がこっそりリリーを相手に楽しんでいたのは、これをされていたのだったか。―――彼女は猫に特有な日なた臭い毛皮の匂いを嗅がされ、ザラザラと皮膚に引っかかるような、痛かゆい舌ざわりを顔じゅうに感じた。そして、突然、たまらなく可愛くなって来て、
「リリーや」
と言いながら、夢中でぎゅッと抱きすくめると、何か、毛皮のところどころに、冷めたく光るものがあるので、さては今の雨に濡れたんだなと、初めて合点がいったのであった。
それにしても、芦屋のほうへ帰らないで、こちらへ帰ったのはなぜであろう。恐らく最初は芦屋をめざして逃げ出したのが、途中で道が分らなくなって、戻って来たのではないであろうか。
わずか三里か四里のところを、三日もかかってうろうろしながら、とうとう目的地へ行き着けないで引っ返して来るとは、リリーにしてはあまり意気地がないようだけれども、ことによるとこの可哀そうな獣は、もうそれほどに老衰しているのであろう。
気だけは昔に変わらないつもりで、逃げてみたことはみたものの、視力だの、記憶力だの、嗅覚だのというものが、もはや昔の半分もの働きもしてくれないので、どっちの道を、どっちの方角から、どういう風に連れて来られたのか見当が付かず、あちらへ行っては踏み迷い、こちらへ行っては踏み迷いして、又もとの場所へ戻って来る。
昔だったら、一旦こうと思い込んだらどんなに道のない所でもガムシャラに突進したものが、今では自信がなくなって、様子の知れない所へ分け入ると怖気がついて、ひとりでに足がすくんでしまう。きっとリリーは、そんな風にして案外遠くのほうまでは行くことが出来ず、この界隈をまごまごしていたのであろう。そうだとすれば、昨日の晩も、一昨日の晩も、夜な夜なこの二階の窓の近くへ忍び寄って、入れてもらおうかどうしようかととまどいながら、中の様子をうかがっていたのかも知れない。
そして今夜も、あの屋根の上の暗い所にうずくまって長い間考えていたのであろうが、室内にあかりがともったのと、にわかに雨が降って来たのとで、急にああ言うなき声を出して障子を叩く気になったのであろう。でも本当に、よく帰って来てくれたものだ。よっぽど辛い目にあったればこそであろうけれども、やはり私をアカの他人とは思っていない証拠なのだ。
それに私も、今夜に限ってこんな時刻に電灯をつけて、雑誌を読んでいたと言うのは、虫が知らせたせいなのだ。いや、考えれば、この三日間ちょっとも眠れなかったのも、実はリリーの帰って来るのが何となく待たれたからだったのだ。そう思うと彼女は、涙が出てきて仕方がないので、
「なあ、リリーや、もうどこへも行けへんなあ。」
と、そう言いながら、もう一遍ぎゅっと抱きしめると、珍しいことにリリーはじっと大人しくして、いつまでも抱かれているのであったが、その、物も言わずにただ悲しそうな眼つきをしている年老いた猫の胸の中が、今の彼女には不思議なくらいはっきり見通せるのであった。
「お前、きっとお腹減ってるやろけど、今夜はもう遅いよってにな。―――台所探したらなんかなとあるやろ思うけど、ま、仕方ない、ここわての家と違うよってに、明日の朝まで待ちなされや。」
彼女はひと言ひと言に頬ずりをしてから、ようやくリリーを下に置いて、忘れていた窓の戸締まりをし、座布団で寝床をこしらえてやり、あの時以来まだ押入れに突っ込んであったフンシを出してやりなどすると、リリーはその間も始終あとを追って歩いて、足もとに絡みつくようにした。そして少しでも立ち止まると、すぐその傍らへ走り寄って、首を一方へ傾けながら、何度も耳の付け根のあたりを擦りつけに来るので、
「ええ、もうええがな、分かってるがな。さ、ここへ来て寝なさい寝なさい。」
と、座布団の上へ抱いて来てやって、大急ぎであかりを消して、やっと彼女は自分の寝床へはいったのであったが、それから一分とたたないうちに、たちまちすうッと枕の近くにあの日なた臭い匂いがして来て、掛け布団をもくもく持ち上げながら、ビロードのような柔らかい毛の物体がはいって来た。と、ぐいぐい頭からもぐり込んで、脚のほうへ降りて行って、裾のあたりをしばらくの間うろうろしてから、また上のほうへ上って来て、寝間着のふところへ首を入れたなり動かないようになってしまったが、やがてさも気持ちの良さそうな、非常に大きな音を立ててのどをゴロゴロ鳴らし始めた。
ゴロゴロいう猫と寝る幸せ
そういえば以前、庄造の寝床の中でこんな具合にゴロゴロ言うのを、いつも隣で聞かされながら言い知れぬ嫉妬を覚えたものだが、今夜は特別にそのゴロゴロが大きな声に聞えるのは、よっぽど上機嫌なのであろうか、それとも自分の寝床の中だと、こう言う風にひびくのであろうか。
彼女はリリーの冷たく濡れた鼻のあたまと、へんにぷよぶよした足裏の肉とを胸の上に感じると、全く初めての出来事なので、奇妙のような、嬉しいような心地がして、真っ暗な中で手さぐりしながら首のあたりをなでてやった。
するとリリーは一層大きくゴロゴロ言い出して、ときどき、突然人差指の先へ、きゅッと噛みついて歯型を付けるのであったが、まだそんなことをされた経験のない彼女にも、それが異常な興奮と喜びのあまりのしぐさであることが分かるのであった。
その明くる日から、リリーはすっかり品子と仲良しになってしまって、心から信頼している様子が見え、もう牛乳でも、花鰹節のご飯でも、何でもおいしそうに食べた。
そしてフンシの砂の中へ日に幾度か排泄物を落とすので、いつもその匂いが四畳半の部屋の中へむうッとこもるようになったが、彼女はそれを嗅いでいると、いろいろな記憶が思いがけなくよみがえって、芦屋時代のなつかしい日が戻って来たように感ずるのであった。
なぜかと言って、芦屋の家では明けても暮れてもこの匂いがしていたではないか。あの家の中の襖にも、柱にも、壁にも、天井にも、皆この匂いがしみついていて、彼女は夫や姑と一緒に四年の間これを嗅ぎながら、口惜しいことや悲しいことの数々にたえてきたのではないか。
だが、あの時分には、この鼻持ちのならない匂いを呪ってばかりいたくせに、今はその同じ匂いが何と甘い回想をそそることよ。あの時分にはこの匂いゆえにひとしお憎らしかった猫が、今はその反対に、この匂いゆえにいかにいとおしいことよ。
彼女はそののち毎晩のようにリリーを抱いて眠りながら、この柔順で可愛らしい獣を、どうして昔はあんなにも嫌ったのかと思うと、あの頃の自分と言うものが、ひどく意地の悪い、鬼のような女にさえ見えて来るのであった。
品子のたくらみ
さてこの場合、品子がこの猫の身柄について福子に嫌味な手紙を出したり、塚本を通してあんなにしつこく頼んだりした動機と言うものを、ちょっと説明しておかなければならないのであるが、正直のところ、そこにはいたずらや意地悪の興味が手伝っていたことも確かであり、また庄造が猫に釣られて訪ねて来るかも知れないという万一の望みもあったであろうが、そんな眼の前のことよりも、実はもっと遠い遠い先のこと、―――ま、早くて半年、おそくて一年か二年もすれば、多分福子と庄造の仲が無事に行くはずはないのだからと、その時を見越しているのであった。
それと言うのが、もともと塚本の仲人(なこうど)に乗せられて嫁に行ったのが不覚だったので、今さらあんな怠け者の、意気地なしの、働きのない男なんぞに、捨てられたほうが幸せだったかも知れないのだが、でも彼女としてどう考えてもいまいましく、あきらめきれない気がするのは、当人同士が飽きも飽かれもした訳ではないのに、ハタの人間が小細工をして追い出したのだと、そう言う一念があるからだった。
もっともそんなことを言うと、いや、そう思うのはお前さんのうぬぼれだ、それはなるほど、姑との折り合いも悪かったに違いないけれども、夫婦仲だってちっとも良いことはなかったではないか、お前さんは御亭主をのろまだと言って低能児扱いにするし、御亭主はお前さんを我が強いと言ってうっとうしがるし、いつも喧嘩ばかりしていたのを見ると、よくよく性が合わないのだ、もし御亭主がほんとにお前さんを好いているなら、いくらハタから押し付けたって、外に女をこしらえる訳がありますまいと、そう露骨には言わないまでも、塚本などのお腹の中は大概そうにきまっているのだが、それは庄造と言う人の性質を知らないからのことなので、彼女に言わせれば、いったいあの人はハタから強く押し付けられたら、否も応もないのである。
呑気と言うのか、ぐうたらと言うのか、其の人よりもこの人がいいと言われると、すぐふらふらとその気になってしまうのだけれども、自分から女をこしらえて古い女房を追い出したりする程、一途に思い詰める性分ではないのである。
だから品子は熱烈に惚れられた覚えはないが、嫌われたと言う気もしないので、周りの者が知恵をつけたりそそのかしたりしなかったら、よもや不縁にはならなかったろう、自分がこんな憂き目を見るのは、全くおりんだの、福子だの、福子の親父だのと言うものがお膳立てをしたからなのだと、そう思われて、少し誇張した言い方をすれば、生木を割かれたような感じが胸の奥のほうにくすぶっているので、未練がましいようだけれども、どうもこのままでは堪忍出来ないのであった。
しかし、それなら、うすうすおりんなどのしていることを感づかないでもなかった時分に、何とか手段の施しようがあっただろうに、―――いよいよ芦屋を追い出される間際にだって、もっと頑張ってみたらよかったろうに、―――じたいそう言う策略にかけては姑のおりんとよい取り組みだと言われた彼女が、案外あっさり旗を巻いて、おとなしく追ん出てしまったのはなぜであろうか、日頃の負けず嫌いにも似合わないと言うことになるが、そこにはやっぱり彼女らしい思わくがないでもなかった。
ありていに言うと、今度の事は彼女のほうに最初幾分の油断があったからそうなったので、それと言うのも、あの多情者の、不良少女あがりの福子を、なんぼなんでもせがれの嫁にしようとまではおりんも考えていないであろうし、また尻の軽い福子が、まさか辛抱する気もあるまいと、たかをくくっていたからなのだが、そこに多少の目算違いがあったとしても、どうせ長続きのする二人でないと言う見通しに、今も変わりはないのであった。
もっとも福子は年も若いし、男好きのする顔だちだし、鼻にかける程の学問はないが女学校へも一・二年行っていたのだし、それに何より持参金が付いているのだから、庄造としては据え膳の箸を取らぬはずはなく、まず当分は有卦(うけ)に入った(幸運な)気でいるだろうけれども、福子のほうがやがて庄造では喰い足らなくなって、浮気をせずにはいないであろう。
何しろあの女は男一人を守れないたちで、もうそのほうでは札付きになっているのだから、どうせ今度も始まることは分かりきっているのだが、それが眼に余るようになれば、いくら人のよい庄造だって黙っていられないであろうし、おりんにしても匙を投げるにきまっている。
ぜんたい庄造はとにかくとして、シッカリ者と言われるおりんにそのくらいなことが見えないはずはないのだけれども、今度は欲が手伝ったので、つい無理な細工をしたのかも知れない。だから品子は、ここでなまじな悪あがきをするよりは、ひとまず敵に勝たしておいて、おもむろに後図(こうと、計画)を策しても遅くはないと言う腹なので、中々あきらめてはいないのだったが、でもそんなことは、無論塚本に対してもおくびにも出しはしなかった。
うわべは同情が寄るように、なるべく哀れっぽいところを見せて、心の中では、どうしてももう一遍だけあそこの家へ戻ってやる、今に見ていろと思いもし、又その思いがいつかは遂げられるだろうと言う望みに生きてもいるのだった。
それに、品子は、庄造のことをたよりない人とは思うけれども、どう言うものか憎むことが出来なかった。あんな具合に、何の分別もなくふらふらしていて、周りの人達が右といえば右を向き、左といえば左を向くという風だから、今度にしてもあの連中のいいようにされているのであろうが、それを考えると、子供を一人歩きさせているような、こころもとない、可哀そうな感じがするのである。
そしてもともと、そういう点にへんな可愛気のある人なので、一人前の男と思えば腹が立つこともあったけれども、いくらか自分より下に見下して扱うと、妙にあたりの柔らかい、優しい肌合いがあるものだから、だんだんそれにほだされて抜きさしがならないようになり、持って来た物までみんな注ぎ込んで、裸にされて放り出されてしまったのだが、彼女としてはそんなにまでして尽してやったと言うところに、なおさら未練が残るのである。
品子の独白は続く
全く、この一・二年間のあの家の暮らしは、半分以上は彼女の痩せ腕で支えていたようなものではないか。いいあんばいにお針が達者だったから、近所の仕事をもらって来ては夜の眼も寝ずに縫い物をして、どうやらしのぎをつけていたので、彼女の働きがなかったら、母親なぞがいくら威張ってもどうにもなりはしなかったではないか。
おりんは土地での嫌われ者、庄造はあの通りでさっぱり信用がなかったから、諸払いの滞りなどもやかましく催促されたものだが、彼女への同情があったればこそ節季が越せて行ったのではないか。
それだのにあの恩知らずの親子が、欲に眼がくれてああ言う者を引きずり込んで、牛を馬に乗りかえた気でいるけれども、まあ見ているがいい、あの女にあの家の切り盛りが出来るかどうか、持参金付きは結構だけれど、なまじそんなものがあったら、一層嫁の気随気儘(きずいきまま)が募るであろうし、庄造もそれをアテにして怠けるであろうし、結局親子三人の思わくが皆それぞれに外れて来るところから、争いの種が尽きないであろう。
その時分になって、前の女房の有難みが初めて本当に分かるのだ。品子はこんなふしだらではなかった、こう言う時にああもしてくれた、こうもしてくれたと、庄造ばかりでなく、母親までがきっと自分の失策を認めて、後悔するのだ。あの女は又あの女で、さんざんあの家を掻き廻した揚句の果てに、飛び出してしまうのが落ちなのだ。
そうなることは今から明々白々で、太鼓判を押してやりたいくらいであるのに、それが分からないとは憐れな人達もあればあるものよと、内心せせら笑いながら時機を待つつもりでいるのだが、しかし用心深い彼女は、待つにつけてはリリーを預かっておくと言う一策を考えついたのであった。
彼女はいつも、上の学校を一・二年でものぞいたことがあると言う福子に対して、教育の点では引け目を感じていたのであるが、でも本当の知恵くらべなら、福子にだっておりんにだって負けるものかと言う自負心があるので、リリーを預かると言う手段を思いついた時は、我ながらの妙案にひとりで感心してしまった。
なぜかといって、リリーさえこちらへ引き取って置いたら、恐らく庄造は雨につけ、風につけ、リリーのことを思い出すたびに彼女のことを思い出し、リリーを不憫と思う心が、知らず知らず彼女を憐れむ心にもならうからである。
そして、そうすれば、いつまでたっても精神的に縁が切れない理屈であるし、そこへ持って来て福子との仲がシックリ行かないようになると、いよいよリリーが恋しいと共に前の女房が恋いしくなろう。
彼女が未だに再縁もせず、猫を相手にわびしく暮らしていると聞いては、一般の同情が集まるのは無論のこと、庄造だって悪い気持ちはするはずがなく、ますます福子に嫌気がさすようになるであろうから、手を下さずして彼らの仲を割くことに成功し、復縁の時期を早めることが出来る。
―――ま、そうおつらえ向きに行ってくれたら幸せであるが、彼女自身はそうなる見込みを立てていた。ただ問題はリリーを素直に引き渡すかどうかと言うことであったが、それとても、福子の嫉妬心を煽り立てたら大丈夫うまく行くつもりでいた。
だからあの手紙の文句なんぞも、そう言う深謀遠慮をもって書かれていたので、単純ないたずらや嫌がらせではなかったのであるが、お気の毒ながら頭の悪い連中には、どうして私が好きでもない猫を欲しがるのか、とてもその真意がつかめっこあるまい、そしていろいろ滑稽きわまる邪推をしたり、子供じみた騒ぎ方をするであろうと言うところに、抑えきれない優越感を覚えたのであった。
陰謀よりも猫が好き
とにかく、そんな訳であるから、そのせっかくのリリーに逃げられた時の落胆と、思いがけなくそれが戻って来た時の喜びとがどんなに大きかったとしても、畢竟(ひっきょう、結局)それは得意の「深謀遠慮」に基ずく打算的な感情であって、本当の愛着ではないはずなのだが、あの時以来、一緒に二階で暮らすようになってみると、全く予想もしなかった結果が現れて来たのである。
彼女は夜な夜な、その一匹の日なた臭い獣を抱えて同じ寝床の中に寝ながら、どうして猫と言うものはこんなにも可愛らしいのであろう、それだのに又、昔はどうしてこの可愛さが理解出来なかったのであろうと、今では悔恨と自責の念に駆られるのであった。
おおかた芦屋時代には、最初に変な反感を抱いてしまったので、この猫の美点が眼にはいらなかったのであろうが、それと言うのも、焼餅があったからなのである。
焼餅のために、本来可愛らしいしぐさがただもう憎らしく見えたのである。
たとえば彼女は、寒い時分に夫の寝床へもぐり込んで行くこの猫を憎み、同時に夫を恨んだものだが、今になってみれば何の憎むことも恨むこともありはしない。現に彼女も、もうこの頃では独り寝の寒さがしみじみこたえているではないか。まして猫と言う獣は人間よりも体温が高いので、ひとしお寒がりなのである。猫に暑い日は土用の三日間だけしかないと言われるのである。
そうだとすれば、今は秋の半ばであるから、老年のリリーが暖かい寝床へ慕い寄るのは当然ではないか。いや、それよりも、彼女自身が、こうして猫と寝ていると、この暖かいことはどうだ! 例年ならば、今夜あたりは湯たんぽなしでは寝られないであろうのに、今年はまだそんなものも使わないで、寒い思いもせずにいるのは、リリーがはいって来てくれるお陰ではないか。
彼女自身が、夜ごと夜ごとにリリーを放せなくなっているではないか。
そのほか昔は、この猫の我がままを憎み、相手によって態度を変えるのを憎み、陰日なたのあるのを憎んだけれども、それもこれも、みんなこちらの愛情が足らなかったからなのだ。
猫には猫の知恵があって、ちゃんと人間の心待ちが分る。その証拠には、こちらが今までのようでなく、本当の愛情を持つようになったら、すぐ戻って来てこの通りなれなれしくするではないか。彼女が自分の気持ちの変化を意識するより、リリーのほうがより早く嗅ぎつけたくらいではないか。
品子は今まで、猫はおろか人間に対しても、こんなにこまやかな情愛を感じたこともなく、示したこともないような気がした。それは一つには、おりんをはじめいろいろな人から情の強い女だと言われていたものだから、いつか自分でもそう思わされていたせいであったが、この間からリリーのために捧げ尽した辛労と心づかいとを考える時、自分のどこにこんな暖かい、優しい情緒が潜んでいたのかと、今さら驚かれるのであった。
そういえば昔、庄造がこの猫の世話を決して他人の手にゆだねず、毎日食事の心配をし、二・三日置きにフンシの砂を海岸まで取り換えに行き、暇があるとノミを取ってやったりブラシをかけてやったりし、鼻が乾いてはしないか、便が軟らか過ぎはしないか、毛が脱けはしないかと始終気をつけて、少しでも異状があれば薬を与えると言う風に、まめまめしく尽してやるのを見て、あの怠け者によくあんな面倒が見られることよと、ますます反感を募らしたものだが、あの庄造のしたことを今は自分がしているではないか。
しかも彼女は、自分の家に住んでいるのではないのである。自分の食べるだけのものは、自分で儲けて妹夫婦へ払い込むと言う条件だから、まるきりの居候ではないが、何かと気が置ける中にいて、この猫を飼っているのである。これが自分の家であったら、台所を漁って残り物を探すけれども、他人の家ではそうも出来ないところから、自分が食べるものを食べずに置くか、市場へ行って何かしら見つけて来てやらねばならない。
そうでなくても、つましい上にもつましくしている場合であるのに、たとえわずかの買い物にもせよ、リリーのために出銭が増えると言うことは、随分痛い事なのである。それにもう一つ厄介なのは、フンシであった。芦屋の家は浜まで五・六丁(約600メートル)の距離だったから、砂を得るには便利であったが、この阪急の沿線からは、海は非常に遠いのである。
もっとも最初の二・三回は、工事現場の砂があったお陰で助かったけれども、あいにく近頃はどこにも砂なんかありはしない。そうかと言って、砂を換えずに放っておくと、とても臭気が激しくなって、しまいに階下へまで匂って来るので、妹夫婦が嫌な顔をする。
接近する品子とリリー
よんどころなく、夜がふけてから彼女はそうッとスコップを持って出かけて行って、その辺の畑の土をかいてきたり、小学校の運動場から滑り台の砂を盗んで来たり、そんな晩には又よく犬に吠えられたり、怪しい男に尾(つ)けられたり、―――全く、リリーのためでなかったら、誰に頼まれてこんな嫌な仕事をしよう、だが又リリーのためならばこう言う苦労をいとわないとは、何としたことであろうと思うと、返すがえすも、芦屋の時分に、なぜこの半分もの愛情をもって、この獣をいつくしんでやらなかったか、自分にそう言う心がけがあったら、よもや夫との仲が不縁になりはしなかったであろうし、このような憂き目は見なかったであろうものをと、今さらそれが悔まれてならない。
考えてみれば、誰が悪かったのでもない、みんな自分が至らなかったのだ。この罪のない、やさしい一匹の獣をさえ愛することが出来ないような女だからこそ、夫に嫌われたのではないか。自分にそう言う欠点があったからこそ、ハタの人間が付け込んだのではないか。………
十一月になると、朝夕の寒さがめっきり加わって、夜はときどき六甲のほうから吹きおろす風が、戸の隙間から冷えびえと沁み込むようになって来たので、品子とリリーとは前よりも一層くっついて、ひしと抱き合って、ふるえながら寝た。
そしてとうとうこらえきれずに、湯たんぽを使い始めたのであったが、その時のリリーの喜び方と言ったらなかった。品子は夜な夜な、湯たんぽの温もりと猫の活気とでぽかぽかしている寝床の中で、あのゴロゴロ言う音を聞きながら、自分のふところの中にいる獣の耳へ口を寄せて、
「お前のほうがわてよりよっぽど人情があってんなあ。」
と言ってみたり、
「わてのお陰で、お前にまでこんな淋しい思いさして、堪忍なあ。」
と言ってみたり、
「けどもうじきやで。もうちょっと辛抱しててくれたら、わてと一緒に芦屋の家へ帰れるようになるねんで。そしたら今度と言う今度は、三人仲よう暮らそうなあ。」
と言ってみたりして、ひとりでに涙が湧いて来ると、夜ふけの、真っ暗な部屋の中で、リリーよりほかには誰に見られる訳でもないのに、慌てて掛け布団をすっぽりかぶってしまうのであった。
庄造家を出る
福子が午後の四時過ぎに、今津の実家へ行って来ると言って出かけてしまうと、それまで奥の縁側で蘭の鉢をいじくっていた庄造は、待ち構えていたように立ち上って、
「お母さん」
と、勝手口へ声をかけたが、洗濯をしている母親には、水の音が邪魔になって聞えないらしいので、
「お母さん」
と、もう一度声を張り上げて言った。
「店を頼むで。―――ちょっとそこまで行って来るよってになあ。」
と、ジャブジャブいう音がふいと止まって、
「何やて?」
と、母親のしっかりした声が障子越しに聞えた。
「僕、ちょっとそこまで行って来るよってに―――」
「どこへ?」
「ついそこや。」
「何しに?」
「そないにしつこう聞かんかて―――」
そう言って、一瞬間むっとした顔つきで、鼻の孔をふくらましたが、すぐ又思い返したらしく、あの持ち前の甘えるような口調になって、
「あのなあ、ちょっと三十分ほど、球つき(ビリヤード)に行かしてくれへんか。」
「そうかてお前、球はつかんちゅう約束したのんやないか。」
「一遍だけ行かしてエな。何せもう半月もついてェへんよってに。頼みまっさ、ほんまに。」
「ええか、悪いか、わてには分からん。福子のいる時に、答えて行っとくなはれ。」
「何でェな。」
その妙に力張ったような声を聞くと、裏口のほうでタライの上につくばっている母親にも、せがれが怒った時にするだだッ児じみた表情が、はっきり想像出来るのであった。
「何でいちいち、女房に答えんなりまへんねん。ええも悪いも福子に聞いてみなんだら、お母さんには言われしまへんのんか。」
「そうやないけど、気をつけてて下さいて頼まれてるねんが。」
「そしたらお母さん、福子の廻し者だっかいな。」
「阿呆らしいもない。」
そう言ったきり取り合わないで、又水の音を盛んにジャブジャブと立て始めた。
「いったいお母さん僕のお母さんか、福子のお母さんか、どっちだす? なあ、どっちだすいな。」
「もう止めんかいな、そんな大きな声出して、近所へ聞えたらみっともないがな。」
「そしたら、洗濯後にして、ちょっとここへ来とくなはれ。」
「もう分かってる、もう何も言わへんさかいに、どこなと好きなとこへ行きなはれ。」
「ま、そない言わんと、ちょっと来なはれ。」
なんと思ったか庄造は、いきなり勝手口へ行って、流し元にしやがんでいる母親の、シャボンの泡だらけな手首を掴むと、無理に奥の間へ引き立てて来た。
「なあ、お母さん、ええ折やよってに、ちょっとこれ見てもらいまっさ。」
「何や、急(せ)からしう、………」
「これ、見てごらん、―――」
夫婦の居間になっている奥の六畳の押入れを開けると、下の段の隅ッこの、柳行李と用箪笥(ようだんす)の隙間の暗い穴ぼこになった所に、紅くもくもくかたまっているものが見える。
「あすこにあるのん、何や思いなはる。」
「あれかいな。………」
「あれみんな福子の汚れ物だっせ。あんな具合に後から後から突っ込んどいて、ちょっとも洗濯せエへんので、汚いもんがあそこに一杯溜ってて、箪笥の引き出しかて開けられへんねんが。」
「おかしいなあ、あの娘のもんは先繰り洗濯屋へ出してるのんに、………」
「そうかて、まさかお腰(こし、下着)だけは出されへんやろが。」
「ふうむ、あれはお腰かいな。」
「そうだんが。なんぼなんでも女の癖にあんまりだらしないさかいに、僕もう呆れてまんねんけど、お母さんかて様子見てたら分かってるのんに、なんで小言言うてくれしまへん? 僕にばっかりやかましいこと言うといて、福子にやったら、こないな道楽されてても見ん振りしてなはんのんか。」
「こんな所にこんなもんが突っ込んであること、わてがなんで知るかいな。………」
「お母さん」
不意に庄造はびっくりしたような声をあげた。母が押入れの段の下へもぐり込んで行って、その汚れ物をごそごそ引き出し始めたからである。
「それ、どないするねん?」
「この中綺麗にしてやろ思って、………」
「やめなはれ、汚い!………やめなはれ!」
「ええがな、わてに任しといたら、………」
「なんじゃいな、姑が嫁のそんなもん触うたりして! 僕お母さんにそんなことしてくれいえしまへんで。福子にさしなはれ言うてんで。」
おりんは聞えない振りをして、その薄暗い奥のほうから、まるくつくねてある紅い英ネル(木綿生地)の束をおよそ五つ六つ取り出すと、それを両手に抱えながら勝手口へ運んで行って、洗濯バケツの中へ入れた。
「それ、洗うてやんなはんのんか?」
「そんなこと気にせんと、男は黙ってるもんや。」
「自分のお腰の洗濯ぐらい、何で福子にさされまへん、なあお母さん。」
「うるさいなあ、わてはこれをバケツに入れて、水張っとくだけや。こないしといたら、自分で気イ付いて洗濯するやろが。」
「阿呆らしい、気イ付くような女だっかいな。」
母はあんなことを言っているけれど、きっと自分が洗ってやる気に違いないので、なおさら庄造は腹の虫が納まらなかった。そして着物も着換えずに、厚司(仕事着)姿のまま土間の板草履を突っかけると、ぷいと自転車へ飛び乗って、出かけてしまった。
自転車をこいで
さっき球つきに行きたいと言ったのは、本当にそのつもりだったのであるが、今の一件で急に胸がムシャクシャして来て、球なんかどうでもよくなったので、なんというアテもなしに、ベルをやけに鳴らしながら芦屋川沿いの遊歩道を真っすぐ新国道へ上ると、つい業平橋を渡って、ハンドルを神戸のほうへ向けた。まだ五時少し前頃であったが、一直線につづいている国道の向こうに、早くも晩秋の太陽が沈みかけていて、太い帯になった横流れの西日が、ほとんど路面と平行にさしている中を、人だの車だのがみんな半面に紅い色を浴びて、恐ろしく長い影をひきながら通る。
ちょうど真正面にその光線のほうへ向って走っている庄造は、鋼鉄のようにぴかぴか光る舗装道路の眩しさを避けて、うつむき加減に、首を真横にしながら、森の公設市場前を過ぎ、小路の停留所へさしかかったが、ふと、電車線路の向こう側の、とある病院の塀外に、畳屋の塚本が台を据えてせっせと畳を刺しているのが眼に留まると、急に元気づいたように乗り着けて行って、
「忙しおまっか。」
と、声をかけた。
「やあ」
と塚本は、手は休めずに眼で頷いたが、日が暮れぬ間に仕事を片付けてしまおうと、畳へきゅッと針を刺し込んでは抜き取りながら、
「今時分、どこへ行きはりまんね?」
「別にどこへも行かしまへん。ちょっとこの辺まで来てみましてん。」
「僕に用事でもおましたんか。」
「いいえ、違いま。―――」
そう言ってしまってハッとしたが、仕方がなしに眼と鼻の間へクシャクシャとしたしわを刻んで、曖昧な作り笑いをした。
「今ここ通りかかったのんで、声かけてみましたんや。」
「そうだっか。」
そして塚本は、自分の眼の前に自転車を停めて突っ立っている人間になんか、構っていられないと言わんばかりに、すぐ下を向いて作業を続けたが、庄造の身になってみれば、いくら忙しいにしたところで、「近頃どうしているか」とか、「リリーのことはあきらめたか」とか、そのくらいな挨拶はしてくれてもよさそうなものだのに、心外な気がしてならなかった。
それと言うのが、福子の前ではリリー恋いしさを一生懸命に押し隠して、リリーの「リ」の字も口に出さないでいるものだから、それだけ千万無量の思いが胸に鬱積している訳で、今はからずも塚本に出会ってみると、やれやれこの男に少しは切ない心の中を聞いてもらおう、そうしたら幾らか気が晴れるだろうと、すっかり当て込んでいたのであったが、塚本としてもせめて慰めの言葉ぐらい、でなければ無沙汰の詑びぐらい、言わなければならないはずなのである。
なぜかと言って、そもそもリリーを品子のほうへ渡す時に、その後どう言う待遇を受けつつあるか、ときどき塚本が庄造の代わりに見舞いに行って、様子を見届けて、報告をすると言う堅い約束があったのである。もちろんそれは二人の間だけの申し合わせで、おりんや福子には絶対秘密になっていたのだが、しかしそう言う条件があったからこそ大事な猫を渡してやったのに、あれきり一度もその約束を実行してくれたことがなく、うまうま人をペテンにかけて、知らん顔をしているのであった。
だが、塚本は、空とぼけている訳ではなくて、日頃の商売の忙しさに取り紛れてしまったのであろうか。
ここで会ったのを幸いに、ひと言ぐらい恨みを言ってやりたいけれども、こんなに夢中で働いている者に、今さら呑気らしく猫のことなんぞ言い出せもしないし、言い出したところで、あべこべに怒鳴り付けられはしないであろうか。
庄造は、夕日がだんだん鈍くなって行く中で、塚本の手にある畳針ばかりがいつまでもきらきら光っているのを、見とれるともなく見とれながらぼんやりたたずんでいるのであったが、ちょうどこのあたりは国道筋でも人家がまばらになっていて、南側のほうには食用カエルを飼う池があり、北側のほうには、衝突事故で死んだ人々の供養のために、まだ真新しい、大きな石の国道地蔵が立っているばかり。
この病院のうしろのほうは田んぼつづきで、ずうっと向こうに阪急沿線の山々が、ついさっきまでは澄み切った空気の底にくっきりとひだを重ねていたのが、もう黄昏の蒼い薄もやに包まれかけているのである。
「そんなら、僕、失敬しまっさ。―――」
「ちとやって来なはれ。」
「そのうちゆっくり寄せてもらいま。」
片足をペダルへかけて、二・三歩とッとッと行きかけたけれども、やっぱりあきらめきれないらしく、
「あのなあ、―――」
と言いながら、又戻って来た。
「塚本君、えらいお邪魔しまっけど、実はちょっと聞きたいことがおまんねん。」
「何だす?」
「僕これから、六甲まで行ってみたろか思いまんねんけど、………」
やっと一畳縫い終えたところで、立ち上りかけていた塚本は、
「何しにいな?」
と呆れた顔をして、かかえた畳をもう一遍トンと台へ戻した。
「そうかて、あれきりどないしてるやら、さっぱり様子分かれしまへんさかいにな。………」
「君、そんなこと、真面目で言うてなはんのんか。置きなはれ、男らしいもない!」
「違いまんが、塚本君!………そうやあれへんが。」
「そやさかいに僕あの時にも念押したら、あの女に何の未練もない、顔見るだけでもケッタクソが悪い言いなはったやおまへんか。」
「ま、塚本君、待つとくなはれ! 品子のことやあれへんが。猫のことだんが。」
「何と、猫?―――」
塚本の眼元と口元に、突然ニッコリとほほ笑みが浮かんだ。
「ああ、猫のことだっか。」
「そうだんが。―――君あの時に、品子があれを可愛がるかどうか、ときどき様子見に行ってくれる言いなはったのん、覚えたはりまっしゃろ?」
「そんなこと言いましたかいな、何せ今年は、水害からこちらえらい忙しおましたさかいに、―――」
「そら分かってま。そやよってに、君に行ってもらはう思ってェしまへん。」
せいぜい皮肉にそう言ったつもりだったのであるが、相手は一向感じてくれないで、
「君、まだあの猫のこと忘れられしまへんのんか。」
「何で忘れまつかいな。あれからこちら、品子の奴がいじめてェへんやろか、あんじょう懐いてるやろか思うたら、もうその事が心配でなあ、毎晩夢に見るぐらいだすねんけど、福子の前やったら、そんなことちょっとも言われしまへんよってに、なおのことここが辛うてつろうて、………」
と、庄造は胸を叩いてみせながらべそをかいた。
「………ほんまのとこ、もう今までにも一遍見に行こ思ってましてんけど、何せこのところひと月ほど、ひとりやったらめったに出してもらはれしまへん。それに僕、品子に会わんならんのんかないまへんよってに、あいつに見られんようにして、リリーにだけそうッと会うて来るようなこと、出来しまへんやろか?」
「そら、むずかしいおまんなあ。―――」
いい加減に堪忍してくれと言う催促のつもりで、塚本はおろした畳へ手をかけながら、
「どないしたかて見られまんなあ。それに第一、猫に会いに来た思わんと、品子さんに未練あるのんや思われたら、厄介なことになりまんがな。」
「僕かてそない思われたらかないまへんねん。」
「もうあきらめてしまいなはれ。人にやってしまうたもん、どない思うたかてショウがないやおまへんか、なあ石井君。―――」
「あのなあ、」
と、それには答えないで、別なことを聞いた。
「あの、品子はいつも二階だっか、階下だっか?」
「二階らしおまっけど、階下へかて降りて来まっしゃろ。」
「家空けることおまへんやろか?」
「分かりまへんなあ。―――裁縫したはりますさかいに、大概家らしおまっけど。」
「風呂へ行く時間、何時頃だっしゃろ?」
「分かりまへんなあ。」
「そうだっか。そしたら、えらいお邪魔しましたわ。」
「石井君」
塚本は、畳を抱えて立ち上った間に、早くも一・二間離れかけた自転車の後ろ姿に言った。
「君、ほんまに行きはりまんのか。」
「どうするかまだ分かれしまへん。とにかく近所まで行ってみまっさ。」
「行きなはるのんは勝手だすけど、後でゴタゴタ起こったかて、かかわりあうのんイヤだっせ。」
「君もこんなこと、福子やお袋に言わんと置いとくなはれ。頼みまっさ。」
そして庄造は、首を右左へ揺さ振り振り、電車線路を向こう側へ渡った。
リリーに会いに六甲へ
これから出かけて行ったところで、あの一家の者達に顔を合わせないようにして、こつそりリリーに会うなんと言ううまい寸法に行くであろうか。
いいあんばいに裏が空地になっているから、ポプラの陰か雑草の中にでも身を潜めて、リリーが外へ出て来るのを気長に待っているよりほかに手はないのだが、あいにくなことに、こう暗くなってしまっては、出て来てくれても中々発見が困難であろう。それにもうそろそろ初子の亭主が勤務先から帰って来るであろうし、晩飯の支度で勝手口のほうが忙しくなるであろうから、そういつまでも空巣狙いみたいにうろうろしている訳にも行かない。とすると、もっと時間の早い時に出直すほうがいいのだけれども、しかしリリーに会える会えないは二の次として、久し振りに女房の眼を盗んで、あちらこちらを乗り廻せると言うことだけでも、愉快でたまらないのであった。
実際、今日を外してしまうと、こう言う時はもう半月待たないと来ないのである。福子はおりおり親父の所へお小遣いをセビリに行くのだが、それが大体ひと月に二度、お朔日(ついたち、1日)前後と十五日前後とにきまっていて、行けば必ず夕飯を呼ばれ、早くて八・九時頃に帰るのが例であるから、今日も今から三・四時間は自由が楽しまれるのであって、もし自分さえ飢えと寒さに耐える覚悟なら、あの裏の空地に、少なくとも二時間は立っている余裕があるのである。
だからリリーが晩飯の後でぶらつきに出かける習慣を、今も改めないでいるものとすれば、ひょっとしたらあそこ会えるかも知れない。そういえばリリーは、食後に草の生えている所へ行って、青い葉を食べる癖があるので、なおさらあの空地は有望な訳だ。
―――そんなことを考えながら、甲南学校前あたりまでやって来ると、国粋堂と言うラジオ屋の前で自転車を停めて、外から店を覗いてみて、主人がいるのを確かめてから、
「こんにちは」
と、表のガラス戸を半分ばかり開けた。
「えらいすんまへんけど、二十銭貸しとくなはれしまへんか。」
「二十銭でよろしおまんのか。」
知らない顔ではないけれども、いきなり飛び込んで来て心やすそうに言われる程の仲やあれへん、と、そう言いたげに見えた主人は、二十銭では断りもならないので、手提げ金庫から十銭玉を二つ取り出して、黙って手のひらへ載せてやると、すぐ向こう側の甲南市場へ駈け込んで、アンパンの袋とタケノコの皮包を懐ろに入れて戻って来て、
「ちょっと台所使わしとくなはれ。」
人がよいようでへんにずうずうしいところのある彼は、そう言うことには馴れたものなので、「何しなはんね」と言われても「訳がありまんねん」とばかり、ニヤニヤしながら勝手口へ廻って行って、タケノコの皮包の鶏の肉をアルミニウムの鍋へ移すと、ガスの火を借りて水煮きにした。そして「すんまへんなあ」を二十遍ばかりも繰り返しながら、
「いろいろ無心言いまっけど、今一つ聴いとくなはれしまへんか。」
と、自転車に付けるランプの借用を申し込んだが、「これ持って行きなはれ」と主人が奥から出して来てくれたのは、「魚崎町三好屋」と言う文字のある、どこかの仕出屋の古ちょうちんであった。
「ほう、えらい骨董物だんなあ。」
「それやったら大事おまへん。ついでの時に返しとくなはれ。」
草むらに潜む庄造
庄造は、まだおもてが薄明るいので、そのちょうちんを腰に挿して出かけたが、阪急の六甲の停留所前、「六甲登山口」と記した大きな標柱の立っている所まで来て、自転車を角の休み茶屋に預けて、そこから二・三丁上にある目的の家のほうへ、少し急なだらだら道を登って行った。そして家の北側の、裏口のほうへ廻って、空地の中へはいり込むと、二・三尺の高さに草がぼうぼうと生えているひとかたまりの草むらのかげにしゃがんで、息を殺した。
ここでさっきのアンパンをかじりながら、二時間の間辛抱してみよう、そのうちにリリーが出て来てくれたら、お土産の鶏の肉を与えて、久しぶりに肩へ飛び着かせたり、口の端を舐めさせたり、楽しいいちゃつき合いをしようと、そういうつもりなのであった。
いったい今日は面白くないことがあったのでアテもなく外へ飛び出したら、足が自然に西のほうへ向いたばかりでなく、塚本なんぞに出会ったものだから、とうとう途中で決心をして、ここまで延(の)してしまったのだが、こうなることと分かっていたらコートを着て来ればよかったのに、仕事着の下に毛糸のシャツを着込んだだけでは、さすがに寒さが身に沁みる。
庄造は肩をぞくッとさせて、星がいちめんに輝き始めた夜空を仰いだ。板草履を穿いた足に冷めたい草の葉が触れるので、ふと気が付いて、帽子だの肩だのをなでてみると、おびただしい露が降りている。なるほど、これでは冷える訳だ、こうして二時間もうずくまっていたら、風邪を引いてしまうかも知れない。
だが庄造は、台所のほうから魚を焼く匂いが匂って来るので、リリーがあれを嗅ぎ付けてどこかから帰って来そうな気がして、異様な緊張を覚えるのであった。彼は小さな声を出して、「リリーや、リリーや」と呼んでみた。
何か、あの家の人達には分らないで、猫にだけ分かる合図の方法はないものかとも思ったりした。彼がつくばっている草むらの前のほうに、葛の葉が一杯に繁っていて、その葉の中でときどきピカリと光るものがあるのは、多分夜露の玉か何かが遠くのほうの電灯に反射しているせいなのだけれども、そうと知りつつ、そのたびごとに猫の眼か知らんとはっと胸を躍らせた。………あ、リリーかな、やれ嬉しや! そう思った途端に動悸が打ち出して、みぞおちの辺りがヒヤリとして、次の瞬間にすぐ又がっかりさせられる。
こう言うとおかしな話だけれども、まだ庄造はこんなヤキモキした心待ちを人間に対してさえ感じたことはないのであった。せいぜいカフェの女を相手に遊んだぐらいが関の山で、恋愛らしい経験といえば、前の女房の眼をかすめて福子と逢引きしていた時代の、楽しいような、じれったいような、変にわくわくした、落ち着かない気分、―――まああれぐらいなものなのだが、それでもあれは両方の親が内々で手引きをしてくれ、品子の手前をうまくごまかしてくれたので、無理な首尾をする必要もなく、夜露に打たれてアンパンをかじるような苦労をしないでもよかったのだから、それだけ真剣味に乏しく、会いたさ見たさもこんなに一途ではなかったのであった。
庄造は、母親からも女房からも自分が子供扱いにされ、一本立ちの出来ない低能児のようにみなされるのが、非常に不服なのであるが、さればと言ってその不服を聴いてくれる友達もなく、悶々の情を胸の中に納めていると、何となく独りぽっちな、頼りない感じが湧いて来るので、そのためになおリリーを愛していたのである。
実際、品子にも、福子にも、母親にも分かってもらえない淋しい気持ちを、あの哀愁に充ちたリリーの眼だけが本当に見抜いて、慰めてくれるように思い、又あの猫が心の奥に持っていながら、人間に向って言い現わすすべを知らない畜生の悲しみと言うようなものを、自分だけは読み取ることが出来る気がしていたのであったが、それがお互いに別れ別れにされてしまって四十余日になるのである。
そして一時は、もうそのことを考えないように、なるべく早くあきらめるように努めたことも事実だけれども、母や女房への不平が溜って、その鬱憤のやり場がなくなって来るに従い、いつか再び強い憧れが頭をもたげて、抑えきれなくなったのであった。
まったく、庄造の身になってみると、ああ言う厳しい足止めをされて、出るにも入るにも干渉を受けたのでは、かえって恋いしさを焚き付けられるようなもので、忘れようにも忘れる暇がなかったのであるが、それにもう一つ気になったのは、あれきり塚本から何の報告もないことであった。あんなに約束しておきながら、どうして何とも言って来てくれないのか。
仕事が忙しいのならやむをえないが、ひよっとするとそうでなく、彼に心配させまいとして、何か隠しているのではないか。たとえば品子にいじめられて、食うや食わずでいるためにひどく衰弱してしまったとか、逃げて出たきり行方不明になったとか、病死したとか、言うようなことがあるのではないか。あれからこちら、庄造はよくそんな夢を見て、夜中にハッと眼を覚ますと、どこかで「ニヤア」とないているように思えるので、便所へ行くような風をしながら、そうっと起きて雨戸を開けてみたことも、一度や二度ではないのであるが、あまりたびたびそう言う幻にあざむかれると、今聞いた声や夢に見た姿は、リリーの幽霊なのではないか、逃げて来る道で野たれ死にをして、魂だけが戻ったのではないのかと、そんな気がして、ぞうっと身ぶるいが出たこともある。
だが又、いくら品子が意地の悪い女でも、塚本が無責任でも、まさかリリーに変わったことが起ったら黙っているはずもあるまいから、便りのないのは無事に暮らしている証拠なのだと、不吉な想像が浮かぶたびに打ち消し打ち消しして来たのであるが、それでも感心に女房の言いつけを忠実に守って、一度も六甲の方角へ足を向けたことがなかったと言うのは、監視が厳しかったばかりでなく、品子の網に引っかかるのが不愉快だからであった。彼にはリリーを引き取った品子の真意と言うものが、今でもハッキリしないのだけれども、ことによったら、塚本が報告を怠っているのも品子のさしがねではないのか、あいつはそう言う風にしてわざとおのれに気を揉ませて、おびき寄せようと言う腹ではないのかと、そんな邪推もされるので、リリーの安否を確かめたいと願う一方、みすみすあいつの罠にはまってたまるものかと言う反感が、それと同じくらい強かったのであった。
彼は何とかしてリリーには会いたいが、品子につかまることはイヤでたまらなかった。「とうとうやって来ましたね」と、あいつがへんに利口ぶって、得意の鼻をうごめかすかと思うと、もうその顔つきを浮かべただけでムシズが走った。元来庄造には彼一流のずるさがあって、いかにも気の弱い、他人の言うなり次第になる人間のように見られているのを、巧みに利用するのであるが、品子を追い出したのがやはりその手で、表面はおりんや福子に操られた形であるけれども、その実誰よりも彼が一番彼女を嫌っていたかも知れない。
そして庄造は、今考えても、いいことをした、いい気味だったと思うばかりで、不憫と言う感じは少しも起こらないのであった。
会えない二人
現に品子は、電灯のともっている二階のガラス窓の中にいるのに違いないのだが、雑草のかげにつくばいながらじっとそのあかりを見上げていると、またしてもあの、人を小馬鹿にしたような、賢女ぶった顔が眼先にちらついて、胸糞が悪くなって来る。せっかくここまで来たのであるから、せめて「ニヤア」と言うなつかしい声をよそながらでも聞いて帰りたい、無事に飼われていることが分かりさえしたら、それだけでも安心であるし、ここへ来た念が届くのであるから、いっそのことそうっと裏口を覗いてみたら、………あわよくば、初子をこっそり呼び出して、おみやげの鶏の肉を渡して、近状を聞かしてもらったら、………と、そう思うのであるが、あの窓のあかりを見て、あの顔を心に描くと、足がすくんでしまうのである。
うっかりそんな真似をしたら、初子がどう言う勘違いをして、二階の姉を呼びに行かないものでもないし、少なくとも後でしゃべることは確かであるから、「そろそろ計略が図にあたってきた」などと、うぬぼれるだけでもシャクに触る。とすると、やはりこの空地に根気よくうずくまっていて、リリーがここを通りかかる偶然の機会をとらえるよりほかはないのであるが、しかし今まで待って駄目なら、とても今夜はおぼつかない。
庄造はもう、袋の中のアンパンをみんな食べてしまった。そしてさっきから一時間半ぐらいは経ったような気がするので、だんだん家のほうの首尾が心配になって来た。母親だけなら面倒はないが、福子が先に帰って来ていたら、今夜ひと晩じゅう寝かしてもらえないで、あざだらけにされる。それもいいけれども、又明日から監視が厳重になる。
だが、一時間半も待つあいだにかすかななきごえも洩れて来ないのは、何だか変だ、ひょっとしたら、この間からたびたび見た夢が正夢で、もうこの家にいないのではないか。さっき魚を焼く匂いがした時が一家の夕飯だったとすると、リリーもあの時何かしら与えられるであろうし、そうすればきっと草を食べに出て来るのだが、来ないのを見るとどうも怪しい。………
庄造は、とうとうこらえきれなくなって、雑草の中から身を起こすと、裏木戸の際まで忍んで行って、隙間へ顔をあててみた。と、階下はすっかり雨戸が締まっていて、子供を寝かしつけているらしい初子の声がとぎれとぎれに聞えて来るほかには、何の物音もしない。
二階のガラス障子にでも、ほんの一瞬間でいいからさっと影がうつってくれたらどんなに嬉しいか知れないのに、ガラスの向こうに白いカーテンが静かに垂れているばかりで、その上のほうが薄暗く、下のほうが明るくなっているのは、品子が電灯を低く下して、夜作(よなべ)をしているのであろう。
ふと庄造は、あかりの下で一心に針を運びつつある彼女の傍らに、リリーがおとなしく背中をまるめて、「の」の字なりに寝ころびながら、安らかな眠りをむさぼっている平和な光景を眼前に浮かべた。
秋の夜長の、またたきもせぬ電灯の光が、リリーと彼女とただ二人だけを一つ輪の中に包んでいるほかは、天井のほうまでぼうっと暗くなっている室内。………夜が次第にふけて行く中で、猫はかすかにいびきをかき、人は黙々と縫い物をしている、わびしいながらもしんみりとした場面。………あのガラス窓の中に、そういう世界が繰りひろげられているとしたら、―――何か奇跡的なことが起こって、リリーと彼女とがすっかり仲良しになっていたとしたら、―――もし本当にそんな光景を見せられたら、焼餅を焼かずにいられるだろうか。正直のところ、リリーが昔を忘れてしまって現状に満足していられても、やはり腹が立つであろうし、そうかと言って、虐待されていたり死んでいたりしたのではなお悲しいし、どっちにしても気が晴れることはないのだから、いっそ何も聞かないほうがいいかも知れない。
庄造は、途端に階下の柱時計が「ぼん、………」と、半を打つのを聞いた。七時半だ、―――と思うと、彼は誰かに突き飛ばされたように腰を浮かしたが、二足三足行ってから引っ返して来て、まだ大事そうに懐に入れていたタケノコの皮包を取り出すと、それを木戸口や、五味箱の上や、あちらこちらへ持って行ってウロウロした。
どこか、リリーだけが気が付いてくれるような所へ置いて行きたいが、草むらの中では犬に嗅ぎ付けられそうだし、この辺へ置いたら家の者が見つけるであろうし、うまい方法はないか知らん。いや、もうそんなことに構ってはいられぬ。遅くとも今から三十分以内に帰らなかったら、又ひと騒ぎ起こるかも知れぬ。
「あんた、今頃まで何しててん!」―――と、そう言う声がにわかに耳のハタで聞えて、福子のイキリ立った剣幕がありありと見える。彼は慌てて葛の葉の繁っている間へ、タケノコの皮を開いて置いて、両端へ小石を載せて、又その上から適当に葉をかぶせた。そして空地を横ッ飛びに、自転車を預けた茶屋のところまで夢中で走った。
福子と庄造
その晩、庄造よりも二時間程おくれて帰って来た福子は、弟を連れてボクシングを見に行った話などをして、ひどく機嫌がよかった。そして明くる日、少し早めに夕飯を済ますと、
「神戸へ行かしてもらいまっせ。」
と、夫婦で新開地の聚楽館へ出かけた。
おりんの経験だと、福子はいつも今津の家へ行って来た当座、つまり懐にお小遣のある五・六日か一週間のあいだというものは、きまって機嫌がいいのである。このあいだに彼女は盛んに無駄使いをして、活動(映画)や歌劇見物などにも、二度ぐらいは庄造を誘って行く。
したがって夫婦仲もむつまじく、しごく円満におさまっているのだが、一週間目あたりからそろそろ懐が淋しくなって、一日家でごろごろしながら、間食をしたり雑誌を読んだりするようになりだすと、ときどき亭主に小言を言う。
もっとも庄造も、女房の景気のいい時だけ忠実ぶりを発揮して、だんだん出るものが出なくなると、現金に態度を変え、浮かぬ顔をして生返事をする癖があるのだが、結局双方から飛ばっちりを食う母親が、一番割りが悪いことになる。
だからおりんは、福子が今津へ駈け付けるたびに、やれやれこれで当分は安心だと思って、内々ほっとするのであった。
で、今度もちょうどそういう平和な一週間が始まっていたが、神戸へ行ってから三・四日たったある日の夕方、亭主と二人晩飯のちゃぶ台に向っていた福子は、
「こないだの活動、ちょっとも面白いことあれへなんだなあ。」
と、自分も行ける口なので、ほんのり眼のふちへ酔いを出しながら、
「―――なあ、あんたどない思うた?」
と、そう言って銚子を取り上げると、庄造がそれを引ったくるようにしてこちらからさした。
「一つ行こ。」
「もう、あかん。………酔うたわ、わて。」
「まあ、行こ、もう一つ。………」
「家で飲んだかて、おいしいことあれへん。それより明日どこぞへ行けへん?」
「ええなあ、行きたいなあ。」
「まだお小遣ちょっとも使うてエへんねんで。………こないだの晩、家で御飯たべて出て、活動見ただけやったやろ、そやさかいに、まだたぁんと持ってるねん。」
「どこにしょう、そしたら?………」
「宝塚、今月は何やってるやろ?」
「歌劇かいな。―――」
後に旧温泉と言う楽しみはあるにしてからが、何だかもう一つ気が乗らない顔つきをした。
「―――そないにたんとお小遣あるのんやったら、もっと面白いことないやろか。」
「何ぞ考えてエな。」
「紅葉見に行けへん?」
「箕面(みのお、大阪府箕面市)かいな。」
「箕面はあかんねん、こないだの水ですつくりやられてしもてん。それより僕、久しぶりで有馬へ行ってみたいねんけど、どうや、賛成せエへんか。」
「ほんに、………あれ、いつやったやろ?」
「もうちょうど一年ぐらい………いや、そうやないわ、あの時カジカがないてたわ。」
「そうや、もう一年半になるで。」
それは二人が人目を忍ぶ仲になりだして間もない時分、ある日瀧道の終点で落ち合い、神有電車で有馬へ行って、御所の坊の二階座敷で半日ばかり遊んで暮らしたことがあったが、涼しい渓川の音を聞きながら、ビールを飲んでは寝たり起きたりして過した、楽しかった夏の日のことを、二人ともはっきり思い出した。
「そしたら、また御所の坊の二階にしようか。」
「夏より今のほうがええで。紅葉見て、温泉にはいって、ゆっくり晩の御飯食べて、―――」
「そうしよう、そうしよう、もうそれにきめたわ。」
その明くる日は早お昼の予定であったが、福子は朝の九時頃からぽつぽつ身支度に取りかかりながら、
「あんた、汚い頭やなあ。」
と、鏡の中から庄造に言った。
「そうかも知れん、もう半月ほど床屋へ行けへんさかいにな。」
「そしたら大急ぎで行って来なはれ、今から三十分以内に。―――」
「そらえらいこッちや。」
「そんな頭してたら、わてよう一緒に歩かんわ。―――早うしなはれ!」
庄造は、女房が渡してくれた一円札を、左の手に持ってヒラヒラさせながら、自分の店から半丁程東にある床屋の前まで駈けて行ったが、いいあんばいに客が一人も来ていないので、
「早いとこ頼みまっさ。」
と、奥から出て来た親方に言った。
「どこぞ行きはりまんのんか。」
「有馬へ紅葉見に行きまんね。」
「そらよろしおまんなあ、奥さんも一緒だっか?」
「そうだんね。―――早お昼たべて出かけるさかい、三十分で頭刈って来なはれ言われてまんね。」
が、それから三十分過ぎた時分、
「お楽しみだんなあ、ゆっくり行って来なはれ。」
と、背中から親方が浴びせる言葉を聞き流して、家の前まで戻って来て、なにげなく店へひと足踏み込むと、そのまま土間に立ちすくんでしまった。
六甲行きがばれる
「なあ、お母さん、なんで今日までそれ隠してはりましてん。………」
と、突然そう言うただならぬ声が奥から聞えて来たからである。
「………何でそんなことがあったら、わてに言うとくなはれしまへん。………そしたらお母さん、わての味方してるみたいに見せかけといて、いつもそんなことさせてはったんと違いまっか。………」
福子が大分お冠を曲げているらしいことは甲高い物の言い方で分かる。母親のほうは明らかにやり込められている様子で、たまにひと言二た言ぐらい口答えをするけれども、ごまかすようにコソコソと言うので、よく聞えない。福子の怒鳴る声ばかりが筒抜けに響いて来るのである。
「………何? 行ったとは限らん?………阿呆らしい! 人の家の台所借って、鶏の肉煮いたりして、リリーの所やなかったら、どこへ持って行きまんね。………それにしたかて、あのチョウチン持って帰って、あんなところに直してあったこと、お母さん知ったはりましたんやろ?………」
彼女が母親をつかまえて、あんなキンキンした声を張り上げることはめったにないのだが、しかしたった今、彼が床屋へ行っていたわずかな間に、どうやら先日の国粋堂が、あの時の立て替えと古チョウチンとを取り返しに来たのだと見える。
ありていに言うと、あの晩庄造はあのチョウチンを自転車の先にぶら下げて帰って、福子に見とがめられないように、物置小屋の棚の上に押し上げて置いたのであるが、お袋には見当がついていたはずだから、出して渡してやったのかも知れない。
だが国粋堂は、いつでもいいようにと言っていながら、なんで取り返しに来たのだろう。まさかあんな古ちょうちんが惜しいこともあるまいに、この辺についででもあったのだろうか、それとも二十銭を借りっ放しにされたのが、腹が立ったのだろうか。
それに又、親父が来たのか、小僧が来たのか知らないが、鶏の話までして行かないでもいいではないか。
「………わてはなあ、相手がリリーだけやったら、何もうるさいこといえしまへんで。リリーに会いに行く言うても、リリーだけやあれへんさかいに、言いまんねんで。いったいお母さん、あの人とグルになって、わてをだますようなことして、すむと思うたはりまんのんか。」
そう言われると、さすがのおりんもグウの音も出ないで、小さくなっているのであるが、せがれの代りに怒られているのは可哀そうのようでもあり、ちょっといい気味のようでもある。
何にしても庄造は、自分がいたら中々福子の怒り方がこのくらいでは済むまいと思うと、危うく虎口を逃れた気がして、スワといえば戸外へ飛び出せるように、身構えをしながら立っていると、
「………いいえ、分かってま! あの人六甲へやったりして、今度はわてを追い出す相談してなはるねん。」
と、言うのにつづいてドタンという物音がして、
「待ちいな!」
「放しとくなはれ!」
「そうかて、どこへ行くねんな。」
「お父さんのところへ行って来ます、わての言うことが無理か、お母さんの言うことが無理か、―――」
「ま、今庄造が戻るさかいに―――」
ドタン、ドタンと、二人がさかんに争いながら店のほうへ出て来そうなので、慌てて庄造は往来へ逃げ延びて、五・六丁の距離を夢中で走った。それきり後がどうなったことやら分からなかったが、気が付いてみると、いつか自分は新国道のバスの停留所の前に来て、さっき床屋で受け取った釣銭の銀貨を、まだしっかりと手の中に握っていた。
再び六甲へ
ちょうどその日の午後一時頃、品子が朝のうちに仕上げた縫い物を、近所まで届けて来ると言って、普段着の上に毛糸のショールを引つかけて、小走りに裏口から出て行ったあと、初子がひとり台所で働いていると、そこの障子をごそッと一尺ばかり開けて、せいせい息を切らしながら庄造が中を覗き込んだので、
「あらッ」
と、飛び上りそうにすると、ピョコンと一つお時儀をしながら笑ってみせて、
「初ちゃん、………」
と言ってから、後ろのほうに気を配りつつ急にひそひそ声になって、
「………あの、今ここから品子出て行きましたやろ?」
と、セカセカした早口で言った。
「………僕今そこで会うてんけど、品子は気イ付けしまへなんだ。僕あのポプラの陰に隠れてましたよってにな。」
「何ぞ姉さんに用だっか?」
「めっそうな! リリーに会いに来ましてんが。―――」
そして、そこから庄造の言葉は、さも思いあまった、哀れっぽい切ない声に変わった。
「なあ、初ちゃん、あの猫どこにいてます?………すんまへんけど、ほんのちょっとでええさかい、会わしとくなはれ!」
「どこぞ、その辺にいてしまへんか。」
「そない思って、僕この近所うろうろして、もう二時間もあそこに立ってましてんけど、ちょっとも出て来よれしまへんねん。」
「そしたら、二階にいてるかしらん?」
「品子もうすぐ戻りまっしゃろか? 今頃どこへ行きましたんや?」
「ほんそこまで仕立物届けに。―――二・三丁の所だすよって、すぐ帰りまっせ。」
「ああ、どうしよう、ああ困った。」
そう言ってぎょうさんに体をゆすぶって、地団駄を踏みながら、
「なあ、初ちゃん、頼みます、この通りや。―――」
と、手をすり合わせて拝む真似をした。
「―――後生一生のお願いだす、今の間に連れて来とくなはれ。」
「会うて、どないしやはりまんね。」
「どうもこうもせえしまへん。無事な顔ひと眼見せてもろたら、気がすみまんねん。」
「連れて帰りはれしまへんやろなあ?」
「そんなことしまっかいな。今日見せてもろたら、もうこれっきり来えしまへん。」
初子は呆れた顔をして、穴の開くほど庄造を見つめていたが、何と思ったか黙って二階へ上って行って、すぐ段はしごの中段まで戻って来ると、
「いてまっせ。―――」
と、台所のほうへ首だけ突ん出した。
「いてまっか?」
「わて、よう抱きまへんよって、見に来とくなはれ。」
「行っても大事おまへんやろか。」
「すぐ降りとくなはれや。」
「よろしおま。―――そしたら、あがらしてもらいまっさ。」
「早いことしなはれ!」
庄造は、狭い、急な段はしごをのぼる間も胸がドキドキした。ようよう日頃の思いが叶って、会うことが出来るのは嬉しいけれども、どんな風に変わっているだろうか。野たれ死にもせず、行方不明にもならないで、無事にこの家にいてくれたのはありがたいが、虐待されて、痩せ衰えていなければいいが、………まさかひと月半の間に忘れるはずはないだろうけれど、なつかしそうに傍らへ寄って来てくれるかしらん? それとも例の、はにかんで逃げて行くかしらん?………芦屋の時代に、二・三日家を空けたあとで帰って来ると、もうどこへも行かせまいとして、すがりついたり舐め廻したりしたものであったが、もしもあんな風にされたら、それを振り切るのに又もう一度辛い思いをしなければならない。………
「ここだっせ。―――」
晴ればれとした午後の外光を遮って、窓のカーテンが締まっているのは、大方用心深い品子が出て行く時にそうしたのであろうか。―――そのために室内がもやもやとかげって、薄暗くなっている中に、信楽(しがらき)焼きのナマコの火鉢が置いてあって、なつかしいリリーはその傍らに、座布団を重ねて敷いて、前脚を腹の下へ折り込んで、背をまるくしながらうつらうつら眼をつぶっていた。
案じた程に痩せてもいないし、毛なみもつやつやとしているのは、相当に優遇されているからであろう。思ったよりも大事にされている証拠には、彼女のために専用の座布団が二枚も設けてあるばかりではない、たった今、お昼のご馳走に生卵をもらったと見えて、きれいに食べ尽したご飯のお皿と、卵の殻とが、新聞紙に載せて部屋の片隅に寄せてあり、又その横には、芦屋時代と同じようなフンシさえ置いてあるのである。
と、突然庄造は、久しい間忘れていたあの特有の匂いを嗅いだ。かつて我が家の柱にも壁にも床にも天井にもしみ込んでいたあの匂いが、今はこの部屋にこもっているのであった。彼は悲しみがこみ上げて来て、
「リリー、………」
と覚えずだみ声をあげた。するとリリーはようようそれが聞こえたのか、どんよりとしたものうげな瞳を開けて、庄造のほうへひどく無愛想な一瞥(いちべつ)を投げたが、ただそれだけで、何の感動も示さなかった。彼女は再び、前脚を一層深く折り曲げ、背筋の皮と耳たぶとをブルン!と寒そうにけいれんさせて、眠くてたまらぬと言うように眼を閉じてしまった。
今日はお天気がいい代りに、空気が冷え冷えと身にしむような日であるから、リリーにしたら火鉢の傍らを離れるのがイヤなのであろう。それに胃の腑(ふ)がふくらんでいるので、なおさら大儀なのでもあろう。
この動物の無精な性質をのみ込んでいる庄造は、こう言うそっけない態度には馴れているので、格別いぶかしみはしなかったが、でも気のせいか、そのおびただしく眼やにの溜った眼のふちだの、妙にしょんぼりとうずくまっている姿勢だのを見ると、わずかばかり会わなかった間に、又いちじるしく老いぼれて、影が薄くなったように思えた。
分けても彼の心を打ったのは、今の瞳の表情であった。在来とてもこんな場合に眠そうな眼をしたとはいえ、今日のはまるで行路病者のそれのような、精も根も涸れ果てた、疲労しきった色を浮かべているではないか。
「もう覚えてエしまへんで。―――畜生だんなあ。」
「阿呆らしい、人が見てたらあないに空とぼけまんねんが。」
「そうだっしゃろか。………」
「そうだんが。………そやさかいに、………すんまへんけど、ほんちょっとの間、初ちゃんここに待っててくれて、このふすま締めさしとくなはれしまへんか。………」
「そないして、何しやはりまんね。」
「何もせえしまへん。………ただ、あの、ちょっと、………膝の上に抱いてやりまんねん。………」
「そうかて、姉さん帰って来まっせ。」
「そしたら、初ちゃん、そっちの部屋から門見張ってて、見えたらすぐに知らしとくなはれ。頼みまっさ。………」
ふすまに手をかけてそう言っているうちに、もう庄造はずるずると部屋へはいって、初子を外へ締め出してしまった。そして、
「リリー」
と言いながら、その前へ行って、さし向いにすわった。
リリーは最初、せっかく昼寝しているのにうるさい! と言うような横着そうな眼をしばだたいたが、彼が眼やにを拭いてやったり、膝の上に乗せてやったり、首すじなでてやったりすると、格別嫌な顔もしないで、される通りになっていて、しばらくするうちに咽喉をゴロゴロ鳴らし始めた。
「リリーや、どうした? 体の具合悪いことないか? 毎日々々、可愛がってもろてるか?―――」
庄造は、今にリリーが昔のいちゃつきを思い出して、頭を押しつけに来てくれるか、顔を舐め廻しに来てくれるかと、一生懸命いろいろの言葉を浴びせかけたが、リリーは何を言われても、相変わらず眼をつぶったままゴロゴロ言っているだけであった。
それでも彼は背中の皮を根気よくなでてやりながら、少し心を落ち着けてこの部屋の中を眺めてみると、あの几帳面で癇(かん)性な品子のやり方が、ほんの些細な端々にもよく現れているように感じた。
たとえば彼女は、わずか二・三分の間留守にするにも、ちゃんとこうしてカーテンを締めて行くのである。のみならずこの四畳半の室内に、鏡台だの、タンスだの、裁縫の道具だの、猫の食器だの、便器だの、さまざまなものを並べて置きながら、それらが一糸乱れずに、それぞれ整然と片寄せられて、こての突き刺してある火鉢の中を覗いてみても、炭火を深くいけ込んだ上に、灰が綺麗に筋目を立ててならしてあり、三徳の上に載せてある瀬戸引きのヤカンまでが、研ぎ立てたようにピカピカ光っているのである。
が、それはまあ不思議はないとしても、奇妙なのはあの皿に残っている卵の殻だった。彼女は自分で食い扶持を稼いでいるので、決して楽ではないであろうに、貧しい中でもリリーに滋養分を与えると見える。
いや、そういえば、彼女が自分で敷いている座布団に比べて、リリーの座布団の綿の厚いことはどうだ。いったい彼女は何と思って、あんなに憎んでいた猫を大事にする気になったのであろう。
考えてみると庄造は、言わば自分の心がら(自業自得)から前の女房を追い出してしまい、この猫にまでも数々の苦労をかけるばかりか、今朝は自分が我が家の敷居をまたぐことが出来ないで、ついふらふらとここへやって来たのであるが、このゴロゴロいう音を聞きながら、むせるようなフンシの匂いを嗅いでいると、何となく胸が一杯になって、品子も、リリーも、可哀そうには違いないけれども、誰にもまして可哀そうなのは自分ではないか、自分こそ本当の宿なしではないかと、そう思われて来るのであった。
と、その時ばたばたと足音がして、
「姉さんもうついそこの角まで来てまっせ。」
と、初子が慌しくふすまを開けた。
「えッ、そら大変や!」
「裏から出たらあきまへん!………表へ、………表へ廻んなはれ!………履き物わてが持って行たげる! 早よ、早よ!」
彼は転げるように段はしごを駈け下りて、表玄関へ飛んで行って、初子が土間へ投げてくれた板草履を突っかけた。そして往来へ忍び出た途端に、チラと品子の後影が、ひと足違いで裏口のほうへ曲って行ったのが眼に留まると、恐い物にでも追われるように反対の方角へ一散に走った。
終わり
◇
原典は青空文庫を利用しました。初出は、「改造 新年号 第十八巻第一号」(1936年=昭和11年1月1日発行)と「改造 七月特大号 第十八巻第七号」(同年7月1日発行)




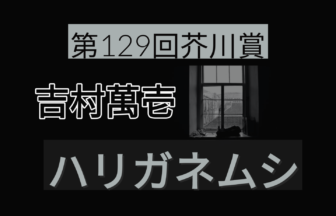

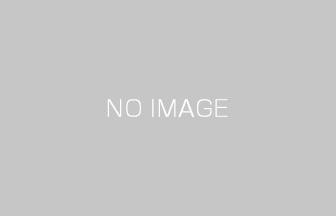


この記事へのコメントはありません。